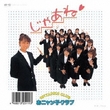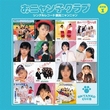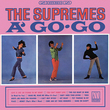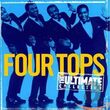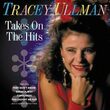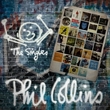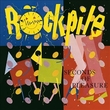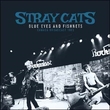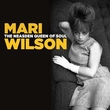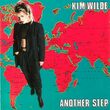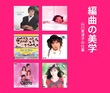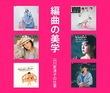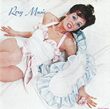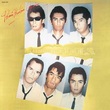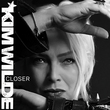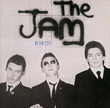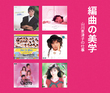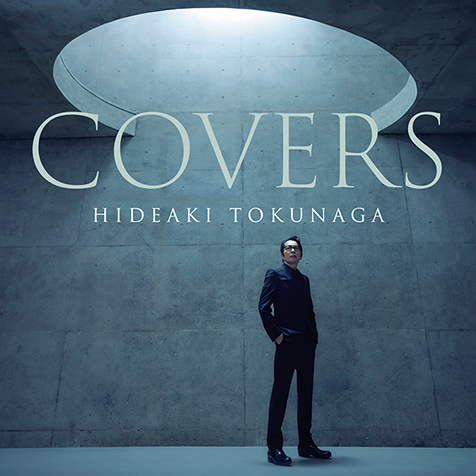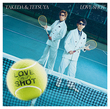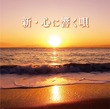タワーレコード新宿店~渋谷店の洋楽ロック/ポップス担当として、長年にわたり数々の企画やバイイングを行ってきた北爪啓之さんによる連載〈聴いたことのない旧譜は新譜〉。そのタイトル通り、本連載では旧譜と称されてしまった作品を現在の耳で新譜として紹介していきます。
第8回は、今年結成40周年を迎えたおニャン子クラブを大特集。7月には記念コンサートも開催され、新田恵利、樹原亜紀、富川春美、立見里歌、白石真子、横田睦美、布川智子、我妻佳代、杉浦美雪といった面々が集結して大きな話題となりました。そんなおニャン子クラブの楽曲を、北爪さんがモータウンの視点から深堀りします。 *Mikiki編集部
おニャン子クラブの楽曲はモータウンっぽい
おニャン子クラブはセンセーショナルな歌詞について語られることはあれど、なぜか音楽性が話題になる機会はあまりない。今年は記念すべき結成40周年のアニバーサリーイヤーなので、今回はその辺りに(軽めの足取りで)踏み込んでみたいと思う。
さて、単刀直入にいえば〈おニャン子の楽曲はモータウンっぽい〉。もちろん全てではないが、意識して聴いてみるとそれ風の曲が意外と多いことに気付くはずだ。とはいえ、文章で説明しても〈なぜ?の嵐〉状態の人がほとんどだとは思うので、本稿ではできる限り曲の動画も挙げながら話を進めていきたい。
その前にまずモータウンについて簡単におさらいをしておこう。1959年にデトロイトで設立されたモータウン・レコードは、〈サウンド・オブ・ヤング・アメリカ〉を旗印にポップで洗練されたソウルミュージックを次々とチャートに送り込んでいった名レーベルだ。専属シンガー、専属スタジオミュージシャン、専属作曲家チームによる自社内分業制という、さながらヒット量産工場のようなシステムを作り上げたのが画期的だった。
サウンド面では1960年代に多く活用された、いわゆる〈モータウンビート〉がじつに特徴的。軽快なテンポの4分の4拍子で、スネアが2拍目と4拍目にアクセントを置いたリズムパターンは、いちど聴いたら忘れ難い独特の魅力を持っている。シュープリームスの“You Can’t Hurry Love”や、フォー・トップスの“I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)”がその典型だろう。
ではモータウンビートを念頭に置いたうえで、おニャン子のデビューシングル“セーラー服を脱がさないで”(1985年)を聴いて頂きたい。
シンセや打ち込みによるいかにも80s歌謡なサウンドながら、2拍と4拍を強調したバックビートはモータウン風である。じつはこの曲は1983年にトレイシー・ウルマンがリリースした“Breakaway”が元ネタではないかと言われている。もともとは1964年にジャッキー・デシャノンとシャロン・シーリーが女性ソウルシンガーのアーマ・トーマスに書いた曲で、厳密にはモータウンビートではない。ところがウルマンがかなり性急なテンポでカバーしているため、原曲の南部的なアクが薄れてモータウンぽくなっているのが面白い。
1980年代は〈レトロがトレンディ〉な時代だった
“セーラー服を脱がさないで”との類似はお聴きの通りだが、“Breakaway”が同時代の音楽であるというのは重要なポイントである。その点に留意しつつ、ここで少しだけ当時の洋楽シーンに視点を移してみたい。
1980年代前半から半ばにかけてのロック/ポップスシーンでは、トレイシー・ウルマンを例に出すまでもなく〈60sリバイバル〉が1つのキーワードでもあった。とりわけモータウンテイスト(またはカバー)の楽曲が大ヒットを記録していることは注目に値する。
フィル・コリンズによる“You Can’t Hurry Love”のカバーが全英1位。
ザ・ジャムが放ったネオ・モータウンビートとも呼ぶべき“Town Called Malice”も同じく全英1位。
ホール&オーツがモータウンを完全咀嚼した“Maneater”は全米1位。しかもこれら3曲はすべて同じ1982年のヒットソングなのだ。
ほかにも、ロックパイルの“Heart”(1980年)、ストレイ・キャッツの“You Can’t Hurry Love”カバー(1981年)、マリ・ウィルソンの“Ecstacy”(1983年)、カトリーナ&ザ・ウェイヴスの“Walking On Sunshine”(1983年)、メイキン・タイムの“Here Is My Number”(1985年)、キム・ワイルドがシュープリームスをカバーした“You Keep Me Hangin’ On”(1986年)など、これだけで連載のテーマになってしまいそうなほど枚挙に暇がない。
ではなぜモータウンを含む60sリバイバルが起こったのかといえば、1980年代がポストモダンの時代だったからのように思える。過去のスタイルを引用や再構成して新たな文脈で提示するというポストモダン的発想で捉えることによって、1960年代の音楽やファッションは単なる懐古趣味ではなく、逆に新鮮でヒップなものとして受け止められていた。平たくいえば、〈レトロがトレンディ〉だったわけだ(この言い回しも80sならではだ)。