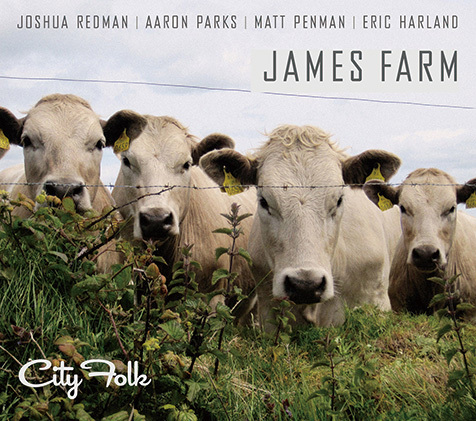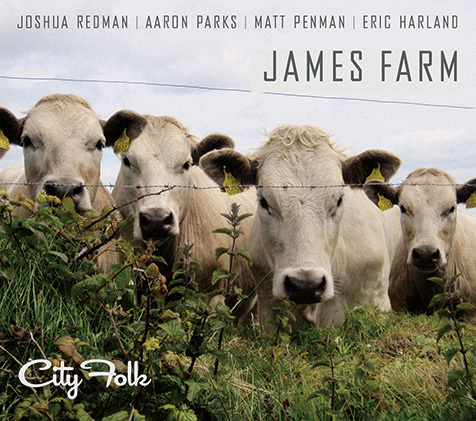このブログでは主に現代ジャズの音楽家について紹介してきましたが、今回は音楽家の紹介ではなく、2014年末~2015年初頭に発売された5作品のレビューを書きました。この中に見逃していた作品があれば是非購入の参考にしてみてください。
※アーティスト名が赤文字になっているのは特にオススメの作品です。
クレジット
Joshua Redman (soprano & tenor saxophone)
Aaron Parks (piano, fender rhodes, juno, mellotron, wurlitzer, keyboards)
Matt Penman (bass)
Eric Harland (drums)
録音日: January 4-7, 2014
ジャズグループ、ジェイムス・ファームのセルフタイトル・アルバム『James Farm』に続く第2作。前作は〈00年代コンテンポラリー・ジャズのサウンドを上手にまとめた〉とまずは要約できそうな作品だった。あの作品のポリリズムや複雑なリズムパターンの対比、何よりもロマンティシズムをダークでシリアスなサウンドで包み込む手法は、カート・ローゼンウィンケルの『The Next Step』やブラッド・メルドーの『Largo』以降のジャズに広く認められる表現だった。
しかし2作目となる本作は、そうした00年代型のサウンドやプログレッシブなビートへの関心は希薄になり、同時代のインディーロックにも通じる素朴でオーガニックな曲が大半を占めている。リズムパターンの積み重ねから、コール・アンド・レスポンスを中心としたメロディックな方向へ軸足を移したことが原因だろう。
2010年前後ににローゼンウィンケルやメルドーらX世代を中心とする00年代の潮流が一段落し、アーロン・パークスやエリック・ハーランドをはじめとするミレニアム世代によって現代のジャズが新しいフェイズに入ったことは、彼らのフォロワーなら誰もが実感しているはずだ。この『City Folk』はやや地味な作品ではあるものの、ハーランドと同世代であるケンドリック・スコットの『Conviction』やデリック・ホッジの『Live Today』と同じく、〈10年代の気分〉を上手く反映させている。
クレジット
Zhenya Strigalev (alto saxophone)
Ambrose Akinmusire (trumpet)
Taylor Eigsti (piano)
Tim LeFebvre (electric bass)
Larry Grenadier (double bass)
Eric Harland (drums)
録音日: ?
昨今のNYの若手シーンでは、テナーサックス奏者が現在の中堅にあたるマーク・ターナーやクリス・ポッター、ジョシュア・レッドマンらのエッセンスを抽出し、上手くまとめたようなミュージシャンが多い。その一方で、アルトサックスはそういった前世代からの影響をにわかには感じさせない個性派がひしめいている。ウィル・ヴィンソンやローレン・スティルマン、ベン・ヴァン・ゲルダーなどがそれで、この作品のリーダーであるゼーニャ・ストリガレフもそのひとりだ。
メロディラインそのもののひねくれ具合は上にあげた同時代の若手アルト奏者よりも控えめだが、その代わりイントネーションの特異さ/多彩さは群を抜く。マウスピースを極端に浅く加えたアンブシュアによって繰り出される、独特のひしゃげたような脱力系フレージングは一度聴いておくべきだ。また、細かいパッセージでワビサビ系の演奏をするアンブローズ・アキンムシーレ、冷めたタッチでクールなモーダル系フレーズやゴツゴツとしたクローズドなヴォイシングを提供するテイラー・アイグスティ、クリス・デイヴ化の進行するエリック・ハーランドなど、サイドマンの活躍も見ものだ。
そんなストリガレフをはじめとする実力者と、アメリカ南部の田舎風景を想起させるような〈泥臭くブルージーな曲〉、変拍子やシュールなリフといった〈現代ジャズ的なアレンジ〉が上手く調合されたのがこの作品である。
クレジット
Vijay Iyer (piano)
Stephan Crump (bass)
Marcus Gilmore (drums)
録音日: June, 2014
現代のジャズピアノを聴いてみると60年代のビル・エヴァンス/スコット・ラファロ・トリオのようなピアニストとリズム隊による〈対話型トリオ〉は意外と少なく、トリオごとにそれぞれの方法論を構築しているように感じる。ブラッド・メルドー・トリオやフレッド・ハーシュ・トリオのようにピアニストがバンドの司令塔となり、一方でリズム隊は単純なキープではなくピアニストに合わせて大胆に様相を変える〈アメーバ型トリオ〉と、ヴィジェイ・アイヤー・トリオやファーマーズ・バイ・ネイチャー(クレイグ・テイボーンが所属)のようにピアニスト、ベーシスト、ドラマーがあえて過度な干渉を控え、同時進行的にフレーズを紡ぐ〈並列型トリオ〉が中でも代表的ではないだろうか。前者は対位法をはじめとするクラシックの語法が、後者はフリージャズの素養があることが共通点だ。
本作はヴィジェイ・アイヤー・トリオがACTレーベルで発表した2つのピアノ・トリオ作品『Historicity』、『Accelerando』にくらべ切迫感という点では劣ってしまうが、その一方で〈並列型トリオ〉的な手法がより前景化した作品だと感じた。“Hood”や”Mystery Woman”は三者が徹底的にリズムやフレーズを反復することによって、オーセンティックなピアノ・トリオにはないトリップ感が味わえる。これはピアノの残響を活かしたアプローチが増えたこととECM的な音響が組み合わさった結果といえる。
曲によってはECMレーベルを必要以上に意識しすぎたような大人しい演奏になっているし、セロニアス・モンクのカヴァーも曲のオリジナリティに引っ張られてしまった感があるが、現代ジャズを代表するピアノ・トリオのレーベルを新たにした再出発作品としてまずは聴いておくべきだろう。
クレジット
Donny McCaslin (tenor saxophone)
Jason Lindner (electric piano, piano, synthesizer)
Tim Lefebvre (electric bass)
Mark Guiliana (drums)
ゲスト
David Binney (producer, synthesizer, vocals)
Nate Wood (guitar)
Jana Dagdagan (voice)
Nina Geiger (vocals)
録音日: 2014年6月
マーク・ジュリアナやジェイソン・リンドナーらエレクトリック・ミュージック対応型の才人を迎えたダニー・マッキャスリンのニュープロジェクト第2弾。ビートミュージックやエレクトロニカ、EDMのテクスチャーを大々的に取り入れた前作『Casting For Gravity』は、それまでのマッキャスリン作品には見られないリズム隊との対話的インタープレイが新鮮な作品だった。一方で、〈ジャズと電子音楽のミックス〉というテーマが中心になり、即興やアレンジにおけるマッキャスリン節が抑えられていたことに物足りなさを感じたのも事実だった。
一方今回の『Fast Future』は前作に比べヴォイス/ヴォーカルを多用した曲が増え、プロデューサーでもあるデヴィッド・ビニーのシンセサイザー、マッキャスリンのテナーのオーバーダブも本格化し、よりハーモニー的な厚みが増している。その結果、電子音楽のテクスチャーはそのままに、前作よりも空間的かつ色彩豊かなサウンドを作ることに成功している。曲の基盤がしっかりしたことで、マッキャスリンの長尺フレーズの復活やジュリアナのドラミングにスリリングさが増したことも嬉しい。
現代ジャズを代表するミュージシャンたちの演奏が楽しめること、近年のポピュラーミュージックの成果を上手く取り入れていること、そして、それにもかかわらずハイコンテクストにならない間口の広さがあるという点で本作を薦めたい。
アンチコン所属のビートメイカー、バスのカヴァー(原曲はこちら)
クレジット
Chris Lightcap (bass, acoustic guitar, organ)
Tony Malaby (tenor saxophone)
Chris Cheek (tenor saxophone)
Craig Taborn (wurlitzer, electric piano, piano, organ)
Gerald Cleaver (drums, percussion)
録音日: December 16-17, 2013
レーベル: Clean Feed Records
リリース前に発表された音源やクリス・ライトキャップの過去作から、私は最初これをスタジオセッション的な作品だと考えていた。しかしフロントを務めるトニー・マラビー、クリス・チークは相変わらず個性的な節回しをしているものの、本作の最大の聴きどころはライトキャップの作曲/選曲と、それを様々な手段でグラデーションしていくクレイグ・テイボーンのキーボードワークである。
ライトキャップの曲は今どき珍しく、呪術性や祝祭性といった言葉で表現したくなるプリミティブなサウンドだ。コンテンポラリー・ジャズ的な複雑性はほとんど見られないが、それがむしろ聴き手のイマジネーションを強く刺激するサウンドを作り出している。またヴェルヴェット・アンダーグラウンドの”All Tomorrow's Parties”をはじめとするカヴァー曲も、ライトキャップのオリジナル曲と共振・共鳴するように演出されている。
一方でテイボーンは、2人のテナー奏者がサウンドに雑味やコクを加えていく後ろで、様々な鍵盤楽器を使い、不穏かつ神秘的な色彩を織りまぜていく。この作品を聴くまで私は楽器や演奏ジャンルによってあまりにも多くの顔を見せるテイボーンにとまどい、何らかのひとつのスタイルに収斂させていないことを彼の弱点とみなしていた。だがそれは間違いで、様々な性格のキーボード奏者が多重人格的・分裂的に同居していることが彼の本当の個性なのだ。個人的には、本作をテイボーンの代表作のひとつに数えても良いと考えている。