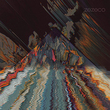これでもdownyはポップ・ミュージックをやっているという捉え方なんです
――歌詞に関してはいかがでしょう。作る前にある程度テーマを設けるのか、それとも言葉を紡いでいった先に〈あ、こういうことが言いたかったんだ〉と気付くのか。
「曲を作るときには、静止画のイメージがあるんですよ。例えば、月があって僕を照らしている、とか。そのイメージに従って曲も歌詞も構築していくので、ライヴでは映像を使って、頭の中にあったイメージを再現したいんです。downyにとって、ライヴで楽曲を演奏するというのは、描いた絵を展示会場へ持って行くような感覚なんですよね。ヴィジュアル・イメージをものすごく大切にしているから、歌詞の字面のために楽曲の構成を変えてしまうこともある。歌詞を縦書きにして、この行は余白があったほうが良いなと思ったら、そこに間奏パートを挿入するとか(笑)。まあ、聴き手にはなかなか伝わらないところではあるのですが」
――いや、めちゃくちゃおもしろいですよ(笑)。
「そうやって一枚絵を9枚仕上げたら、トータル・アートとしてのアルバムが完成するわけなんです」
――そういう歌詞の書き方は、詩人からの影響が強いんですか?
「もっとも影響を受けたのが石原吉郎で、他にも吉田一穂や萩原朔太郎が好きでした。ミュージシャンではeastern youthにものすごく影響を受けましたね。僕は6才まで香港に住んでいて、その頃はほとんど日本語を話せなかったんです。さらに日本に引っ越しても沖縄だったので、先生の言葉もウチナーグチ(沖縄方言)で。なので、周りからは〈お前ナマってるな〉と言われるわけですよ。それがすごく悔しくて、(日本語を)めっちゃ勉強したんです。その過程で詩人たちの言葉の使い方や、それを字面にするときのセンスにすごく感動して。小説とはまた別の興奮がありました」

――メロディーの作り方は、ここ数年で変わってきていますか?
「かなり変わってきましたね。もっとテクニックを使っていこうと思ったんです。ロック・バンドって、テクニカルになるのをダサイとする風潮があるんですけど、僕ももういい歳なので(笑)、そういう表現もやっていいんじゃないかなと。僕なりのソウルフルな歌い回しとか、前作ではまだ手探りなところもありましたが、今作はわりと上手くいった気がしますね」
――downyの歌がソウルフルというと意外に思う方もいるかもしれないですけど、例えばベス・ギボンズ(ポーティスヘッド)やエリザベス・フレイザー(コクトー・ツインズ)の歌にあるソウルと近いものを、青木さんの歌からは感じます。いわゆる通常のソウルのアプローチじゃないところとか。青木さんはどのような音楽を聴いて育ったのですか?
「とにかく母親が音楽好きで、家には何百枚とレコードがあったんですよ。当時は沖縄に住んでいたので車での移動が多かったんですが、車中ではいつも音楽が流れていましたね。ほんとジャンルレスに聴いていて、ドアーズやビートルズといったロックはもちろん、イエスやペンタグルなどのプログレ、ジャズ……もちろんソウルも大好きでした。ボビー・ウーマックやダニーハサウェイ、プリンスなどをよく聴いてましたね」
――それからクラブ・ミュージックに傾倒したのはなぜ?
「上京してきた頃、ライヴハウスへの興味がなくなっちゃった時期があって、それでクラブ通いをするようになったんです。2000年代前半ですね。恵比寿MILKや代官山AIR、渋谷のOrgan Bar、その界隈のDJとも仲が良かったし、いつもつるんでいました」
――そこでDJやトラックメーカーの道には進まず、バンドを続けていたのは?
「バンドでもクラブ・ミュージックを演奏できると思っていたんです。負けたくないという気持ちもあったし、それがdownyのモチヴェーションでもあった。いまでもサン・ラックスやスローイング・スノウ、ドルドラムスのようなエレクトロと生楽器の垣根を壊して自由にやっている人たちに惹かれます。ロング・アームの新作(2015年作『Kellion/The Stories Of A Youn』)を聴いても、やっぱりドラムは生なんですよ。ジェイムズ・ブレイクもライヴはバンド編成だったりするじゃないですか。そういうのを観ると、どれだけテクノロジーが進んでも、フィジカルな強さというのはやっぱり残るんじゃないかなって思いますね」
――ダンスミュージックを人力でやるというコンセプトだと、人間的なグルーヴを消すか、あるいはあえて残すかという方法があると思いますが、downyは後者なんですね。
「〈第三作品集〉では人間的な要素を取っ払う方向でレコーディングしたんですけど、〈第四作品集〉からはリズムのなまりを大切にするようになりました。ライヴでも、なだらかな昂揚感みたいなものを求めるようになっていて。今作もその方向性です。もちろんカチッとした曲もありますが、全体的には粘っこくうねっているアルバムだと思いますね」
――downyのAメロ~Bメロ~サビとはいかない楽曲構成は、ダンス・ミュージックからの影響ですか?
「それもありますけど、プログレからの影響が大きいと思います。ただ最近は、自分としてはかなりわかりやすくしているつもりなんですよ。これでもdownyはポップ・ミュージックをやっているという捉え方なんです。特に今回はライヴを踏まえての作品なので、ライヴを想定しているところもある。演奏している自分たちがいかに昂揚できるかというのはとても大事で、それがなくてダラダラと弛緩してしまうのは嫌だったんですよね。展開が多いのは、自分たちを緊張させる意味もありますし、ベタじゃない展開ができるのはメンバーの持つアイデアやスキルの賜物かと思います」
――downyのライヴでは、オーディエンスはどんなふうに楽しんでいるんですか?
「東京のお客さんは棒立ちで観ている人が多いですね。なんで、こんなにミサみたいになってるんだろう?と思います(笑)。変拍子なんて1拍目だけ合わせて、好きに踊れば良いんですよ。外国人のお客さんやミュージシャンは普通に踊ってますし、地方のライヴのほうが、みんな踊ってますね」
――いわゆるEDM的な、ブレイクがあってドロップ(サビ)があって……という構成とは違うわけですよね。とはいえガチのプログレだと踊りにくいし、めざしているのは〈踊れるプログレ〉といったところでしょうか。とにかく音に合わせて身体を動かしてみれば、また違った聴こえ方がしてくるかもしれないですよね。
「そうそう、そうなんですよ。自分でも、変拍子や難解なリズムを作ろうとは思ってない。出来たトラックがたまたまそうなっているだけなんです。歌については、4拍子で取っている曲もあるし、歌いながらギターを弾くときは、手だけ別の拍子動いていますね(笑)」
設けた制約を取り払っても〈downyらしさ〉は何も変わらない
――先ほど過程を話してくれたプリプロが終わったあとのレコーディングは、メンバー揃ってから一発録りで行っているんですか?
「いえ、ドラムから順番に録っていきます。レコーディング中はメンバー全員がスタジオに揃わないこともあります。それはもう単純にスケジュールが合わないからなんですが、お互いのプレイに関しては全幅の信頼を置いているし、前作からはずっとそういうやり方ですね」
――それが可能だからこそ、ロビンさんは沖縄で暮らしながらバンド活動を続けられる。
「そうなんです。良い時代ですよね(笑)」
――前作以降、シンセサイザーを積極的に導入しているのも特徴の一つになっていますね。
「そうですね。最近は鍵盤ばかり弾いているし、むしろギター/ヴォーカルでずっとやっていたことのほうが不思議なんです。結成した時からdownyは〈シンセを使わない〉〈ドラムは4点(キック、スネア、タム2つ)のみ〉〈ベースはエフェクターを踏まない〉というルールを作って、そのなかでどこまでできるか?にこだわってきたバンドだったんです。エレクトロニクスがものすごい勢いで浸透していき、音楽制作の自由度がどんどん上がっていった時代に、僕らはあえて制約を設けて、〈シンバルを刻まなくても細かいグルーヴを表現できる〉〈ディストーションを踏まなくてもエモーショナルにバーストできる〉〈ヴォーカルが絶叫しなくても聴き手を圧倒させられる〉ということを突き詰めていった。ただ、そういう制約のいくつかを、前作の〈第五作品集〉では取り払ってみたんです」
――制約を設けることによって、ある意味ではdownyらしさを守り続けてきたと思うんですけど、前作でその制約を取り払ったことで、逆に〈downyとは何か?〉という問いかけに繋がったのでは?
「そうなんです。そして、結果的には何も変わらなかった。シンバルを刻んでも、ディストーションを踏んでも、シンセを使っても、そこに僕たちなりの好みというか美学があるから、バンドとしての方向性はブレないんです。だったら、良いと思ったものはこれからどんどん採り入れていったらいいんじゃないかって」
――それは大発見ですよね? もう何をやってもdownyになるという自信にも繋がりますし。
「ホントにそうなんですよ。なぜ、いままでそうしてこなかったんだろう(笑)。でも、制約のなかでずっと作り続けてきたからこそ、音楽性が研ぎ澄まされていったし、僕らだけの美学を持ち得たとも言えますしね」
――何をやってもdownyらしくなることが証明されたわけですから、次の展開もまた楽しみですね。
「そうですね。ガチガチのハードコアをやっても、きっとdownyらしくなるでしょうし(笑)。メンバーそれぞれの引き出しはたくさんあるので、それを開放したいです」