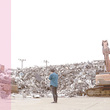エリオット・スミス『Figure 8』の壁を観に行ったら〈悲しい男ね〉と言われた
――負け犬の話をふまえると、今回のアルバムにはブルースのフィーリングも感じました。
「だと嬉しいです。ここ1、2年くらい、戦前ブルースやデルタ・ブルースにハマって、ずっと聴いていたんです。ブルースに関しては、曲の良さとかじゃなく、全体に漂う不穏な感じとか、感覚的に引き込まれる部分が多いんですよね」
――ブルースを演奏するというより、ブルースの空気感が大切なんですね。
「別にブルースのフレーズを弾かなくても、そういうムードが出ればいい。アレックス・チルトンの『Cliches』というアルバムが大好きで、ジャズのスタンダードとかをカヴァーした作品なんですけど、すごくブルースのフィーリングを感じるんです。そういうムードが今回のアルバムに出ればいいなと思って」
――なるほど。そういう面も含めて、今回のアルバムにはアメリカっぽい雰囲気が漂っていますね。
「あんまり国を意識はしないんですけど、スティール・ギターが入っていたり、もともと土臭いグルーヴが好きだったりするので、そういう部分はアメリカ感があるのかもしれないですね。あと、アルバムを作る前にアメリカに行ったんですよ。エリオット・スミス『Figure 8』の(ジャケットに写っている)壁を見に行きたくて。そこで、メンフィスやサンフランシスコ、ニューオーリンズなどいろいろ見て回ったんです。その頃、仕事を辞めることになったこともあり、この際死ぬ前に行っとかなきゃいけない場所に行っておこうと思ったんですよね」

――ロックの聖地巡りですね! 行きたい場所を考えたらアメリカが多かった?
「そうですね。そういう意味ではアメリカの音楽が好きなのかもしれない」
――『Figure 8』の壁、どうでした?
「もう最高でしたよ! その近くまでは車で友人と一緒に回っていて、壁の近くで降ろしてもらって1人になったんです。最初は場所がわかんなかったので、現地の人と仲良くなって、壁まで連れてってもらったんですよ。その案内してくれた人も音楽好きで、いろいろな話をしながら壁まで行ったんですけど、そこはちょっとした観光地みたいになっていて、人が集まっていました。そこで出会った人に〈この壁を見るために日本から来たんだ〉と話したら〈とても悲しい男ね〉って言われて(笑)」
――悲しい男(笑)。
「こっちは超テンションが上がっていて、悲しいとか切ないとか全然思ってないんですけど、そんなふうに見えるんだと思って。でも、エリオット・スミスのことを知っていないと言えない発言だから、〈そういうことを言ってくれる人がいるなんて最高だな〉と思いました」

――エリオット・スミスが、どういう土地で音楽を作っていたかというのを実感できるのも大きいですよね。
「すごく大きいです。壁がある辺りは、サンセット・ブールヴァードという大通りがあって、シルヴァーレイクやエコパークとか、いわゆるインディー的なコミュニティーが多い場所。60年代だったらラヴのメンバーが住んでいたような場所なんです。わりと平和的でヒップな空気が流れているんですけど、ちょっとやさぐれた部分もあって。そういう雰囲気を実感できたことで、それまで自分が聴いてきたエリオット・スミスの音楽が凄く腑に落ちた」
――なるほど。〈土地に行って腑に落ちる〉感じと、〈住んでいる環境が曲に反映される〉というのは通じている気がします。
「やっぱり、(環境からの影響は)勝手に曲に反映されるものなんですよ。だから、好きなアーティストが住んでいた街に行くと腑に落ちる。今回メンフィスに行ったのは、ブルースが好きだからというのもあるんですけど、いちばんの理由はビッグ・スターの“Dream Loverという曲の歌詞にビール・ストリート(Beale Street)が出てきて、そこに行ってみたかったんです」
――行ってみてどうでした?
「ビール・ストリート自体は意外としょぼかったんですけど、そこからちょっと離れると、一気に不穏な空気になるような町で。そういう、ある意味ではブルージーな面もありつつ、だからこそロックやブルースが持つエネルギーで活気づいていることがわかって、純粋におもしろかったですね」
――そういう話を聞くと榊原さんがソロで作った音楽も聴いてみたくなりますね。『Cliches』みたいな弾き語りのスタイルで。
「やります(笑)」
――えっ!? 出すんですか。
「日本語でやろうかなと考えています。もともと、カセットテープ1本ごとに宅録してて、ライヴ会場やそのへんで売ろうかなと思っていたんですよ。ダニエル・ジョンストンみたいに(笑)。でも、KiliKiliVillaが出してくれるみたいで」
――それは楽しみですね。それを出すためには新作を売らないと(笑)。では、最後に今回の『formulas and libra』というタイトルについて教えてください。
「今回のアルバムはロックンロール・アルバムだと思っています。でも、最初に言ったようにロックンロールは定義が難しいんですよね。〈グッとくる〉ってどういうことか説明するのは。それは曲のムードが変わっても、曲調が変わっても根底にあるものなので、〈形式(formula)〉としか言いようがない。それでタイトルに〈formula〉と入れたんです。そして、〈libra〉というのはバランスをとる〈天秤〉という意味で、今回のアルバムはバラバラな曲調のなかでJAPPERSとしてのバランスがとれているというか、1本の芯が通っているのを感じてもらえればと、この言葉を入れました。あと、いま自分が好きな女の子が天秤座なんですよ(笑)。天秤座の女の子といえば、自分にとっては(ビッグ・スターの)“September Gurls”だし、(アレックス・チルトンの)『Cliches』の〈Cliche〉は〈決まり文句〉という意味で、それって〈formula〉に通じていて……」
――最後は強引にアレックス・チルトンに寄せてきましたね(笑)。
「気づいたらアレックス・チルトンの話をよくしているんで、今回の新作に関してもアレックス・チルトンは重要な存在なんだと思います。あと、バンドというより個人的な話なんですけど、前のアルバムまでは人が存在していなかったんです。すごく自分の内にこもった作品だった。でも、今回は人がいるんです」
――前作は個人的な作品だったけど、新作は第三者の存在や外部を意識しているということ?
「そうですね。自分の内にこもった感じをバンドで表現していた時期を脱したというか。前のアルバムは夢みたいな感じだったんですよ。そこから、気持ちも音も外向きになって、より現実味が増したというか。 今回、“One Plus One”という曲が入っているんですが、あとから考えたら象徴的なタイトルだと思った。今回は1人に1人が加わった感じのアルバムなんです」