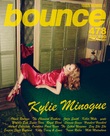「グッド・タイム」は音で始まる映画だ。チリチリとしたノイズ、這うような低音、そこに被せられる人声を模したようなシンセのループ。観る者の不安感を呼び起こすような不穏な音響が画面を満たしていく。それはプロローグにあたる心療内科のセッションの場面でいったん鳴り止むが、タイトル・バックとともに別のシンセ・ループを引き連れて復活する。そして唐突に銀行強盗のシーンへと突入したかと思えば、テンポを上げて緊迫感のあるメロディーが流れ出す。そのオープニング10分を目撃するだけで、「グッド・タイム」が音楽とともに動いていく映画だと観客は理解するだろう。
その「グッド・タイム」の音楽を全編にわたって担当したのは、現在多彩な活躍を見せるエレクトロニック・ミュージックのプロデューサー、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下OPN)だ。そして、11月3日の「グッド・タイム」日本公開に合わせて、ディレクターズ・カット版のサウンドトラック『Good Time... Raw』が発売される。これは8月に発表されたサウンドトラックとは異なり、楽曲が映画で使用される曲順に編集されたものとなっている。つまり、映画のストーリーそのものに沿うものだ。映画の世界観とダイレクトにシンクロするヴァージョンである『Good Time... Raw』をより深く味わうためにも、このコラムでは映画「グッド・タイム」の主題とOPNが手がけた音楽の関連性を探っていきたい。
「グッド・タイム」を監督したジョシュ&ベニー・サフディ兄弟はともに80年代半ば生まれの気鋭で、注目を集めたのは前作の「神様なんかくそくらえ」(2014年)だ。そこではNYの路上で生活するストリート・キッズたちの荒れた日常が生々しく映されており、21世紀のアメリカ都市が生み出し続ける〈ゴミ〉としての子どもたちが叫び声を上げていた。社会から滑落した人間たち、誰もが見て見ぬふりをする者たちの生がそこには存在したのだ。すぐに連想されるのはラリー・クラーク監督、ハーモニー・コリン脚本の「KIDS/キッズ」(95年)だが、しかし、ストリート・キッズたちの日常を瑞々しく映していた同作に比べると、「神様なんかくそくらえ」のキッズたちはもっと追いつめられているように見える。執拗なまでにクローズアップが多用され、切迫感が終始強調されているからだ。「KIDS/キッズ」では悲惨さのなかにも叙情的な空気が少なからず漂っていたように思うが、90年代はストリート・カルチャーの隆盛もあって〈路上〉にまだ夢を見られたということなのかもしれない。それから20年の時を経て、「神様なんかくそくらえ」においてファストフード店のトイレで麻薬を打つ子どもたちは、社会的にも文化的にもアメリカから廃棄される存在になってしまった。サフディ兄弟は、そして、そんな彼らのズタボロの恋こそを活写したのだ。
「神様なんかくそくらえ」が新しかったのは、そのドキュメンタリー的手法(近年の映画の演出において重要な手法のひとつだ)には普通、そぐわないように思える音楽が使われていたことである。そこでは、冨田勲がドビュッシーのピアノ曲をシンセサイザーで演奏した『月の光』(74年)からの楽曲が、映画の印象的なシーンで使用されている。ストリート・キッズのクローズアップに被せられるシンセのドリーミーなメロディー……これほどまでに息がつまりそうな“雪は踊っている”は聴いたことがなかった。他に劇中使用されたタンジェリン・ドリームやアリエル・ピンクの楽曲も含め、キッズたちの日々の息苦しさと音楽がこれ以上ないほど呼応していた。
以上のように、サフディ兄弟の映画にとって音楽はその独自性を発揮するための重要な要素となっている。そこで「グッド・タイム」の音楽担当に選ばれたのがOPNだ。OPNことダニエル・ロパティンはソフィア・コッポラ監督の「ブリングリング」(2013年)のスコアを担当したことも話題になったが、それは数曲のことであったし、音楽的にも「グッド・タイム」のサウンドトラックとの強い関連性は見出しにくい。よって今回の「グッド・タイム」は彼の映画音楽の仕事の発展形というよりも、サフディ兄弟の映画においてシンセサイザー音楽をどのように活かすかという課題を推し進めたものであるだろう。すなわち、「神様なんかくそくらえ」における冨田勲の役割がここではOPNに与えられているのだ。
一方でOPNのサイドから音楽面で「グッド・タイム」のサウンドトラックを捉えてみると、とりわけOPNとしての前作『Garden Of Delete』(2015年)からの連続性が強いことが窺える。本作のプログレッシヴ・ロックを思わせるシンセの派手なメロディーやメタルからの影響などは『Garden Of Delete』によく見られた傾向だ。どこか80年代初頭のシンセ・ポップ感覚、あるいはそれらの楽曲が使われたジャンル映画やB級映画のサウンドトラックを思わせるところもある。その前作『R Plus Seven』(2013年)の美しい静けさと比べるとわかりやすいが(あるいは「ブリングリング」に提供した楽曲のアンビエンスと比較してもいい)、『Garden Of Delete』と『Good Time... Raw』はより俗っぽさを纏いながらダイナミックな躍動感が漲っている。とりわけ今回のサウンドトラックでは、作品を通して気を抜ける瞬間はほとんどない。
そうした意味で「グッド・タイム」はサフディ兄弟にとってもOPNにとってもそれぞれ真っ当な次の一手を示したコラボレーションだと言えるが、しかしながら、さらに重要なのは音楽と映像、物語や演出も含めた総体としての映画作品「グッド・タイム」において、両者のテーマがこれ以上ないほど合致しているということである。
「グッド・タイム」はNYを舞台にした犯罪映画だ。アメリカの都市でもっとも貧しい層として生きるコニー(ロバート・パティンソン)とニック(ベニー・サフディ)の兄弟による強盗と、そこからの逃亡劇を追っていく。ほぼ一日だけの出来事を描いており、リアルタイム・ドキュメンタリー風のタッチで進行する。
ポイントは、現代の格差社会の下層で生きる人物が主人公になっていることだろう。経済的に追いつめられた人々、すなわち現代における〈下〉の人間による現金強盗はザック・ブラフ監督「ジーサンズ はじめての強盗」(2017年)やスティーヴン・ソダーバーグ監督「ローガン・ラッキー」(2017年)のようなエンターテインメント作品も題材にしているのである意味旬だと言えるかもしれないし、リアルタイム感のあるアクション映画やスリラー映画は近年非常に流行している。だが、「グッド・タイム」がそれらとまったく違っているのは、〈下〉で生きる人間たちの犯罪をまったく痛快なものにしていないことだ。コニーは兄として知的障害を持つ弟ニックのために行動しているつもりかもしれないが、基本的に自分本位で場当たり的にしか行動しないため、逃亡の過程で度々窮地に陥ってしまう。愚行に次ぐ愚行。時折ユーモラスな場面が現れはするが、それが根本的な救いになることはない。映画は予想外の方向へとスリリングに次々と展開していくが、主人公の機転でピンチを乗り越えるような〈映画らしい〉爽快さはやってこない。
だが、それもまた映画であるとサフディ兄弟は宣言する。NYを舞台とし、そこで生きる人物をリアルなタッチで撮影しているという点で、サフディ兄弟の作品をジョン・カサヴェテスの映画と比較する向きもあるが、なるほど大いに頷けるものだ。だがそれに加えて、貧しさと人間の愚かさから目を逸らさないという意味では、自分にはダルデンヌ兄弟の映画(たとえば「ある子供」(2005年)のような)をインターネット世代の手によってアップデートしたものに思える。サフディ兄弟の作品では社会から〈ゴミ〉と見なされ、地面に這いつくばって生きる者たちの姿が克明に映し出されている。「グッド・タイム」では〈下〉で生きる者たちのリアルな窮状が、新しい感性のもと、犯罪ものというジャンル映画の形で表現されているのである。
このようなサフディ兄弟の主題はどこかでOPNの作風と重なっているのだろう。80年代のCMの音を拾い集めてループしエディットした『Replica』(2011年)、あるいはヴァーチャル空間の閉塞感を見事に視覚化したフォード&ロパティン『Channel Pressure』(2011年)のアートワーク、そして『Garden Of Delete』のB級感覚やグロテスクなモチーフ(“Sticky Drama”のミュージック・ビデオを観てみよう)。OPNは、そのような価値のないもの、だらしないもの、汚いもの……をどうも気にせずにはいられないようだ。そして、それらを美化することなく、しかし実験を重ねながら奇妙な姿の音楽にしてみせる。〈ゴミ〉がアートと、ポップと繋ぎとめられる。そこで〈ゴミ〉が突然輝き出すことはないが、しかしもう〈ゴミ〉とは呼べない何かになっている……。
「グッド・タイム」のコニーは立派な人間ではないが、しかしOPNの音楽をエンジンとして確かに映画の主人公となっている。良いとか悪いとかではない。多くの人間が無視しようとする存在こそがスクリーンで躍動し、観客はそれを見つめずにはいられない。追いつめられていくコニーを煽るように、不安を醸すシンセのメロディーが畳みかけられていく。〈音楽が映画の登場人物のひとりである〉というのはよくある言い回しだが、しかし「グッド・タイム」において、それは切実なものなのである。OPNの音楽がなかったとしたら、映画は硬直してしまっていただろう。
だから、映画を観てから『Good Time... Raw』を聴けば、もう一度物語のダイナミズムを体感することができる。先のサウンドトラックがアルバム作品として聴きやすいようにエディットされていたのに比べ、『Good Time... Raw』は映画の展開そのままなので起伏に富んでおり、また以前収録されなかったトラックもあるためストーリーをよりヴィヴィッドに感じられるものとなっているからだ。
序盤から“Banco Popular”~“Bail Bonds”にかけて逃亡劇の焦燥感に拍車をかけ、中盤の偶然入った家で休息を取るシークエンスではダーク・アンビエント的な音響が聴ける。後半では再び神経症的な圧迫感を前面に出し(“Cops Show Up / Acid Dose”の過剰な密度の音の応酬がハイライト)、終盤、フィルム・エディット版となった“Connie”では重々しい低音や金属的なノイズ音に美しいシンセの和音が被さっていく。〈Raw〉の名の通り、ディレクターズ・カット版ではコニーとニックの息遣いがより生々しく想起される。サフディ兄弟が観客に対峙させようとする実存がそのまま、OPNによるダイナミックな音楽にこめられているように聞こえてくる。
そして、“Connie”の陶酔的な余韻を引き継いで、クロージングの役割を果たすのがイギー・ポップを迎えた“The Pure And The Damned”だ。ピアノ・バラッドに重なるシンセの柔らかい音色。ニックの澄んだ瞳に宿る切なさ。そこでようやく映画を覆っていた切迫感の代わりに叙情性が立ち上がる。イギー・ポップが歌っているように、これが〈愛〉の映画だったことを観る者はそこで思い知るのだ。立派でも美しくもない、あまりにも愚かな愛。そこではいまにも廃棄されそうなものが、どうにかして音を立てているようだ。
映画「グッド・タイム」
監督: ジョシュ&ベニー・サフディ
脚本: ジョシュ・サフディ、ロナルド・ブロンスタイン
撮影: ショーン・プライス・ウィリアムズ
音楽: ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー
出演: ロバート・パティンソン、ベニー・サフディ、バディ・デュレス、タリア・ウェブスター、バーカッド・アブディ
2017年11月3日(金・祝日)から東京・シネマート新宿ほか全国ロードショー
http://www.finefilms.co.jp/goodtime/