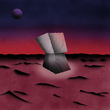痩せっぽちの男が、赤い頭髪を揺らしながらギターを掻き鳴らし、一度聴いたら忘れられない嗄れ声で歌っている。ビスケットの街について、半魚人について、痛みについて、不眠症について……。その声とザラついた不穏なサウンドは、まるでB級ホラー映画のVHSから聞こえくるかのようだ。
ファースト・アルバム『6 Feet Beneath The Moon』でリスナーに大きな衝撃を与えたキング・クルール(King Krule)が、新作『The Ooz』を携えて実に4年ぶりに戻ってきた。しかも、サウンドの深みと複雑さは前作の比ではない。ダークなトーンや独特の世界観はそのままに、音楽家として一気に跳躍した印象だ。現に、海外のメディアでは、ほぼ絶賛一色で、今年のアルバム・オブ・ザ・イヤーの1枚として『The Ooz』が挙げられることは確実だろう。
しかし……疑問は残る。この男は一体、何者なのだろう? 聴き手の孤独感に寄り添うようで、同時に突き放すような、この異様な音楽はどこから来るのだろう? そんな素朴な疑問を、インディー・ミュージックに独自の視点から切り込んでいる天井潤之介と小熊俊哉という2人の音楽ライターにぶつけてみた。以下は、その対話の記録である。謎めいたキング・クルールの実像に近づけたのか、あるいは遠ざかったのかは、その目で確かめてほしい。

『The Ooz』は2017年版〈In Utero〉?
――まずは最新作『The Ooz』についてお訊きしたいのですが、このアルバムを聴いてお二方はどう感じました?
天井潤之介「すごく陳腐な喩えだけど、ファースト・アルバム『6 Feet Beneath The Moon』が(ニルヴァーナの)『Nevermind』なら『The Ooz』は『In Utero』じゃないですか。曲毎に音質もバラバラで雑然としているし、ロウ・キーで、すごくコアなものを作ってきた。ただ、これがどういう文脈で評価されるのかは謎なところが多くて。カッコいいけど、噛み砕きにくいアルバムだなと思いましたね」
小熊俊哉「でも、コアな作風に徹したことで、彼の場合は逆にわかりやすくなった気がしますね。実際、グランジっぽいザラついた音は本人も意識していたらしいですよ。ファーストはもっと整頓されていてトラックっぽい作りだったけど、今回はディストーションを効かせたり、生々しい音になっている。演奏もジャズ・バンドっぽい曲が多くて、特にサックスの音色が強烈ですよね。奏者のイグナシオ・サルヴァドレス(Ignacio Salvadores)はアルゼンチン出身で、彼はキング・クルールに自分のライヴ動画を送り付けたそうなんですよ。そこから共演に至ったらしくて」
――Facebook経由で繋がったらしいですね。SNS世代らしい身軽さです。
小熊「イグナシオの名前を検索しても、何にも出てこないんですよ。よく会いに行ったなと(笑)。あと、『The Ooz』はメロディアスな曲が以前よりグッと良くなっている。個人的に好きなのは“Czech One”や“Slush Puppy”のようなドリーミーな曲です」
天井「“Lonely Blue”もまさにそういう曲ですね。とてもムーディーで、チェット・ベイカーへの敬愛がありありと感じられるというか」
小熊「Spinのインタヴューによると、今になってビートルズを初めてしっかり聴いたらしいです。彼はスタイリッシュで尖った音楽が好きじゃないですか。ポストパンクやジャズ、ヒップホップは渋いところまで掘りまくっているけど、ビートルズみたいにベタなところは通ってこなかったのは、ポスト・インターネット世代っぽくて納得というか(笑)。もちろん直接的にビートリーになったわけではなくて、郷愁を誘うメロディーやコードには、ボサノヴァやレゲエ、南米音楽からの影響も感じます。歌も以前より広い音域が出るようになっているんじゃないかな」
天井「歌への自信が増したのもあるんでしょうね。歌い回しに極端に表情をつけるようなところは少なくなったし、ファーストと比べるとストレートに歌っている場面が増えた印象を受けます」
小熊「このご時世に19曲も入ったアルバムを作るのもいい度胸していると思います(笑)。それも、ドレイクの『More Life』みたいなプレイリスト的発想ではなくて、オーセンティックな作りのコンセプト・アルバムになっている。最近はみんなもっと戦略を練ったりするものだけど、このアルバムはとにかく自分の内面を提示することしか考えていない。そこも痛快ですよね」
――今作はディリップ・ハリス(Dilip Harris)が共同プロデューサーとしてクレジットされています。
天井「マウント・キンビーやミカチューの作品にもエンジニアとして携わっている人ですよね」
小熊「キング・クルールも参加したマウント・キンビーの新作『Love What Survives』は、『The Ooz』と通じ合うものがありますよね。制作スタッフも被っているし、両者の新作を比べると見えてくる部分もあると思います」
――具体的に言うと?
小熊「例えば、最近出演したBeats 1 Radioでエチオピアン・ジャズの第一人者であるムラトゥ・アスタトゥケの“Tezeta(Nostalgia)”をかけているんですよ。この曲は『The Ooz』にかなり影響を与えていると思います。その一方で、マウント・キンビーは再評価が進んでいるカメルーンの電子音楽家、フランシス・ベベイの“Sanza Tristesse”も選んでいて、こちらはミカチューが歌っている“Marilyn”の元ネタっぽい。きっと両者の間で、〈やっぱり今はアフリカだよね〉みたいなリテラシーが共有されているんじゃないですかね。いろんな音源をシェアしながら、二人三脚でサウンドをアップデートさせてきたというか」
天井「Spinのインタヴューではルイス・アルベルト・スピネッタの名前も挙げていましたね。そういった感覚はアート・リンゼイにも近いのかな。アート・リンゼイはまさに、ジャズやポスト・パンクとボサノヴァやラテン音楽を横断するようなキャリアのアーティストであるわけだし」
小熊「確かにそうですね! キング・クルールは2013年のSpotifyのプレイリストでもリンゼイの“Illuminated”を挙げていますし、越境的なセンスは通じる部分があると思います。リンゼイのこの曲は実にキング・クルールっぽいですね。2002年の発表というのが信じられないくらい」
キング・クルールはなぜアメリカで愛される?
――キング・クルールの音楽はPitchforkを始め、特にアメリカのメディアでの評価が高いと感じます。それはどうしてなのでしょう?
天井「簡単に言ってしまえば、オーセンティックな素養を備えた玄人好みなところと、それでいてモダンな志向も感じさせるバランス感覚。そこのセンスの良さじゃないですかね。音楽的な背景はわかりやすい。ジャズやブルース、フォークなどのスタンダードでクラシカルな音楽がベースにありながら、パンクやポストパンク的な感性を持っている。キング・クルールを聴いて真っ先に思い浮かべたのがダーティ・ビーチズ。それとジェイムズ・フェラーロ辺りの〈ヒプナゴジック・ポップ(hypnagogic pop)〉と呼ばれたようなサウンド。キング・クルールは、そういった北米のアンダーグラウンドなアーティストの、スモーキーでダブっぽいプロダクションをシェアしているようなところがありますね」
小熊「ダーティ・ビーチズに通じているのは、どういうところですか?」
天井「50年代のロックンロールやジャズといったアメリカ音楽に対する並々ならぬ愛情を感じさせるところですね。ダーティー・ビーチズのアレックス・ジャン・ハンタイ(Alex Zhang Hungtai)もチェット・ベイカーの歌なら何でも好きっていうような人だし。それと、〈暗さ〉。洞穴の中で歌っているような(笑)」
――キング・クルールの音楽にはヒップホップの要素も強くあります。ファーストのアートワークにもヒップホップ・マナーを感じる。そういったアメリカへの憧れやアメリカ文化との関連性についてはどう思いますか?
小熊「そこがイギリス人っぽいとも言えるかもしれない。古き良きアメリカへの憧れがある一方で、同時代のイギリスの音楽とも繋がっていて、さらにヒップホップも通過している。そこが新しかった。そういえば、以前、天井さんはThe Sign Magazineのレヴューでベックを引き合いに出していましたよね」
天井「ええ。ベックの場合はブルース寄りですが、やはりルーツにそういったアメリカの古い音楽がある。それと同時に、ジョー・ミークやレイモンド・スコット、カールハインツ・シュトックハウゼンのような電子音楽に影響を受けている。キング・クルールの場合は、さっき言ったような北米のアンダーグラウンドな音楽とプロダクションの嗜好を共有している。ベックとキング・クルールはそういった構造が似ています」
小熊「顔も似ていますしね(笑)。キング・クルールがアメリカでも評価されるのはやっぱり〈暗さ〉に尽きるんでしょう。最近のロックでここまで暗い人はいなかったし、『The Ooz』の日本盤オビに〈孤高〉と書いてあるのも大袈裟ではないというか」
天井「歌詞の文学性とセットでそういった評価がされているのでしょうね。海外のレヴューでは、ほぼ歌詞抜きには評価されていない。歌詞についてが8割を占めるレヴューもあります。ほとんど楽曲はラヴソングと言っていいと思いますが。それと、これは後で触れるアルバムのテーマとも関係しますが、彼の歌にある血生臭さだったり猟奇的な側面は、アメリカン・トラッドから派生した〈マーダー・バラッド(murder ballad)〉に通じるところがあると思います。もちろん、キング・クルールは実在した殺人事件を歌っているわけではないですが、“Vidual”のサスペンスに満ちた描写なんかはそう強く感じさせますね」
――文学といえば、キング・クルールはチャールズ・ブコウスキーが好きだということでも有名ですね。一方、〈暗さ〉については、現在のアメリカのラップ・ミュージックは鬱を題材にした曲が多いと小林雅明さんがおっしゃっていました。アッパーなEDMやポップスがある一方で、いわゆるラップ・ミュージックは暗くダウナーな方向へ行っている。キング・クルールも、そういった最近のラップに近い感触はあると思います。
小熊「なるほど。言われてみれば、XXXテンタシオン(XXXTentacion)やリル・ウージー・ヴァート(Lil Uzi Vert)に代表されるような、今のアメリカの病んだ感じにもマッチしているのかもしれない。アメリカもイギリスも〈暗さ〉を抱えている状況にキング・クルールの音楽がシンクロしているのだとすれば、それは高く評価されるのも当たり前ですよね(笑)」
――また、これはele-kingの野田努さんがデビューEP『King Krule』のレヴューで書かれていたことですが、2011年8月にロンドンを中心とした若者による暴動があり、EPのリリースはその数ヶ月後です。その後、2016年にはブレグジットがあり、翌年に『The Ooz』がリリースされている。ソーシャルな状況とどこかで呼応しているように思えますね。
小熊「本人は〈(自分が書く曲は)ほぼフィクションではない。ロンドンは自分が住んでいる場所だから、それが自然と自分の音楽のなかに出て来ているとは思う。でも、自分の歌詞で何か政治的なメッセージを伝えようと意識しているわけではない〉と話していましたね。今回の『The Ooz』も直接的に社会的なことを歌ったアルバムではないけど、救いのないフィーリングが歌詞やサウンドに充満している。言い換えれば、〈パーソナルであることが政治的である〉というか。日常と政治性は否応なしにリンクせざるをえない。結果的に、ストレートな表現よりもリアリティーを感じます」
天井「僕は音楽の政治的な面ってそこまで興味がないのですが、小熊さんがおっしゃっていることはわかります。彼が歌う救いのないフィーリングには、どの時代に置かれてもハマるようなリアリティーがありますよね。だから、キング・クルールの音楽は良い意味でトゥー・マッチなんでしょう」