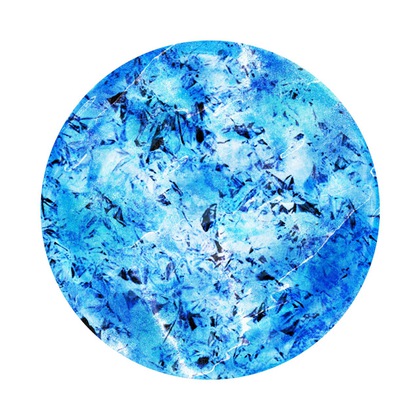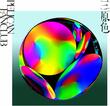初のフル・アルバム『Home Electronics』のリリースに加えて、パノラマパナマタウンとAge Factoryとのツアー〈GREAT TRIANGLE TOUR〉の実施、さらに東京・幡ヶ谷forestlimitでのフロアライヴ企画〈DREAM DAZE〉の開催&同ライヴに合わせた新曲“SF Fiction”“Shadow Play”の配信リリースなど、2017年は意欲的な活動が目を引いたPELICAN FANCLUB(以下、PFC)。その挑戦心は2018年も鎮まることはないようだ。
1月19日(金)より3都市でのワンマン・ツアー〈SPACE OPERA〉をスタート。大阪CONPASSでは『ANALOG』、愛知CLUB ROCK’N ROLLでは『PELICAN FANCLUB』(共に2015年)、そして東京GARAGEでは『OK BALLADE』(2016年)と各公演ごとに過去のミニ・アルバム3作の再現ライヴを行い、さらに現在進行系のセットも加えた二部構成が予定されている。そして2月4日(日)、東京Mt.RAINIER HALL PLEASURE PLEASUREでのツアー・ファイナルは、バンド初となるホール公演。同公演は〈FUTURE〉と銘打たれており、これまでになかった試みとして、大人数編成でのパフォーマンスが披露される。文字通り、PFCの未来像が垣間見えるライヴになるのではないだろうか。
今回、Mikikiでは過去作と向き合い、その先に〈FUTURE〉を見据えることを選んだPFCにインタヴュー。エンドウアンリ(ヴォーカル/ギター)とカミヤマリョウタツ(ベース)の2人に、各タイトルをリリースした当時の状況を振り返ってもらった。作品ごとの音楽的な背景のみならず、その頃に彼らが抱いていた想いや悩みまで、率直に明かしてくれている。
――このインタヴューでは、ミニ・アルバムごとに当時の状況を振り返ってもらいますが、まずは再現ライヴを据えたツアーを実施しようと思った経緯から教えてください。
エンドウアンリ「ミニ・アルバム3枚を出したあと、PFCというものは何なのか――それがわからずに迷走していた時期があって。だけど、フル・アルバム『Home Electronics』を完成させたことで、〈PFCはこういうバンドなんだ〉とメンバーの4人全員が確信できたんです。『Home Electronics』という作品がPFCの名刺、ベーシックになったうえで、いまの自分たちが過去のミニ・アルバム3作を演奏したらどうなるんだろう?と考えた。現在のPFCによる過去のPFC研究というか、そういう感覚でやってみたくなったんです」
CDショップに自分たちの作品を置かれていることが不気味だった
――では、最初はファースト・ミニ・アルバム『ANALOG』(2015年1月)について。そもそも初期のPFCはどんなバンドに影響を受けてきたんですか?
エンドウ「もう僕は確実にコクトー・ツインズですね。それ以外だと、当時はディアハンターにも心酔していました。あと、その頃のスタイルで思い出すのは、ライヴの日には絶対にソニック・ユースの『Washing Machine』(95年)のシャツを着て演奏していたこと。(ソニック・ユースの)サーストン・ムーアに憧れていて、彼をめざしていたんです」
カミヤマリョウタツ「日本のバンドであげるとすれば、その時期の僕たちとしてはスピッツかなと思います。海外だとドラムスも大きいんじゃないかな。引き算のアンサンブルが良いなとなっていた時期でもあって、そのうえでドラムスを参考にドンドン音を引いていった(笑)」
エンドウ「ドラムスはセカンド『Portamento』(2011年)を聴き狂っていました。ファーストはすごく苦手だったんですけど、セカンドを聴いたとき、立て続けにBPM170~180くらいの曲が続いて、なんだこの疾走感?と惹かれた。バンドからメンバーが去って、もう完全にバンド・サウンドもやめたんだなってところがカッコよかったですね」
――いま名前があがったバンドしかり、『ANALOG』はPFCのディスコグラフィーのなかでも、ネオアコやネオ・サイケといったサウンドからの影響がもっとも屈託なく出た作品になっていますね。
エンドウ「特にキュアーからの影響は大きかったですね」
カミヤマ「あと、“Dancing Queen”あたりはペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハートが参考になっていて」
エンドウ「そうだ! ペインズも聴き狂ってましたね(笑)。あとは、ジョイ・ディヴィジョンなんかも。最終的に未収録になった曲が1つあって、めちゃくちゃ激しく叫んでいる曲だったんですけど、それはジザメリやニルヴァーナを意識していた。やっぱり僕たちがやっていくうえで、90年代のバンドは滅茶苦茶大きい存在なんです。いまでもそうなんですけど、そういう憧れをひたすらに反映させようとしていた時期でした。〈自分はこういう血が入ってるんだぜ〉と世に知らしめたい、みたいな」
――この作品でPFCを知ったリスナーも少なからずいたと思うんですが、そうしたファンからのレスポンスを感じた瞬間もありました?
エンドウ「うーん、あんまりなかったですね。というのも当時は閉じていたというか、知らしめるという気持ちもありつつ、〈自分が歌いたいからやっている〉という気持ちが強かったので、ツアーとかも廻らなかったし。なので、あまり周りがどうとかを気にしていなかったです。ただ、CDショップに行くと自分のCDが置いてあることは気味が悪いなと思っていました(笑)」
――ハハハ(笑)。その〈気味の悪さ〉はカミヤマさんにも共通していた感覚なんですか?
カミヤマ「いや、それはエンドウ独特の感覚で(笑)、僕は普通にショップの棚に背表紙が並んでいるだけでも嬉しかったですね」
エンドウ「なんなんだろうね、あの感覚は。例えば自分の卒業アルバムがTVに映ったときの不気味さというか、それに近いかもしれないな」
――それを言い換えると、当時のエンドウさんは、まだPFCをパブリックなものとして捉えてなかったということですか?
エンドウ「あー、そうですね。自分の部屋を見せているじゃないですけど、自分の大事なものを公開しているというか」
聴き手をもっと騙してやりたいと挑発してみたんです
――『PELICAN FANCLUB』(以下、『PFC』)は『ANALOG』とは違って、オルタナやシューゲイザーからの影響が窺えるノイジーなサウンドになっています。制作時に参照点となったバンドも『ANALOG』とは違っているんじゃないですか?
エンドウ「かなり違いましたね。リンゴ・デススターであったり、90年代で言えばライドだったり、そういったバンドを参考に、『ANALOG』が平面だったら『PFC』はもっと奥行きのある立体的なものにしたいと思っていました。音に関してもとにかく重ねていったし、しつこいくらいにリヴァーブもかけて」
――その一方で、あいかわらずネオアコ/アノラック的な曲もあって、例えば“Police City”はコミュニオンズの“Love Stands Still”(2014年)を想起しました。
エンドウ「あー! 僕、コミュニオンズにはかなり感銘を受けたし、影響されました」
――『PFC』はマンチェスターっぽいグルーヴの曲もあるし、初期のコミュニオンズに通じていると思います。
エンドウ「スミスとかも大好きなんで、そういうマンチェスターの匂いを僕らも採り入れたいなと思っていました」
――当初から前作とは異なるサウンドにしようという意識があったんですか?
エンドウ「作曲するときはすごくありましたね。『ANALOG』を出したときに友人から〈PFCってこんなにポップだったっけ?〉と言われたんですよ。ライヴでは激しい曲もやっていたんですけど、それらはあえて入れなかったから。だから、そう捉える人がいたんだってことが、僕にとって最初の世論というか、それが衝撃的だったし、そうなるんだったら、もっと裏表をわかんないように騙してやりたいなと思ったんです。だから、詞の書き方とかも変えて、激しい曲を入れて」
――受け取られ方が予想外だったという点も、さっきの不気味さに繋がっていたのかもしれません。
エンドウ「うん、そうですね。僕自身が思ったようには聴き手に伝わらないんだなと感じていた」
――〈騙してやりたい〉と言われましたが、『PFC』の歌詞は聴き手に疑問を投げかけるようなフレーズが多いですよね。実際、作品のテーマは〈謎〉だったそうで。
エンドウ「もともとバンドをやるうえで、〈謎〉というのは僕のなかで大きなテーマだったんです。当時は日記的な感じで曲も書いていたんですけど、例えばニュースを見ていたり、電車で何かを見たりしたときに感じた〈どうして?〉という疑問――そういう謎から曲作りはスタートしていたんです。僕の言動力である〈謎〉を、曲としても歌詞としても掘り下げたいなと取り組んでいました」
――『ANALOG』では〈謎〉というテーマはそこまで顕在化していなかった?
エンドウ「『ANALOG』のときは、それらを〈謎〉としては出さずに、僕の目に見えた話として書いていましたね。だから、曲の主人公はすべて僕自身だったんです。『PFC』に関しては、それぞれに主人公がいるというか、全部が全部自分の話ではなく〈これは何?〉という提示が中心にある。この概念って何?みたいな。そういう挑発をした作品でした」
――『ANALOG』は私小説的な側面も強い作品だったんですね。それは、ショップに並んでいると居心地が悪いわけだ。
一同「ハハハ(笑)!」
エンドウ「そうなんです! 自分は千葉で育ったんですけど、千葉の外房線という電車に乗って出来た歌とか、そういう個人的な体験が全国のタワーレコードに置かれるという。居心地の悪さはそこでした(笑)」
――そのうえで、『PFC』での挑発というのは、リスナーが前提になったアプローチでもあります。
エンドウ「そう、聴き手がいるということを意識せざるをえなかったんです」