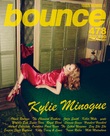くるりの12枚目、4年ぶりとなるオリジナル・アルバム『ソングライン』が9月19日(水)にリリースされた。これまで歌やメロディーに重きを置きつつも、クラシックや民族音楽など多様なジャンルを吸収し、実験的な楽曲も多く発表してきた彼らだが、今作ではそういった実験精神を極力排除。より歌とメロディーにフォーカスした、原点回帰とも言えるアルバムに仕上がった。
今回Mikikiでは佐藤征史(ベース)とファンファン(トランペット)の二人にインタヴューを行い、改めて原点へと立ち返った作品になった理由や、不在だった岸田繁(ヴォーカル、ギター)の見据えるヴィジョンなどについて語っていただいた。
(アルバムを出すまでの4年間は)過去を見つめ直すいい機会でした。いや、見つめ直してもいないですね(笑)
――今作のタイトルにもなっている〈ソングライン〉という言葉は、オーストラリアの先住民族・アボリジニの言葉だそうですね。本作は、もともとそういうテーマで作られたのでしょうか?
佐藤征史「この言葉はアボリジニの方々が、例えば〈この岩を曲がったら池がある〉みたいな地形や自然現象に付けた歌で、自分たちの住む場所を表現していて、そういうことが結果的に、時代を超えても〈歌で繋がっている〉っていう意味のようなんです。今回のアルバムには新旧いろんな曲があって、中にはデビュー前にやっていて、今回〈思い出したから録ってみよう〉みたいな曲もあるんですよね。我々は一昨年デビュー20周年を迎えましたけど、そういう意味では過去と現在がリンクしていて、〈歌で繋がっている〉っていうことにも通じていて、〈いいタイトルだね〉ってしっくりきて決めたんですよね。それも後付けっちゃあ後付けなんですけど(笑)」
――(笑)。それではアルバムが完成するまでの〈ソングライン〉も伺いつつ、今日いらっしゃらない岸田繁さんについても伺えればと思います。前作『THE PIER』から今作までの間にいろいろなことがあったのは存じ上げておりますが、結果的に4年、間が空きましたね。
佐藤「そうですねえ……いろいろ振り返ってたんですかね(笑)」
――デビュー20周年もあって、かつてのアルバムを再現するライヴがあったり、オールタイム・ベストも出たりしましたからね。
佐藤「ファンちゃん(ファンファン)が産休でいいひん時に、〈NOW AND THEN〉っていう過去のライヴを再現するっていうことがたまたま出来たんですけど、そういう過去を見つめ直すいい機会でした。いや、見つめ直してもいないですね(笑)。たまたまそういう期間だった」
――たまたまですか(笑)。
佐藤「アルバムはもっと早く出るはずだったんですけど、くるりって自分たちでもアルバム・アーティストだなとは思っていて、作り始めるまでがなかなか大変で。もちろんアルバムってその年その年の自分たちの活動の冠みたいなものだと思ってるから、早く作りたかったんですけど、このご時世にアルバムをCDで買って頭から最後までしっかり聴く人も減ってるだろうし。だから最初は6~7曲入りのEPを、間をそんなに空けずに2枚出すなんてことを考えてました。その時は〈歌もの〉と〈ふざけたもの〉に分けようっていう話だったんですね。それで〈歌もの〉から作ろうとするんですけど、やっぱり作り始めるまでが……(笑)」
――その重い腰を上げて、本格的に作ろうとし始めたのはいつですか?
佐藤「今年の頭くらいですね」
――そんな最近なんですね。
佐藤「今までもそうなんですけど、作ってるうちにコンセプトというか、アルバムを統一する味みたいなものが見えてくるんです。〈このスパイスが全曲に入ってたらいいね〉みたいな。それが決まるまでは、単品でいい曲が2、3曲あっても全体像がなかなか見えないんですよね。それが見えたら割とすぐ方向が定まって、ギアが4速までポンと入れられるんですけど、それまでは1速でノロノロ~って走ってて。その期間が長かったです」
――なるほど。
佐藤「でも、“その線は水平線”の音が録れた時にすごく説得力が感じられて、〈そのままでいいじゃん〉って思えたんで、ほかの曲も〈そのまま〉を活かすように録っていったんです」
――楽曲の制作の順序的にはどう進めていったんですか?
佐藤「曲自体はそれぞれすでに出来ていたものが多くて。“忘れないように”はデビュー前のライヴで1、2回やってる曲です。“春を待つ”もデビュー前のデモ録りで一応録ってるし。“その線は水平線”は7、8年前に出来て、“landslide”も3、4年前にはありましたね」
ファンファン「ライヴでも披露してますね」
佐藤「“Tokyo OP”は去年の8月にベーシックだけのレコーディングは終わってましたし、“どれくらいの”は2年前の音博(京都音楽博覧会in梅小路公園)でやったし。“風は野を越え”も2015年にアルバム作ろうって時にドラマーを呼んでセッション大会をした時に原型があった曲で。アルバム用に新しく作ったのは“How Can I Do?”“ソングライン”“だいじなこと”“特別な日”、あと“News”ですね」
――すでに出来ていた曲も多くあって、新曲もあって、アルバムにどの曲を入れるというのはどうジャッジするんですか?
佐藤「最初に〈歌ものを作ろう、そういう曲を集めよう〉となった時に、古い曲が候補に入ってきたんですよ。“春を待つ”なんて、すごくくるりらしいんですけど、ここまでフォーキーな曲って、くるりらしすぎて逆にやってきてない。アルバムでこういう曲を多くするってことは今までやってこなかったんですよね。ついふざけた曲を入れたりして(笑)」
ファンファン「うんうん」
佐藤「でも今回は〈歌に軸を置く〉というのをスタート地点にしたので、こういう曲が集まり、こういう並びになって、『ソングライン』というタイトルになったんだと思います」
当たり前のことをちゃんとやったアルバム
佐藤「人に言われて思ったんですけど、今作って地味なアルバムですよね」
――いやいや(笑)。地味っていうと悪く聞こえますけど、〈くるり、いい歳の重ね方をしたなあ〉とは思いました。
一同「(笑)」
佐藤「自分たちもそう思ってて、昔だったら絶対こんな作品は出来てない。何かしらで〈とんがらなアカン〉って思ってたはずですけど、なんだかんだで余計なものは抜けていきましたね」
――前作(『THE PIER』)なんてリード・トラックの“Liberty&Gravity”のPVで踊ってましたからね(笑)。
佐藤「踊ってましたね(笑)」
――でも今作は、例えば仕事で疲れて帰ってきて聴くと骨身に沁み込みやすいような、そんなアルバムになってると思います。
佐藤「やっぱり音楽ってメロディーと歌がメインじゃないですか。楽器やアレンジももちろん大事ですけど、今作ではメロディーと歌を大事にしたので、全体的に牧歌的なんだと思います。(岸田)繁君の書く歌詞も、聴く人によって答えが違うような、ほとんど抽象的な歌詞になってるし。だからさっき〈地味〉って言いましたけど、ド派手なお化粧はしてないけれど、当たり前のことをちゃんとやったというか。例えばオーケストラ・アレンジも曲を際立たせるために用意しているし、聴きごたえはあると思います」
――そうですね。アルバム名でもあり、リード・トラックのタイトルでもある〈ソングライン〉という言葉は、そういったテーマを象徴していると思うのですが、この名前はいつ決まったんですか?
佐藤「全部録り終わってからですね。先にアルバムが『ソングライン』というタイトルに決まって、もともとは別のタイトルだったこの曲がアルバムを象徴するような楽曲になったし、その時使っていたタイトルが使えなくなってしまったのもあって、“ソングライン”というタイトル・トラックにしようと」
――曲名よりもアルバム名が先だったんですね。岸田さんのセルフ・ライナーによると、“ソングライン”はもともとサンフジンズ用の楽曲だったそうで。奥田民生さん(サンフジンズではカイ・ギョーイ名義)の声でも合いそうな曲だから納得できる一方で、サンフジンズの曲がくるり用になって、それがアルバムのタイトル曲になるっていうのは意外でもあります。
佐藤「繁君も気に入ってた曲だと思うんですけど、サンフジンズさんも〈じゃあいいよ〉って言ってくれはったんでね。自分はサンフジンズ・ヴァージョンも聴いたことがありますけど、まったく違うものになりました(笑)。やっぱりサンフジンズはサンフジンズだからそれはそれでカッコいいんですけど、くるりはくるりで〈よくぞここまで音詰め込んだな〉って思うし」
――この曲は、例えばビートルズやELO、あるいはブライアン・ウィルソンやフィル・スペクターといったさまざまな先人たちへの愛だったり影響だったりも感じました。途中“ボレロ”(モーリス・ラヴェル作)のオマージュも出てきますね。
佐藤「“ボレロ”に関してはたまたま思い付いた洒落だと思いますけど(笑)。今回アルバムは全部同じ方にミックスをしていただいて、〈この曲のギターは何年代のイギリスで〉とか〈このバンドのギターの音〉とか、そういうことを明確にやっていただいたんです。例えば使う機材にしても〈73年のこのアルバムのこの音だったら、このエフェクターはないから使っちゃダメ〉とか。そういうところがこの曲だけでなく、アルバム全体に出てるんだと思います」
――ドンピシャの音が出せると。
佐藤「はい。しかもレコーディングって普通どんな人でもいい音で録りたがりますよね。でもそのエンジニアさんは、CDで鳴る音そのままで録ってくれるんです。例えばジョン・レノンが出してた音をギターで作ってマイクで録っても、今の技術で鳴らすと全然別ものになってしまう。それがそのまま鳴るように録ってくれる人で、だから楽器が鳴ってる音と作品で聴いた時の音の違いがないんです」
――じゃあ聴く際はいい環境で聴いたほうがいいですね。
佐藤「そうですね。でもファンちゃんが〈久しぶりにBGMになるアルバムだ〉とも言ってて」
ファンファン「自分のなかでアルバムってなると1曲目から構えて〈ちゃんと聴くぞ〉って思うことが多くて、このアルバムはそうじゃなくても聴ける心地よさがあると思いますね」
佐藤「前作なんて単語の羅列で歌詞を作ることも多かったから、ちょっと聴き逃しても意味わからなくなるし、ちゃんと聴いたらそれはそれで意味わからなくなったりして。今作は聴き流しても大丈夫だと思うんです」
二人が思う、岸田繁の歌詞と作曲
――歌詞の話が出ましたけど、お二人は岸田さんに歌詞の意味を聞いたりすることはあるんですか?
ファンファン「ないです(笑)」
佐藤「ないですね(笑)。まあ、繁君の歌詞で初めて知った単語の意味とかは聞きますけど。今パッと出てきたのは“家出娘”(2006年作『ベスト オブ くるり -TOWER OF MUSIC LOVER-』収録)の〈アノラック〉って単語とか。〈
ファンファン「(笑)」
佐藤「あとは今作で “風は野を越え”の歌詞ってすごい難解だと思うんですけど、繁君が〈よう文学的とか言われてるけど、自分でそんなこと思ったこともないし、そんなふうにしてきたつもりもないから、初めてわざとそういうふうに書いたったわ〉って言ってましたね。自分も〈ほんまやなあ、漢字難しいなあ〉って言って(笑)」
ファンファン「私も漢字読めへんかった(笑)」
佐藤「昔、繁君がもっと身を削って歌詞を書いてた時は、一番近くにいるので〈あ、これはあの時のことなのかな〉とかわかるような気もしましたけど、最近はそういう歌詞も書かへんし。〈この曲は悩んではるのかな〉とか、〈“How Can I Do?”ってすごいタイトルだな〉とか、〈“だいじなこと”は1分半でよくここまで詰め込んだな〉とか、聞かないけどいろいろ思ってはいますね。今作で言うと“どれくらいの”とか“News”はいちばん自然に書いてると思いますよ」
――そういうのはわかるものなんですね。
佐藤「繁君の歌詞って、流行り廃りがない言葉を使っていて。〈サザエさん〉のアニメに携帯電話が出てこないように、くるりの世界観に合った言葉しか出てこないので、古臭い懐メロにならないんですよね。もちろん時代を切り取った歌詞もいいとは思うんですけど、くるりの歌詞は時代に関係ない風景とか感情とかで作られているなと、勝手に思ってます」
ファンファン「あと、歌詞をもらって最初に読んでも気にならなかったのに、ライヴでやってる途中で急に耳に残る歌詞があったりして、印象強い言葉ってそのときどきによって変わっていくのが面白いです」
――今作でもありますか?
ファンファン「いま思い浮かんだのは、“その線は水平線”の間奏でトランペットが一瞬出てくるんですけど、それを録るのにすごい時間がかかって。岸田さんから〈前後の歌詞で歌っていることを橋渡しするように思い描いて吹いてみて〉って言われて。直前の〈消さないで〉っていう歌詞は印象に残ってます」
佐藤「ファンちゃんって音を入れるのが一番最後だから大変なんですよ。楽器も録って歌も録り終わってから入れるから、すでに世界観が99%出来ていて、最後の1%を決めるのがファンちゃんで。自分らはやり逃げできるんですよね(笑)。そこで歌とかけ離れたことってなかなかできないし、〈頑張って! 大変だね!〉って思って見てます(笑)」
ファンファン「佐藤さんたちは何もないところからスタートするから、違う苦労はあると思いますけどね(笑)」
佐藤「それで〈違うな〉ってなったら後から録り直しするから(笑)。『ワルツを踊れ(Tanz Walzer)』でウィーンに行って“ブレーメン”っていう曲を録った時は、2ヶ月半後くらいにもう一回録ってますからね(笑)。アルバムを作り出してみて、〈入口からズレてるな〉って感覚になったらもう一回やり直すこともあります。実は“ソングライン”って曲なんてドラマーさん3人分のヴァージョンがあるんです。それぞれステキなところはいっぱいあるんですけど、アルバムをトータルで見たら〈違うかな〉っていうヴァージョンもあるので」
――トランペットのフレーズはあらかじめ決まってるんですか?
ファンファン「今回は他の楽器も含めて、ほぼ岸田さんがアンサンブルで全部書いてきたので、もともと決まってるものがほとんどでした。“その線は水平線”は最初自分が作ってきたフレーズと、岸田さんが持ってきたメロディーとどっちにするかっていう話があって、答えが出ないまま録音とミックスをしてもらって、結果半々で使われてるっていうのはありましたけど。そういうアイデアは自分だったら全然思い浮かばないことだったので〈おおっ! いい!〉って思いました(笑)」
佐藤「繁君が曲を書いた時点でオーケストレーションありきの曲もあるから、そこで自分勝手なことはできないじゃないですか。そこは考えられてる通りに演奏しますね」
――岸田さんってどれくらいデモをかっちり作ってこられるんですか?
佐藤「前回の『THE PIER』からデモをちゃんと作るようになったんですけど、その時はオルガンでコードだけ打ち込んだようなデモだったんです。でも交響曲(第一番)を書いたということもあってか、今作ではデモをある程度きちっと作ってきて。エラいですよね(笑)」
――そうなんですね。
佐藤「その上でエレキ(ギター)だったりアコギだったり、割とちゃんとしたヴォーカルを乗せてきて。実はデモのヴォーカルをそのまま使った曲もあるんです。ベースにしても、今回のうち6、7割は打ち込んで作ってありました。ウワモノとの関係性があるからフレーズを勝手に変えられないし、それは結構大変だったんです」
――ベースのフレーズがシンプルすぎて、〈ちょっとオカズを入れたい〉とか思ったりはしないですか?
佐藤「一切ないですね。逆にここだけは声を大にして言いたいんですけど、Aメロが4回あるとしたら4回全部フレーズが違うんですよ。それを覚えるほうがどれだけ大変か(笑)。オカズはライヴで盛り上がったら好き勝手弾けばいいんですけど、そういうフレーズは流れがあるから勝手に変えられないんですよ。大変なだけで誰もそんなとこ聴かないだろうし(笑)」
――そんなことないですよ(笑)!
佐藤「“ソングライン”とか“landslide”も大変だったし、“Tokyo OP”なんて〈真ん中のパートどうやって覚えんねん〉って思いましたよ(笑)。でもそうやっていろんな音が複雑に入り組んでるのに、出来上がったらそう聴こえない。それがいちばん大事なことですよね。歌や歌詞に自然と耳がいけばこっちの勝ちなんやと思ってます」