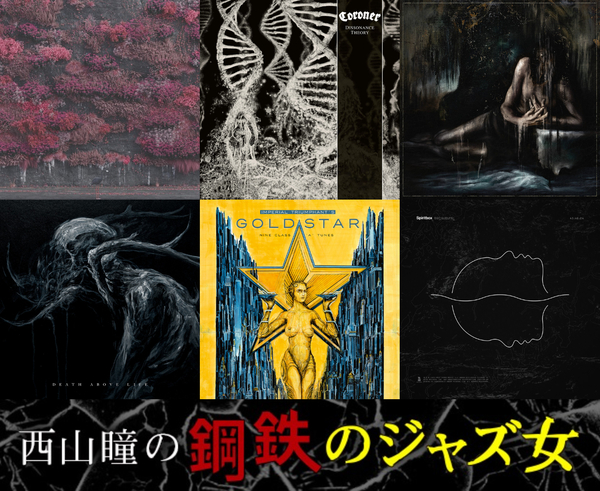2000年代のインディーは〈置き換え〉の時代
――2009年に、ベイルートと〈リアルピープル〉っていうザックの別名義でのユニットをカップリングした2枚組のEP『March Of The Zapotec / Holland EP』がリリースされたんですよ。リアルピープルは、ザックがベイルート以前――10代の頃に活動していたときの名前で、サウンド的にはシンセ・ポップ。もともと彼は初期のマグネティック・フィールズみたいなシンセ・ポップが好きで、そのシンセのパートをブラスに置き換えるところからスタートしたらしいんですよね。
岡田「楽器を置き換えるみたいな感覚はわかりますね。ある程度音楽をやりつくしたあとに、楽器を置き換えていくみたいなことが2000年代には多かった。ギター・ロックのギターのフレーズをシンセで弾いたり、フリート・フォクシーズはシンセをコーラスに置き換えて過剰な音響にしたり。ベイルートはトラディショナルな音楽として聴いていたからそういうふうには思わなかったけど、シンセ・ポップをブラスに変えたというと俄然聴く気がしてくる(笑)。そう言われると、この後の『No No No』っていうアルバムも〈なるほどな〉って思えますね」
――『The Flying Club Cup』といま岡田くんが出した『No No No』の間には、2011年にアルバム『The Rip Tide』をリリースしています。『The Rip Tide』には、シャロン・ヴァン・エッテンがヴォーカルで参加していたりもするんですが、このアルバムはどうでした?
三船「ザックが東欧とかフランスとか特定のモチーフを纏うのを止めて、自分っぽくなっていった契機が『The Rip Tide』という印象ですね」
――普通にギター・ポップとかチェンバー・ポップみたいに聴こえる瞬間もありますよね。なので、ディヴァイン・コメディとか、ベル&セバスチャンが好きな人でも聴けるのかなと思う。
三船「バルカンかぶれとか、フランスかぶれじゃなくなって、普通にシンプルに、ピアノとホーンと歌みたいな。だからサラッとしていて、何回も聴けるアルバムですよね」
――あと当時、ザックは長年のガールフレンドと、地元のサンタフェで結婚したんですよ。その感じが反映されていたのかも。
岡田「結婚して良くなったパターンですか」
三船「ジェイムス・ブレイクとは違うね」
――しかしその数年後に、無事離婚しまして(笑)。
三船・岡田「……」
――さっき岡田くんが言った『No No No』は、離婚したあとに作られたアルバムなんです。でも、そのあとトルコ出身の女性と恋におちたらしくて。だから『No No No』の歌詞には別れが仄めかされているものが多いんだけど、なぜか音楽自体は結構陽気。
三船「確かに陽気ですよね。ザックは(ダーティ・プロジェクターズの)デイヴ・ロングストレスみたいにはならなかった※」
※ダーティ・プロジェクターズの2017年作『Dirty Projectors』は、デイヴと元メンバーでもあるアンバー・コフマンとの別れがモチーフになっており〈失恋アルバム〉と言われている
――(笑)。でも、あれは嘘じゃないけど、デイヴは当時すでに新しい彼女がいたみたいよ。彼女ができていたのに、「俺はもうダメだ」みたいなことを歌っていた。
三船「あ、同情を買って。あいつ~(笑)」
岡田「僕たち、踊らされてたんだね(笑)」

三船「『The Rip Tide』より、『No No No』のほうが不思議とあっさりと聴けるんですよね」
――実際このアルバム、すごく短いんですよ。30分で終わるっていう。
三船「サウンド的には、ピコピコしてきたなと思ったけど」
岡田「ホーンがいなくなった印象もありました」
――そうそう、ホーンも参加してはいるんだけど、あんまりそこにこだわっていない感じで。
三船「タイトル曲のアレンジが好きですね」
――その曲のMVもカラフルで、オシャレな感じになっていて。
岡田「僕はこのアルバムがいちばん好きだな」
三船「エナジーが落ち着いた気がする。キャラを纏うのをやめつつ 、オリジナル路線を深めていった」
――岡田くんがリアルタイムで聴いたのはこの作品から?
岡田「リアルタイムで〈ベイルート知ってます、新譜が出ます〉っていうのは『No No No』からでしたね。ちょうどバンド(森は生きている)が解散したばっかりで、暗い曲を聴きたくなかったからすごく良かったです(笑)。このへんから全体的に音楽が明るくなってきたような印象もあるし、ナードなインディー・ロックみたいなのがなくなった時期に、ベイルートもカラフルなジャケになって、これでいいんだって思った記憶がありますね」