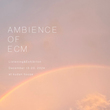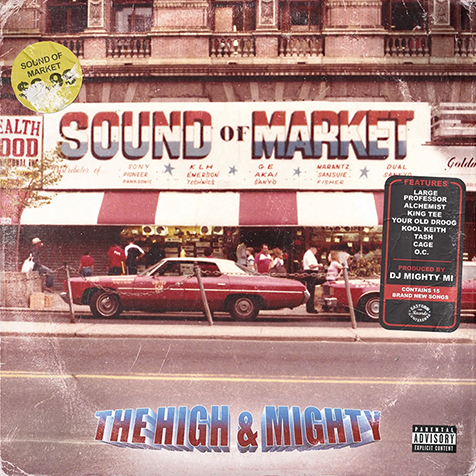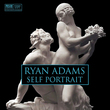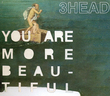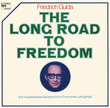フィンランドの映画監督、アキ・カウリスマキの出世作となった「レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ」(89年)とベイルートについて、以前こんなふうに書いたことがある。ロシアの架空のロック・バンドがアメリカ大陸を横断し、メキシコでトップ10入りするまでを描いたあの映画は、東欧で生まれたポルカがメキシコに渡り、マリアッチに影響を与えるという音楽の歴史を可視化したとも言える作品だった。そして、その道を逆から辿るように、メキシコとの国境沿いにあるアメリカのニュー・メキシコ州に生まれ、バルカン半島のジプシー・ブラス・ミュージックに辿り着いたのが、ベイルートの首謀者ザック・コンドンなのではないだろうかと。
2006年、ザックが弱冠20歳のときにリリースしたファースト・アルバム『Gulag Orkestar』でバルカン・ブラスとインディー・ロックを融合させ、世界を熱狂させたベイルートが、2015年作『No No No』から4年ぶりとなる新作『Gallipoli』をリリースした。これまでにもソ連やフランス、オーストラリアなどを作品のモチーフにしてきたザックが本作でインスピレーションを受けたのは、中世の趣を残すイタリアの城塞都市・ガッリーポリだという。
今回は、ベイルートのファンを自認し、ブラスを使ったバンド・サウンドや異国情緒漂うメロディーなど音楽性の面でもベイルートと共通点の多いROTH BART BARON(以下、ロット)のフロントマン・三船雅也と、元・森は生きているのリーダーであり、現在はソロ名義での活動を行いつつ、ロットのサポート・ギタリストも務めている岡田拓郎を迎え、新作の魅力に迫った。カナダやUKでのレコーディングや各国を廻るツアーなど渡航経験も豊富な三船と、主にドラクエで冒険していたというインドア派(?)の岡田拓郎。音楽を紹介しているYouTube番組〈BIZARRE TV〉のメイン・パーソナリティーでもある両者は『Gallipoli』をどう捉えたのだろうか。
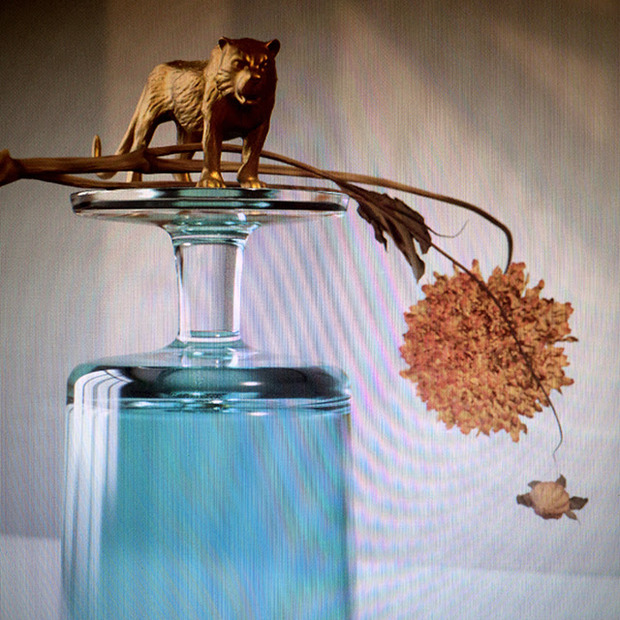
最初の転機は骨折
――最初にバイオ的なことから紹介すると、ベイルートのザック・コンドンは86年生まれ。出身はニュー・メキシコ州のサンタフェ。14歳のときに橋から落ちて左手首を複雑骨折したことで、当時習っていたギターを止めてトランペットを手にしたそう。もともとギターはお父さんに無理やり習わされていたみたいで、あんまり好きじゃなかったらしい。
岡田拓郎「なんで橋から落ちたんだろう?」
三船雅也「わざとっていう説もあるんじゃない(笑)? もうギターは弾きたくないって」
――そして17歳のときに、バイト先の映画館で観たエミール・クストリッツァの映画に衝撃を受け、高校を中退してお兄さんと一緒にヨーロッパを旅行しました。ベイルートの音楽的な特徴であるジプシー・ブラスともその流れで出会ったようですね。そうした経験を経て音楽性を確立していき、ファースト・アルバム『Gulag Orkestar』が世界的な評価を得る……と。おふたりのベイルートとの出会いは?
三船「うーん……もしかしたら初めて知ったのは、彼らが出ていた〈The Take Away Shows〉かもしれない。それを観てセカンド・アルバムの『The Flying Club Cup』(2007年)を買ったんですよ。当時、あの番組の影響力はデカかったですよね」
――ディレクターだったヴィンセント・ムーンっていう映像作家のセンスが反映されていて、「あれに出てるバンドは良いぞ」みたいな雰囲気がありましたよね。いまは他の人がコンセプトを引き継いでいるんだけど、手広くやりすぎていてあの頃のようなセレクト感はないと思う。
岡田「音質的にも〈部屋のほうが良くね?〉となって、〈Tiny Desk Concerts〉に取って変わられたのかも(笑)」
――ベイルートはファースト・アルバムの『Gulag Orkestar』ではバルカン半島のジプシー・ブラスに影響を受けていたけど、セカンドの『The Flying Club Cup』ではフランス映画の台詞をサンプリングしていたり、ジャック・ブレルなんかのシャンソン歌手に影響を受けたりしていて。レコーディング場所はアーケイド・ファイアが所有していたモントリオールの教会。その関係なのかオーウェン・パレットがアレンジで全面的に参加していて、彼がメインで歌っている曲も入っています。三船くんが初めてこのアルバムを聴いたときの感想は?
三船「その頃から、アメリカのバンドがまたおもしろくなっていきましたよね。フリート・フォクシーズもいればグリズリー・ベアもいて、さらにヴァンパイア・ウィークエンドが出てきて。そのなかでもベイルートは特に変わってるなと思いました。名前からして〈ベイルート〉だし、さっきも言ったようにフランス映画の音をサンプリングしたり、異質感があって引っ掛かっていたというか。アメリカにはないリズムで、パッションも独特だった。当時、エイト・ビート以外のバンドがたくさん出てきておもしろく感じてたんですけど、そのなかのひとつですね」