
!!!(チック・チック・チック)が新作『Wallop』をリリースした。パンク × ファンクなサウンドで衝撃を与えた彼らもすでに20年選手。ここ数作は以前より情報量を抑えたプロダクションのもと、ダンス・ミュージック的な側面を強めてきた。『Wallop』は近作のそうした傾向を引き継ぎつつ、ガラージ・ハウスや2ステップ、ダブステップなど特にUKのエレクトロニック・ダンス・ミュージックを採り入れた新機軸も聴かせてくれる。
2001年の初作『!!!』から数えて8作目。最新作からまず聴くべきなのは当然だが、そのあとに過去作もチェックしたい!となったとき、若いリスナーはどのアルバムから手を出すべきか悩むことも多いのではないか。そこで今回はバンドのフロントマンにしてアイコン的な存在、ニック・オファーに新作『Wallop』も含めた彼らの全アルバムをみずから点数付けしてもらった。はたして本人がもっともお気に入りとする作品はどれなのか? バンドのストーリーを追体験できる記事にもなったので、10月終盤から開催される来日公演の予習もかねて彼らのディスコグラフィーを振り返ってみよう。
――今回は!!!がこれまでリリースしてきた全アルバムをみずから100点満点で採点してもらうという企画です。
「最初に言っておきたいのは、今回これまでのレコードに関しての話をするけど、それらのレコードを何年も聴いていないってことはわかっておいてほしい。リリースされてから一度も聴いてないといっても過言ではないくらいだな。曲をたまーに聴いたりはするけど。だから、記憶を頼りに答えることにする」
――OKです。じゃあスタートしましょう。
『!!!』(2001年)

――まず2001年のファースト・アルバム『!!!』は?
「これは82点かな」
――いきなり高い点数ですね。
「俺のレコードなんだから、もちろんいい点をあげるに決まってるだろ(笑)」
――82点の理由は?
「当時の俺たちにしてはベストを尽くしたからさ。それまでに一枚もレコードを作ったことのない状況だったし、初めてコンピューターで音楽を作って、それは俺たちにとって大きな一歩だった。実は、あのレコードを作った理由は、俺たちがNYに引っ越す直前で、その後は解散するだろうと思っていたからなんだ。もう一緒に音楽を作ることはないだろうから、いまある曲を記録しておこうって話だった。で、実際に出来上がると、〈俺たちにもレコードって作れるんだ〉という感情が湧いた。すっごく興奮したね。
ピッチフォークのレヴューでは、〈ヴァイナルにレコーディングされた史上最悪のヴォーカル〉って書かれたけど(笑)。でも俺的には歌詞の新しい書き方を発見できたし、いい時期だったからそれでいい。だから、俺にとってはいいレコードなんだ」
――もともとあなたを含めてサクラメントのハードコア・パンク・シーンで複数のバンドにいたメンバーが、90年代の後半に!!!を結成したんですよね。どうしてダンス・ミュージックをやろうと思ったんですか?
「俺は当時ディスコのカヴァー・バンドにいて、マリオ(・アンドレオーニ、ギター)のパンク・バンドとツアーしてたんだ。そのツアーが毎晩楽しくてさ。俺たちのバンドのディスコ・サウンドと、マリオのバンドが持つエナジーとが混ざり合って最高だった。だから、ツアーから帰ってきたときに、〈マリオのバンドのヴァイブを持ったディスコをやろうぜ〉って話になったんだ。それが転換のきっかけさ。当時、もうリスナーとしてパンクは聴かなくなってたしな。〈なんで俺たちは自分たちが聴きもしない音楽を作ってるんだ?〉って思いはじめていたんだよ」
『Louden Up Now』(2004年)
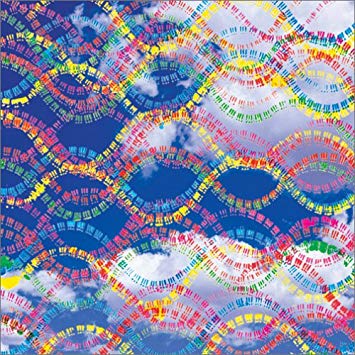
――セカンド・アルバム『Louden Up Now』はいかがでしょう? リード・シングルの“Me And Giuliani Down By The School Yard(A True Story)”はダンス・パンク・シーンのアンセムになりました。
「78点。あのレコードは俺がNYに越してから初めて作った作品で、全体を見渡せるプロデューサーがいなかった。大勢のアイデアが飛び交って、かつ西海岸と東海岸の間でコミュニケーションをとって、新しい活動の仕方を模索していた時期だったんだ。いいポイントももちろんあるけど、もっといい作品が作れたんじゃないかなって思うんだよな。『Louden Up Now』がベストだっていう人たちがいるのも知ってる。当時ああいうサウンドが出たのは新鮮だったしね。でも個人的には、お気に入りの曲が数曲しかないアルバムなんだ」
――このアルバムはパンク/オルタナの拠点であるUSのタッチ&ゴーと、UKのエレクトロニック・ミュージック・レーベル、ワープとのダブルネームでリリースされました。このことは、当時のあなたたちの立ち位置を象徴している気がしますが、パンク・カルチャーとダンス・カルチャーの挟間にいたことで、苦労した面はありますか?
「いや、苦労したとは思わない。狭間にいたのはおもしろかったよ。パンクとダンスのミュージシャンが話をしていてまったく噛み合ってないのを見たりさ(笑)。ダンス・クラブにパンク・バンドとして行くのは楽しかった。シャンパンがあるような自分たちはあまり馴染みのない世界だけど、そのサウンドシステムを使って自分たちがやりたい音楽を演奏することができた。それに、そういう場で聴く新しい音楽にインスピレーションを受けたりもしたしね。あれはエキサイティングな時期だったな」
『Myth Takes』(2007年)

――サード・アルバム『Myth Takes』は何点?
「俺はこのレコード、結構好きなんだ。というか大好き。95点」
――ハイスコアが出ましたね。
「いや待って、92点(笑)」
――その理由は(笑)?
「セカンド・レコードをイマイチに思っていたから、まだ何かを求めていたし、何かを証明したかった。それが形になったのがこのアルバムなんだ。それに、最初のレコードをプロデュースしてくれたジャスティン(・ヴァン・ダー・ヴォルゲン)が戻ってきてくれた。彼が来て核となってくれたことで、形にならず漂っていたいろいろなアイデアが機能しはじめたんだ。
皆でパーティーに行きながら新しいことをたくさん発見して、それを音に落とし込むっていう楽しい時期だった。NYに来て、クールなものにたくさん触れて、多くを学びつつも、来たてのときよりもクールぶったり調子に乗ったりせず、もうちょっと謙虚になれていたのがこの時期なんだ」
――濃密なエネルギーが渦巻いている一方で、プロダクションは細部まで整理されているからダンスするにも最適。まさに最強のパンク・ファンク・レコードだと思います! あと、このアルバムは2009年に不慮の事故で亡くなったドラマー、ジェリー・フックスをフィーチャーした作品でもありますよね
「レコードの大部分のサウンドが俺にとっては彼のサウンド。このレコードを聴くと、彼がいるなというのがわかるんだ。『Myth Takes』をヴィジュアルとして頭のなかで考えると、彼の姿が浮かぶね」
『Strange Weather, Isn't It?』(2010年)

――4作目の『Strange Weather, Isn't It?』は、これまでよりロック色が抑え目でダンス・ミュージックとしての側面を強めた作品という印象でした。
「これは72点かな。セカンドよりも低い。プロデューサー(エリック・ブルーチェックと思われる)とあまりコネクションを感じなかったんだ。でもその〈反プロデューサー〉という面でバンドがひとつになったってのはあったけど……。人としてはナイスガイで好きだったんだけどね。アイデアが俺たちとは違っていただけ。
あと、ドラマーのジョン(・ピュー)がバンドを出たのが痛かった。それまでのレコードでは、彼がたくさんいいアイデアを出してくれていたからね。それに、バンドのなかで口論が絶えない時期でもあったんだ。成功していい場所に到着できた時期に喧嘩が増えるっていうのは〈バンドあるある〉さ。
そういうときだったから、あのレコードは作るのが、ある意味大変だったんだよ。でもそんななかで一生懸命頑張ったし、個人的に好きな曲もたくさんある。バンドのコミュニケーションとヴァイブ、フィーリングがいちばん難しかった時期に出来たのがこのアルバムなんだ」
――2000年代も終わり、一時は大量にいたパンキッシュなダンス・バンドも少なくなっていた。そのなかで孤立無援だと感じることもありましたか? LCDサウンドシステムが翌年解散したことにもひとつの時代の終わりを感じました。
「孤立無援とまでは感じていなかったけど、これまでになかった新しい何かが音楽シーンに入ってきているのは察していた。俺たちもずっと人気者でいれるわけじゃないんだ、っていうのは感じていたよ。それもバンドの状態が難しくなっていたひとつの理由かもしれないしね」
『Thr!!!er』(2013年)

――5作目の『Thr!!!er』はスプーンのジム・イーノがプロデューサーとして入りました。
「92点。『Myth Takes』のときと同じ。イマイチなレコードのあとには、そのぶんハングリーになっていいレコードが出来上がるってわけ。〈どうやってよりいいものを作ろうか〉っていうのをバンドで追求しあったんだ。前回のようなミスをふたたび犯すわけにはいかない。そして、自分たちがコネクションを感じられるプロデューサーを起用しようとなって、ジム・イーノに頼んだんだ。あれは俺たちにとってすごくいい決断だった。あのレコードでは、彼のおかげで本当に多くを学んだんだ。発見の連続だったね」
――結果的に1曲あたりの長さも短めで、コンパクトななかにアイデアが詰まったポップ・アルバムという印象です。
「パトリック(・フォード、共同プロデューサー)とも初めて作業してそれもすごく良かったし、キーボードにラファエル(・コーエン)も入った。ラファエルはたくさんのアイデアを俺たちと共有して繋ぎ合わせることができる。それが最高だったんだ。このアルバムで、バンドのコミュニケーションが段々とよくなっていったんだよ」
『As If』(2015年)

――6作目の『As If』も引き続きスプーンのジム・イーノがプロデュース。
「86点かな。点数は下がったけどあのレコードは好き。ジムとは何曲か一緒に作業したけど、彼がスプーンで忙しくて全体的にはお世話になることができなかったんだ。さまざまな人たちとコラボしたのがこのレコードだけど、基本的には俺とパトリックとラファエルの3人で一日18時間くらい作業して出来上がったんだ。スタジオで笑いながら、楽しみながら出来上がったんだ。
個人的にはもっと高い点をあげてもいいと思えるレコードだな。“All U Writers”は俺のいちばんお気に入りの!!!ソングのひとつだしね。でもいくつかもっと上手くできたんじゃないかと思える部分があるから、総合的には86点」
――前作にもその片鱗はありましたが、『As If』以降は多数のゲスト・ヴォーカリストが参加するようになりました。そうした方向性にシフトしたねらいは?
「サウンドの幅を広げて、もっとユニークにしたかった。あと、何枚も同じヴォーカルのレコードを出していると自分たちも飽きちゃうんだよ。その弱みを逆に強みに変えようとしたんだ」
『Shake The Shudder』(2017年)

――いよいよ現在に近付いてきましたね。前作にあたる7作目『Shake The Shudder』はどうですか?
「うーん……90点。前よりも少し知識があったし、作っていてすごく楽しかったからね。サウンドがもっとタフになったのも良かった。『Myth Takes』にいい意味でふたたび近づいたアルバムだったと思うね。汗臭いというか、そういうサウンド。個人的には、『Myth Takes』と『Thr!!!er』の間みたいなアルバムだな」
――なるほど。!!!も近作ではダンス・ミュージック的な側面を強めてきていますが、このアルバムではムーディーマンやニコラ・クルズなどのストレンジなハウスがインスピレーション源になったそうですね。当時のあなたはそうしたサウンドのどんな面に魅力を感じていたのでしょうか?
「コンテンポラリーなクラブ・ミュージックなんだけど70年代のファンク、ディスコ・サウンドが混ざっているところだね。クラシックなソウルフルさが好きなんだ。俺たちは楽器の生演奏をするから、そういうサウンドに繋がりを感じるんだよ。70年代のソウルはバンドにとってオリジナルのインスピレーションで、コンテンポラリーなクラブ・ミュージックはバンドが向かっている未来だった。その両方を兼ね備えているのが特にムーディーマンだったんだ」
『Wallop』(2019年)

――ついにここまできました。新作『Wallop』については?
「これは100点! そりゃそうさ。作ったばかりなんだから(笑)。作り終えたばかりの作品がいちばん好きっていうのは自然だと思うね。これまでのレコードもそうだし。でも今回のレコードに関しては自信があるんだ。ここ2、3枚のレコードの評価を見ていて、だんだんどんなレスポンスが返ってくるかが読めるようになってきた。自分たちを前進させるのも上手くなってきたし、作品に何か強いポイントを持たせることもできるようになった。今回はいろいろなことに挑戦もしたんだけど、挑戦をしたぶん、反応も返ってくる。それをすでに感じてるんだ」
――どんな新しいことに挑戦したんですか?
「『Shake The Shudder』で、タフで汗臭いサウンドを作れることは証明できた。それをもっと上手く作って、かつ緩くした感じ。そうすることで、自分たちがこれまで入ったことのない領域に入れていたらいいなと思ってる。“Slow Motion”や“Serbia Drums”、“Couldn’t Have Known”みたいな曲は、俺たち自身にとってもユニークで新しい。俺自身、新作には興奮しているんだ」
――いまあげてくれた3曲しかり、今作にはUKガラージやダブステップ、グライムの要素もあって、同時代のUKダンス・ミュージックへのアプローチが印象的です。
「そうだね。2ステップとかガラージは特に聴いているかな。俺たちにとっては未来的だけど、70年代のディスコのようなクラシックな要素を含んでいるところが、さっき話したのと同じように魅力なんだ。エネルギーも大好きだしね」
――今回はトランプ政権や現在のアメリカ社会への怒り/苛立ちが起点になっているそうですね。この数年でアメリカは大きく変わったと思いますか?
「変わったとは思う。アメリカに住んでいたら、その変化を感じない人はいないんじゃないかな。すでに燃えていた炎にトランプがさらに薪を投げ込んでいる感じだね。そんななかで生活するのは本当に大変さ。でも俺たちはそれについて歌うことをメインにしたりはしていない。
俺たちは、いい作品、美しい作品をただ作りたいだけ。それにも対して誰かがインスピレーションを受けてくれたら最高さ。何か素晴らしいものを自分たちの音楽を通してもたらすことが出来たらそれでいいんだ。ネガティヴなものを提示するより、ポジティヴな何かをもたらすことの方が大切だからね」
――ここ日本でも経済格差の拡大やレイシズムの蔓延など、いまの社会のムードは明るいとは言えません。そうした時代においても、ダンス・ミュージックは希望になると信じていますか?
「ダンス・ミュージックはずっとアンダーグラウンドの核にあるものだと思う。人々がそこに集まって、ひとつになる。それが大事なことで、オンラインで人々が孤立してきている現代、ダンス・ミュージックを楽しむことで人々と一緒になるきっかけができると思うんだ。生身の人間と過ごすという経験ができる。ダンス・ミュージックが果たせる役目はたくさんあると思うよ。そのなかでも、コミュニティーを築き上げて人々をひとつにするというのは大きいんじゃないかな」
LIVE INFORMATION
!!! - Wallop Japan Tour -
2019年10月30日(水)京都METRO
開場/開演:19:00/20:00
前売り:6,500円(別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可
INFO:METRO 075-752-2787/info@metro.ne.jp /www.metro.ne.jp
2019年10月31日(木)大阪LIVE HOUSE ANIMA
開場/開演:18:00/19:00
前売り:6,500円(別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可
INFO:SMASH WEST 06-6535-5569/smash-jpn.com
2019年11月1日(金)東京・渋谷O-EAST
開場/開演:18:00/19:00
前売り:6,500円(別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可
主催:SHIBUYA TELEVISION
INFO:BEATINK 03-5768-1277/www.beatink.com






















