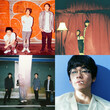EP『alaska』での衝撃デビューから3年。アカツカ率いるSouth Penguinが帰ってきた。去る8月にリリースされた念願の初アルバム『Y』では、爽やかなポップセンスはそのままに、愛が呼ぶほうへグルーヴとメロウネスを突き詰め、理想的なパワーアップを果たしている。今回もプロデュースは岡田拓郎で、サウンドの完成度は折り紙つき。その一方で、ラストを飾る“happy”が真逆の曲調であるように、“spk”という曲名が精神病院の看護人と患者のバンドに由来するように、やはり彼らは一筋縄ではいかない。どうやら、ここに辿り着くまでの道のりもハッピーとは程遠いものだったようだ。
当初は4人組だったSouth Penguinは、ある時期を境にアカツカ以外のメンバーが全員脱退。大きな挫折とともに、バンドは解散の危機に陥っていた。しかし『Y』では、過去にYogee New Wavesのサポートも務めたニカホヨシオ(キーボード)、折坂悠太(合奏)のメンバーでもある宮坂遼太郎(パーカッション)など実力派のサポート・メンバー5人が集結。さらにゲストとして、Dos Monosの荘子itがラップ、hikaru yamadaがサックスで助太刀し、大量の〈!〉と〈?〉を演奏に添えている。
何色にも染まらない東京インディーのアウトサイダーは、どん底からの復活劇をいかに成し遂げたのか。アカツカとニカホの共演がいち早く実現した2016年11月の〈Mikiki Pit〉を挟み、数年ぶりに対面したアカツカは、サングラスをかけたまま内情を明かしてくれた(彼は表情が読まれることを嫌う)。お笑い好きのアウトローだけに、ジョーク・毒舌・減らず口は相変わらず。しかし、フザけているはずの一言一句が、以前よりまっすぐ胸に届いたのは気のせいか。前回のインタヴューと今回で最後の質問を読み比べれば、彼の成長ぶりがわかってもらえるはずだ。さらに、Dos Monos、No Buses、篠田ミル(yahyel)を迎え、2019年11月12日(火)に東京・渋谷WWWで開催される『Y』リリース・パーティーについてもたっぷり語ってくれた。
〈美しさ〉は永遠のテーマ
――わりと最近まで、バンドの状態がヤバかったらしいじゃないですか。
「そうなんですよ。South Penguinを始めた2016年の夏、それこそMikikiに前回インタヴューしてもらった時点で、僕らはまだ一回もライヴをしたことがなかった。でも最初のEP『alaska』を出すタイミングで〈フジロック〉の〈ROOKIE A GO-GO〉への出演が決まって。初ライヴを〈フジロック〉にするのは怖かったので、無理やり1週間前にライヴを入れてもらったんです。そんな感じで、いろんなことを知らないままバンドがスタートしちゃった」
――ああ、そうでした。
「だから、話題性は多少あったけど、蓋を開けてみたら〈こんなのアマチュアじゃん〉となっちゃって。その後もいろんなライヴに誘ってもらったけど反応は微妙で、バンドの状態を整えられずオファーを断ることもありました。スタジオ作品は(プロデューサーの)岡田拓郎さんの手が加わっていたから、最初にしてはある程度のクオリティーだったかもしれないけど、どんどん自分たちのメッキが剥がれていったんです」
――態勢を整え直す余裕もなく、活動が上手く回らなくなってしまった。
「翌年に出したセカンドEP『house』は自信作だったのに、その頃には忘れられてしまったのか、まったく広まる気配がなかった。それだけでもショックなのに、メンバー脱退などいろんなことが重なり、活動もストップしてしまって。それが大学卒業のタイミングだったから、バンドをやめようと思ったんです。音楽は相変わらず好きでしたけど、周りへの不信感もあったし、メンバーも全員いなくなった。僕は一人で弾き語りするようなタイプでもないから、ここでやめても悔いはないと。メンバーを探したりもしたけど上手くいかず、バンドはシューッと終わっていきました……(顔をしかめる)」
――それは辛かったでしょう。
「日本で音楽をやろうという気持ちが完全になくなりましたね。その時期は、音楽やってる友達とつるむのもやめました。就職して親孝行しようと。そう決めたあともセカンドEPの失敗を引きずってたんですけど、そんなあるときNHKの『スタジオパークからこんにちは』に吉岡里帆さんが出ていて。出演していたドラマ『朗読屋』の宣伝で、中原中也の『帰郷』っていう詩を朗読していたんですけど、読み終えた時に涙を流されていたんですよね」
――ええ、なんでまた?
「詩の世界に入り込みすぎたんですかね。その姿に、僕もすごく感動してしまって。なんでそんなにピュアな気持ちで作品に触れることができるんだろうって。もともと吉岡さんは好きだったけど、どういう人なのかもっと知りたくなって。いろんなインタヴューを読み込むうち、めっちゃストイックな人だとわかったんです。国民的な人気女優なのに、表現というものに対して驕りがない。彼女のInstagramを見ると、いろんなライヴに足を運んだりもしていて……」
――文化的だし探究心がある。
「劇場に足を運んだり、ライヴを観たり、美術展に行ったりとか、あらゆる方向から刺激を受けて自らの表現を充実させよう、という吉岡さんの姿勢を尊敬する様になりました。僕は周りの人間がやってる音楽も聴いてなかったし、好きなバンドが来日しても行かなかったりして。かと言って、他に詳しい分野があるわけでもない。自分は何をしてたんだろうって。最初に話したように、美術館に足を運ぶようになったのもそこからですね。自分の知らない世界をもっと知りたくなったんです」
――そこまで影響されまくってたとは。
「表現や芸術に対してまっすぐな人は他にもいるんでしょうけど、僕にとってはいちばんダイレクトでしたね。その姿勢がめちゃくちゃ美しいなと。あれほどのスターがこんなに努力している……僕、頑張ってる人が好きなんですよ。箱根駅伝も好きで。でも、自分は頑張っていたのかなって。いろんな人に助けてもらって、作品も出すことができたのに、あんなに好きだった音楽をやめようとしている。意味なく友達もシャットアウトしてしまって……これはもう親孝行じゃないだろうと気が付いて。そこからガラッと考え方が変わったんですよ。ライヴにも足を運ぶようになったし、いろんなものに触れようって気持ちがものすごく強くなった。その大きなきっかけが吉岡里帆さんだったんです」
――アカツカくんの人生すら変えてしまったんですね。なんだか僕も感動してきました。
「本当にそう、ターニングポイントだったんですよ。今回のアルバム『Y』は〈美しさ〉がテーマで、それはいま言ったように、吉岡さんの表現に対する姿勢が美しいと思ったからなんですけど。これは今回のアルバムだけじゃなくて、この先も僕の表現活動に繋がっていくテーマになってくると思いますね。ここは太字で強調してほしいです」
――タイトル『Y』の由来は?
「ポップ・グループのファースト(79年の『Y(最後の警告)』)が元ネタです。あれもすごく奇跡的な、美しい作品だと思ってて。音楽的なバックグラウンドとかだけじゃなくて、思想を持った悪ガキたちが奇跡的に生み出したものだなって」
――前回の、3年前のインタヴューで、トーキング・ヘッズみたいな〈ニューウェイヴでファンキーで、ちょっと踊れるようなものが好み〉と言ってましたけど、相変わらずその辺の音楽が好きなんですね。
「その辺はZAZEN BOYSがきっかけですね。高校時代に初めてギターを買うとき、向井(秀徳)さんが使ってたギターと同じやつにしたくらい好きで。彼らのインタヴューを読んでたら話に出てきて、そこからYouTubeの関連動画で掘り下げていきました」
――そういう音楽の趣味は、初期のバンド・メンバーとは共有できてたんですか。
「いや、最初のメンバーとはまったく共有できてなかったですね」
――いまだから言えますが、あの頃のメンバーはかなりテンションの開きがある感じもしていました。
「そうですね。僕も未熟だし、メンバーもそれに対してあまり理解を示してこなかった。セカンドEPも最初の4人で録ったんですけど、ほとんど僕と岡田さんのディレクションで作ったので。もはやメンバーである意味もないし、彼らも仕事が忙しかったりしたので、じゃあやめようかって。僕のイメージではそのあとすぐ、鉄壁のメンバーを揃えて再スタートするつもりだったんですが……」