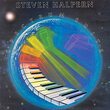ニューエイジ思想とニューエイジ・ミュージックの不遇
おおよそ70年代半ばに始まり、80年代に隆盛を誇り、90年代に徹底的に商業化された〈ニューエイジ〉なる音楽ジャンル/スタイル。それが音楽の世界で肯定的に捉えられるようになったのは、2010年代に入ってからだと思う。もちろん、〈そんなことはない!〉という意見もあるだろうし、2000年代からすでに再評価が始まっていたこともまたたしかだ。しかし、少なくとも2010年代まではリヴァイヴァルのような大きな波になることはなく、ごく一部の好事家の間で聴かれているものにすぎなかっただろう。レコードやCDの市場価値は無いに等しく、それ以上に、シリアスに聴かれるべき音楽とは考えられていなかったのだ。
そもそもニューエイジ・ミュージックは、〈癒し〉や〈リラクゼーション〉といった効能と実用性を持つ機能的な音楽であり、瞑想やヨガ、自己啓発のBGMとして作られているものがほとんど。〈音楽の外〉にあるコンテクストや思想抜きには成立しないのであって、それゆえに〈音楽のための音楽(music for music’s sake)〉ではない。だから、アートではない――。そういった評価は一般的なものだったと思うし、疑似宗教にも接点を持つニューエイジのスピリチュアルな側面を危険視する向きもあっただろう。
ヴェイパーウェイヴ、環境音楽、バレアリック……ニューエイジの再評価
そんな不遇をかこってきたニューエイジの音楽的な価値、アートとしての価値が、近年再評価されている。ある時期まで〈ダサい〉と思われてきたデジタル・シンセサイザーの音色や独特の音像は一転して〈アリ〉になり、電子音楽の一ジャンルとして歴史的に位置づけられつつあるのだ(私自身の感覚や評価も、ずいぶん変わった実感がある)。
その再評価は、ニューエイジの背景や思想とは切り離されたところで、純粋に電子音楽として聴かれるようになったことに起因している、と私は思う(ただ、これはなかなか音楽の世界で言われないことだが、そのリヴァイヴァルが、ある側面では新たなスピリチュアリズムのブームと結びついていることは、ここで指摘しておいたほうがいいだろう)。
そのようにしてニューエイジが再評価された背景には、さまざまな文脈がある。ニューエイジを〈ネタ〉として消費したヴェイパーウェイヴの登場。近接ジャンルであるアンビエントや日本の〈環境音楽〉(米レーベル、ライト・イン・ジ・アティックによる2019年のコンピレーション・アルバム『Kankyō Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990』がグラミー賞にノミネートされたことも記憶に新しい)の再評価。あるいはクラブ・カルチャーにおける〈バレアリック〉という視点、などなど。