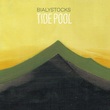2人体制の利点は自由度の高さと曲主体のアレンジ
――本作はファーストアルバム『ビアリストックス』から約1年ぶりの作品となりますが、制作はどのように始まりましたか?
甫木元「前作のアルバムが一つの区切りとなっているというよりも、今回までずっと地続きという感覚です。自分たちは締め切りを設けないと、なかなか動かないので(笑)。でも普段から継続的に作った曲は共有しているから、〈そろそろ次の作品を作ろう〉という流れで始まりました」
菊池「なので今回も〈何かテーマを設けて作っていこう〉ということもなく、デモから選んだ5曲を坦々と作っていきましたね」
――特に区切りになるものという感覚はないとのことですが、改めて前作はどのような位置づけの作品だと捉えていますか?
甫木元「集まった4人でどういう音楽ができるのか、俯瞰してみるために作った作品でしょうか。一つの方向性を決めることもなかったので、〈このメンバーでできた音楽〉という意味でタイトルをバンド名にしたというのもあります」
――前作はギタリストとドラマーを加えた4人編成でしたが、今回からクレジットされているのは甫木元さん、菊池さんのみですね。お2人になったことによる変化はありましたか?
甫木元「最初から基本的に菊池が編曲の方向性を決めてくれていたので、そういう意味では変わらないのですが、2人になったことで自由度は上がった気がします。前はバンドが主体だったのが、今回はこの5曲が主体というか」
菊池「前作では4人それぞれに花を持たせる瞬間を設ける意識をしていたし、全員の意見をまとめる必要もありました。でも今回はそれぞれの曲をどのようによくするかだけを考えればいいので、目立たない楽器があってもお構いなし。より主体的にアレンジができました」
人間を肯定するミュージカル映画からの影響
――1曲目の“Over Now”から、すごく愛おしい情景が浮かび上がってきます。歌い出しの〈何回目の三振だって 後悔から邁進成功〉からしてダメダメ感があるけど、光は消えずしぶとく灯っているような。
甫木元「“Over Now”は菊池がピアノの弾き語りで作ったもので、歌詞も彼が作った言葉に僕が補足して仕上げたものです。だから〈三振〉という言葉もデモ段階から指定されていました。ミュージカル映画に出てくるような、陽気だけどうだつのあがらないおじさんの哀愁みたいなものがイメージです」
――意外なワードですが、そのミュージカル映画とは具体的な作品があるんですか?
菊池「『くたばれ!ヤンキース』(1955年)というブロードウェイミュージカルが大好きで。1958年に映画化もされているのですが、この曲を作っている時にその映像を繰り返し観ていました。主人公の情けないおじさんが野球チームに入ってしまうんですが、そこで歌われる曲もすごくよくって。(甫木元には)その雰囲気を歌詞に反映してもらいました」
甫木元「そこに出てくるキャラクターには哀愁があるんですけど、悲観的ではないんですよね。特定の感情を吐露したものだったり、聴き手の背中を押すものだったり、歌に乗せやすい言葉はたくさんあると思います。でもそれだけじゃなくって、悲しみを背負いながらも、舞台で煌びやかに演じている道化のような人間を描こうとしました。
“All Too Soon”も菊池がハマっているミュージカルの映像を一緒に観て作った曲で」
――“All Too Soon”はお2人とも作詞作曲にクレジットされています。こちらは何を観たのですか?
菊池「これは『いつも上天気』(1955年)というMGMの黄金期を過ぎて発表されたミュージカル映画ですね。ジーン・ケリーがローラースケートを履いて、街中でタップダンスするシーンが有名で、甫木元と共有して一緒に観ていました」
――こちらもさまよいながらも夢の続きを見ようとする刹那的な享楽を歌詞やサウンドから感じます。それらのミュージカル映画は主にどういう部分を参考にしているのでしょうか?
甫木元「チャップリンの有名な言葉として〈人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ〉というものがあります。音楽を作る考え方の大枠としても面白い言葉だなと思っていて、悲観的な物語も歌や映画であれば、雨に打たれている中でも踊ることができる。今のは極端な話ですが、場面の切り取り方や、人間を肯定するやり方の一つのイメージとして参考にできるんじゃないかなと。
あと自分は父親がミュージカルの演出家だったので、小さい頃から舞台や映画はよく観ていました。だから、ミュージカルや映画を通じて、僕と菊池の間で共通する感覚の一つとして気配や雰囲気を共有しているんだと思います」