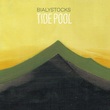2023年7月8日、Bialystocksにとって2度目のツアーである〈Bialystocks 2nd Tour 2023〉のファイナルが大阪・梅田CLUB QUATTROで開催された。同ツアーは9月10日(日)に東京・六本木のEX THEATER ROPPONGIでの追加公演(早くもソールドアウト)が控えているが、その前に一旦の区切りがつけられたのが大阪公演だ。2022年11月のメジャーデビューアルバム『Quicksand』のリリース以降、さらに躍進してきた2人が、歩みを止めずにバンドとして新たなモードを見せつけた同公演。彼らの進化を目撃してきた音楽ライターの峯大貴がその模様を伝える。 *Mikiki編集部
拡張し続ける期待の大きさとそれに応えるスピード感
1~2月にかけて東名阪をまわる初ツアーを走り切ったかと思いきや、その最終日である恵比寿LIQUIDROOMの公演で早くも2回目のツアー開催を発表。福岡、北海道を加えて全5公演に規模を拡大、さらには9月10日に東京・EX THEATER ROPPONGIでの追加公演の開催も早々にアナウンスされた。彼らに向けられた期待の大きさも、そこに応えるスピード感も拡張を続けるばかりである。
MikikiでBialystocksの節目となるステージの模様を記すのも本稿で5回目となるが、せっかくここまで追いかけてきたのだからと筆者も普段の行動範囲を飛び出し、ツアー最終日の大阪・梅田CLUB QUATTROまで足を運ぶことにした。今回、甫木元空(ボーカル/ギター)と菊池剛(キーボード)の2人に加わるサポートミュージシャンは、朝田拓馬(ギター)、Yuki Atori(ベース)、小山田和正(ドラム)、秋谷弘大(シンセサイザー/グロッケン/ギター)の6人編成で全公演共通。ぜひこのツアーを通した手ごたえや経験が反映されたファイナルをレポートしておきたかったのだ。

変化を渇望し、オリジナルから解き放たれる楽曲たち
ソールドアウトの梅田CLUB QUATTRO。開演ギリギリまで途切れない入場列に、スタッフは必死に前へ詰めるようフロアの観客に促している。会場BGMで流れるスティーリー・ダン“Reelin’ In The Years”、サイモン&ガーファンクル“My Little Town”、ホイットニー・ヒューストン“Greatest Love Of All”などの選曲は甫木元と菊池によるものかと想像を巡らせていると、SEに切り替わりメンバーがステージに登場した。満員の会場から拍手が起きるや否や、甫木元が〈グランパーでどっかめざして/僕たちは進む……〉と歌い出し、そこに菊池のピアノだけが帯同する。確かに“Nevermore”に違いない。しかし冒頭のフレーズ〈I don’t wanna love you, my baby〉だけで会場のボルテージが数段上がる屈指のキラーチューンの趣を、痛快に裏切るような静かな幕開けである。そこからドラムのフィルインで徐々にドライブをかけていく新たな演出が施されていた。


今、振り返って考えると、1曲目からこの日にかける彼らの思いが色濃く滲み出ていたと言える。端的に結論付けてしまうと〈今まで生み出してきた楽曲たちはあくまでその時点での姿に過ぎず、さらなる変化を渇望して各々が声を上げている〉と。そう感じたのは中盤に披露された“差し色”だ。アウトロにベースソロが入ること自体は原曲同様の構成ではあるが、他の演奏が終わってもなお続く3分半ほどのAtoriの独壇場。フリーキーに蠢くフュージョン調のフレーズは温かさともの悲しさが同居するこの曲の余韻に、また新たな差し色を加えていた。


そんなAtoriのベースが消え入るのと交差して、少しスウィングしたアコースティックギターのストロークが聴こえてくる。流麗なピアノが主体となって淡々と進んでいく原曲の演奏とはまるで彩りが違うのが、“朝靄”だ。テンポは心地よくとも、それが独特の不穏さを醸している。そしてなだれ込むように“All Too Soon”へと移行すると、怒涛のソロパートの応酬が挟まる。菊池はジャズピアニストとしての側面を全開にして、朝田のテクニカルなギターと演奏の主導権をパスし合っている。次いで小山田はリズムキープからも解き放たれたようなドラミングを放つなど、曲としての枠組みを超えるギリギリを狙うようなインプロビゼーションさながらのシーンであった。