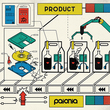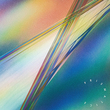〈ジャズを勉強してきたんだな〉というより〈ジャズが好きなんだろうな〉
――ここから改めてムーンチャイルドの面白さを話していきたいのですが、サウンドの個性の前に、まず男性2人女性1人という編成が見え方としてもキャッチーですよね。
「そうですね。ドリカム的な(笑)」
――そうそう、初期DREAMS COME TRUE編成。ほかにも初期のEvery Little Thingなど、日本にはこの編成のグループがいくつかありましたけど、大前提としてこの編成は各メンバーの性格のよさとか協調性がないと成り立たないと思うんです。
「ムーンチャイルドは3人とも穏やかそうだし、それが音楽にも表れていますよね。SNSに3人が管楽器を吹いている様子があがっているのを見ると、各々がすごく楽器を好きなんだなって感じるし、3人の穏やかさも同時に伝わってくる。だからこそ安心して聴けるというところもあるかもしれないですね」
――音楽性は、ざっくり言うなら現代R&B。特にネオソウルと呼ばれる種類のものであり、現代ジャズの要素も含んでいる。とはいえ尖ったビートやリズムで刺激を与えるものではなく、抑制されていて、終始メロウ。アンバー・ナヴランの優しい声の感触も手伝って、ポップスとしての親しみやすさもある。そうした全体の柔らかな感触はTENDREの表現にすごく通じるものがあるように思うのですが、どうですか?
「それぞれがいろんな音楽を好きで聴いていて、その上で3人が〈いいな〉と感じるスイートスポットを探しつつ一個一個具現化していったら、結果ムーンチャイルドの音楽になったという感じなんじゃないかと思いますね。自分たちの落ち着ける温度感を探しながら、例えばマイクの距離感とかによってナチュラルな部分を出そうとしている印象がある。そのへんが自分と共通しているところのように感じます。自分もジャンルとして考えるというよりかは、曲を作りながらムードを確かめる。それをカテゴリーとして置いたときにネオソウルでありポップスでもありという複合的なものになっているという感じなので、そこが近いかなとは思います」
――ムーンチャイルドの3人は南カリフォルニア大学でジャズを専攻していました。河原さんはお父様がバークリー音楽大学に通われていたウッドベース奏者で、お母様がジャズボーカリスト。5歳の頃からジャズピアニストにピアノを習っていたとのことで、ジャズがベースにあるところも共通しているわけですが、彼らの音楽を聴いていて〈ジャズを学んだ人たちの表現だな〉という印象は受けますか?
「〈ジャズを勉強してきたんだな〉というよりは、〈ジャズが好きなんだろうな〉という印象ですね。それはコードワークってことだったり、テンションノートの使い方だったり、要するにロックには通じていない部分がそこにあるということ。ジャズの場合、ライブでも決まった曲を決まったフレーズのみで構築するよりかは、その場のアイデアでどんどん変化させながら新しい発見をするところがあって、それがジャズの醍醐味でもある。そういう部分がムーンチャイルドにあるのは感じますね」
――ムーンチャイルドは3人とも複数の楽器を使い分けますが、3人とも管楽器奏者であり、しかも管楽器を特別な楽器として扱っていない印象があります。曲のなかであからさまに管楽器の音を目立たせるのではなく、ほかの楽器や声と同等に扱っている。河原さんもトランペットを吹きますが、そうした用い方についてはどう感じますか?
「自分が紹介されるときとかによく〈マルチプレイヤーの〉という枕詞がついてきて、まあそう言っていただけるのはありがたいんですけど、自分から〈マルチプレイヤーです〉とは言わない。ムーンチャイルドのメンバーも各々に自分のセクションがありながらも、曲をどういうふうに盛り上げるのか、どういうアプローチをしたら面白いのか、その純粋な探求のなかに楽器があるという感じだと思うんです。〈この空間にトランペットがあったらいいよね〉といったふうに、アイデアが広がるから自然とその楽器を選んでいるだけなんでしょう。僕もそういう使い方なので、彼らと話したら気が合うんじゃないかなと思います」
――鍵盤楽器のチョイスの仕方や使い方に関してはどう思いますか?
「ガッとアタックの強いピアノを弾くことはなくて、基本的にはエレピサウンドとかを敷いていくイメージがありますね。音を敷いていく。ボーカルに寄り添った音色を大事にする。なかにはさっき言った“Run Away”のようにシンセの音がほかの曲より際立っている曲もあって、あれはアナログシンセでしょうけど、そのように一概にピアノだけとかエレピだけとかではない。箱庭音楽を作ることとは逆で、広げていくためのシンセの使い方をしているように感じます。音数が少ない分、そのへんが際立つんですよね」
――少ない音数でクールに聴かせながら、温かみが必ずあるというのも特徴ですよね。
「温かみを基本として持たせつつ、楽器本来の持つおいしい音色を差し込んでくる。そこは上手いですよね。足し算ではなく、引き算が上手い。日本人に好まれそうな音楽だなとも思います」
ビートだけで白米を食えますよっていうぐらいの気持ちよさ
――確かに。アンバーのボーカルに関してはどうですか? USの典型的なR&Bシンガーのような押しの強さはなく、それこそ日本人に好まれそうな柔らかな歌声ですよね。
「ブレス要素が多いですよね。マイクに近い距離で歌っているんじゃないかと思います。耳元で囁くのに近いというか。たぶんアンバーは喋り声からしていい声なんでしょうね。カラダに沁み込みやすい成分が声にある。だからどの曲を聴いても安心感が得られるんだと思います。曲のなかでレンジの変化はありますけど、ボーカル自体はずっと同じところにいるような印象があるので、そこはやっぱり男性メンバーの2人がいかにアンバーのボーカルを立たせるサウンドメイクにこだわっているかということの表れなんでしょう。3人のチームワークのよさが、ボーカルからだけでもわかるという」
――あとアンバーって、MVでもライブでも、いつもにこやかに歌っていますよね。
「ほんとにそうですね。NPRの〈Tiny Desk Concert〉を観ても、すごくリラックスしていて自然体。ベーシックにあるマインドが自然体なんでしょうね」
――彼らの曲の構造やサウンドデザインに関しては、どんなふうに感じますか?
「ディテールにものすごくこだわって作っているのがわかります。曲作りで僕が初めの頃に意識していたのは、曲の頭と終わりをどれだけ美しくできるかということ。例えば頭からキックの音を鳴らすとしたら、それにはどういう意味があるのか、力強さの表現なのか寂しさを表現したいのか、それによって情景の描き方が変わってくる。ムーンチャイルドはディテールにすごくこだわっているから、始まりから宇宙的な情景だったり、ジャケットに表れているような不可思議な世界だったりが見えてくるんです。
それって音の配置の仕方が絶妙だからなんですよ。こんなところでこんな音が鳴っているんだという発見も多い。ビートメイクではキックとスネアのリム、その一貫した気持ちよさを追求しているでしょうし。素材をちゃんと磨いている感じがしますね。ビートだけでも白米を食えますよっていうぐらいの気持ちよさがあって(笑)、その上にこんな鍵盤と歌が乗っていたら、そりゃあ美味しいでしょうっていう。でも決していろいろ乗せすぎたりはしないし、調味料をかけることもない。塩味で召し上がってくださいっていう、そんな感じがしますね」