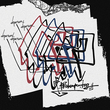いつでも真ん中にあるメロディー、作品が伝える変化への共感
──自分たちとの共通点はどう感じます?
福富「メロディーというものがずっと真ん中にあるのは共通してるかもしれない」
畳野「私もそう思います」
福富「打ち込みっぽいこともやるけど、ちゃんと歌が前に出てきて、声と歌を大事にしてるし、そのバランスでどう面白くアレンジするかを考えてる。そういう曲をいっぱい作ってることに親近感があります」
畳野「私は、彼らのアルバム3枚での変わり方にシンパシーがあります。アルバムごとに、変わらない部分としてはモリーのボーカルの良さがあるんですけど、そのときメンバーがハマってることが彼らの変化を通じてわかりやすく伝わる。バンドのその時点でのムードがわかる感じは、ホムカミの作品にもあるかな」
福富「素材は80年代っぽかったり、今っぽかったりするんですけど、それらを自分たちでごちゃ混ぜにしながら、歴史を前に進めようとしてる感じ。同年代で音楽をやってる身としては、そこはいいなと思えるところです」

短い曲に詰め込まれた多彩な要素
──では、『Blue Rev』で好きな曲は?
福富「僕は“Belinda Says”がいちばん好き」
畳野「あ、私も同じ。めちゃいい、って思いました」
福富「“Tom Verlaine”もそうなんですけど、イントロのホワーンとしたシンセが、この曲では映画の『摩天楼はバラ色に』(87年)みたいな80年代の感じなんです。僕らが生まれる前の映画だけど、懐かしいと思える。で、曲の最後に転調してびっくりさせられる」
畳野「曲を構成する要素が多すぎてすごいよね。彼らは、前から構成は単純じゃない曲が多いんです。だけど、今回は1曲が短いのに、そのなかでさらにいろんなことが起きてる」
福富「でも、急にめちゃくちゃ変わったというより、もともとバンドが持ってた素質みたいなものが、たぶん、ショーン・エヴェレットがプロデュースしたことで広がったり強くなったりしてるんだと思う」
畳野「シンセの使い方も変わったよね。前はコード楽器だったけど、今回はフレーズも弾いてたりするし」
福富「だから、今までよりニューウェーブっぽい感じがするのかな。それこそ僕らも高校生や大学生の頃にニューウェーブやポストパンクのリバイバルがあって、そこからさかのぼって聴く流れがあったから、もしかしたら同世代のオールウェイズのメンバーにもそういう流れがあったのかもしれない。あのときのポストパンクリバイバルを今の自分たちで更新する、みたいな」

同時代的で同世代的、今だからこその新しさ
畳野「セカンドを出した後に、ドラムがシェリダン(・ライリー)に変わったんですけど、彼女がめちゃめちゃ良くて。ライブでは超パワフルなんですよ。パンキッシュなドラマーになってるから、それが曲作りにも影響してそうな気がする」
福富「ニュー・オーダーで言ったら『Brotherhood』(86年)の感じかな。ちょっとパンクっぽくて踊れるテンションの曲が入ってる」
──来日したら対バンしてほしいですね。
畳野「私はワンマンでオールウェイズを観たいです(笑)」
福富「セカンドのときはライブハウスが小さく感じたんですけど、この新作については、ここからの曲だけの演奏をライブハウスで観たいですね。そういう面白さがある。パンクスたちが輪になって踊ってるあの絵を見たいな。そこはドラマーが変わって、ビートが変わったのも影響してるかもしれない」

──ニューウェーブ、ネオアコからシューゲイザーも含めて、本当に広い意味でのポストパンク的な匂いを継承してる新作だというのはわかる気はします。
福富「そういう意味では僕らと共通してるんやろな」
畳野「好きなものがルーツというか、軸になっているということだよね」
福富「それに、今の10代が抱えてるメンタルヘルスの問題みたいなところに、過去のパンクが一周回って届いてるというのはある気がする。
あと、曲は宅録的に家で作られた感じがするけど、作品が向いてるところは広くなってる。それはこの時代だからこその新しいタームな感じがします。オールウェイズもそういうところを経てきてる気がする。だから、同時代的でもあるし、同世代的でもある」