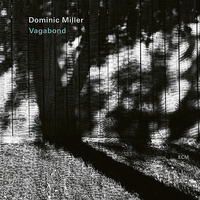スティングの側近ギタリスト、審美眼に富むECM3作目を発表
すらりとしていて、格好いい。その様に触れると、なるほどこの人はジャズ畑というより、ロック畑の人物であると思わされようか。現在ECMからリーダー作を出しているギター奏者のドミニク・ミラーだが、彼は1990年以降スティングのバンドに在籍し、その懐刀的な存在となっている。そして、その一方で詩的なアコースティック・ギターを用いたリーダー作を随時発表してきた。ECMとの関係は、同社主プロデューサーであるマンフレート・アイヒャーから会いたいと連絡されたことで始まった。
「もちろん僕のコレクションのなかにはキース・ジャレットをはじめ、パット・メセニーやラルフ・タウナー、エグベルト・ジスモンチをはじめECM作がいろいろあった。だから、最初(オスロのレインボウ・スタジオで)レコーディングしたときは、彼らと同じスタジオで、同じエンジニアやプロデューサーのもと――きっとマイクも同じだったんじゃないかな――録音ができるなんて、ちょっと非現実的な夢が叶ったっていう感じだった」
彼はアコースティック・ギター演奏が全面に出た『サイレント・ライト』 (2017年)、バンドネオン奏者も編成に加えた『アブサン』(2019年)に続く、『ヴァガボンド』をリリースする。〈放浪者〉という表題は、アルゼンチン生まれながら米バークリー音大にも通い、英国に住みつつワールドワイドに活動している自身のことを語っているのかと思ってしまうところだが。
「確かに僕は旅するミュージシャンではあるし、そう思われるのは当然だと思う。もともとは詩人のジョン・メイスフィールド(1878~1967年、英国人)が書いた詩のタイトルなんだ。僕の父が亡くなったんだけど、彼の好きな詩だったので、父へのトリビュート的な意味でそれをアルバム表題にした。実際7曲目“ミ・ヴィエホ”は英語にすると〈マイ・オールド・マン〉という意味で、〈オールド・マン〉というのは老人ではなく〈父親〉という意味なんだ」
新作は、カルテットによる録音。ピアノのヤコブ・カールソンはスウェーデン人、ベーシストのニコラ・フィズマンはベルギー人、ドラマーのジヴ・ラヴィッツはイスラエル人と、参加者の属性は散る。
「アルバムごとに僕は違うことをやっているけど、前作と共通する奏者はニコラだけ。彼の場合は、そのポップス的なタイトさやタイミングが導く規律のようなものがすごく好きで、そんな部分とジャズ・ミュージシャンが一緒になった際に面白いバランスが生まれるんだ。ジヴは自由にビートの上を踊るように叩くわけで、それはポップスの規律とのいい意味での対立みたいなものを生じさせる。そして、ヤコブはクラシックの要素を持っており、その演奏がさらに加わることで、まったく個性が異なる役者が一つの舞台で演じているかのようになる。そうした場に曲を書いている僕が監督のような形でいて、その舞台のデザインをしてくれるのがECMであり、マンフ レートなんだ」
そして、彼は『ヴァガボンド』を以下のようにも説明する。
「ECMから出したアルバムのなかで言うと、一番シンプルで一番直接的かもしれない。メロディとかコードといった部分で一番曖昧なところがない。だけど、シンプルなものこそ一番難しいわけで、ぼくは生涯そういうことを突き詰めようとしているんだ」
ジャズは〈点〉でつないで描くような表現でずっと演奏を追っていかないと、その真価はちゃんと伝わらない。だが、ポップスは〈面〉で描く音楽なので、パッと聞いても良いものはすぐに分かる。彼の表現を聞いて合点がいくのは、かような〈点〉と〈面〉の両方に留意していることだ。
「その見解はクール、すごくうれしいな。僕はポップスとかロックのシェイプとジャズの自由さ、その両方が好きだからね。究極の僕の願いは、それを自然に生まれた音楽だと聞き手に聞いてもらいたということ。だけど、その水面下では様々なストラクチャーがせめぎ合い、そこには言葉を超えた危なさや神秘性が付随している」
ドミニク・ミラー(Dominic Miller)
1960年3月21日、アルゼンチン・ブエノスアイレス生まれ。バークレー音楽学校、ロンドン・ギルドホールスクールでクラシックを学ぶ。セバスチャン・タパジョスに師事。1991年にスティングのアルバム『ソウル・ケージ』に参加し、その後のスティングのツアー、レコーディングには欠かせないギタリストとなる。その他、ティナ・ターナー、ブライアン・アダムス、パヴァロッティ、レナード・コーエン、ユッスーン・ドゥール、ローナン・キーティン、バックストリート・ボーイズなど多くのアーティストとの共演、レコーディングなど活動は多岐に渡る。