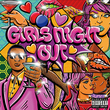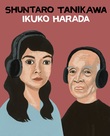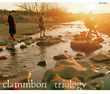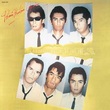蠢きや気配を音にしてみたい
そんなふうに個別で制作されてきた楽曲群をアルバムとしてまとめる磁場となった一曲がある。それが、本作の終着点である谷川俊太郎との共作曲“いまここ”だ。
「2021年、rei harakamiさんが亡くなってから10年の節目に、harakamiさんが音楽を担当したプラネタリウム〈暗やみの色〉がリヴァイヴァル上映されて、そのときのトークショーで谷川さんと久しぶりにご一緒できたんです。宇宙、言葉、音、いろんな科学のこと、あと、小さいときに谷川さんの本で言葉のリズムや語感のおもしろさを教えてもらったっていう、音楽を好きになるより前の、自分にとってのルーツで、とそういう話をさせてもらって。それで後日、〈一緒に歌をつくれたら〉とお手紙を書かせてもらいました。そこからほどなく、この詩が届いて、その速さに驚いたのですが、トークショーでお話ししたこと、谷川さん自身の死生観、〈生きる〉っていうことがすべて含まれているように感じて、震えました。その後はこの詩を肌身離さず持ち歩いて、歌やサウンドを考える日々が続いたんですけど。だんだんと、〈原田郁子〉とか〈クラムボン〉〈日本〉っていうところも超えて、届けたいな、伝えなくてはいけないなって思ったんです」。
谷川の呼吸の音、心臓の鼓動に耳を傾けているうちに意識が宇宙へと飛ばされるような、深遠な音世界が広がる11分半の大曲“いまここ”。ピアノと電子音が織り成す組曲の如きアンビエンスのなかで0歳から91歳までの声が飛び交い、谷川の朗読が絶対的な存在感で響き渡る。ラストに置かれたrei harakami“intro”のサンプリング然り、多くの音が重ねられていった先に浮かび上がるのは、森羅万象の生命力、その息吹に触れるような壮大な物語だ。
「一面的ではなくレイヤーになっているっていうか、そこに何層もあったり、ゆっくり変化していったりっていうことが表現できたらいいなっていうのと、あと、この詩からは躍動感というか、例えば細胞とか微生物も、生きて死んで、常に蠢いているっていう感じを受け取ったので、そういうミクロな世界や、人間以外の生き物の気配を音にしてみたいっていうのはありました。そうやって作っていくなかで、やっぱりharakamiさんの音が最後に聴こえてきたらいいなって。プラネタリウムが開催されていた当時、harakamiさんと谷川さんがお会いしたことはなかったそうなので、音楽のなかで二人が出会えたらいいなって思ったんですよね。そして、rings(harakamiの音源リイシューを手掛けるレーベル)やご家族の方々にご理解いただいて、サンプリングという形でharakamiさんの音を使わせてもらえることになりました」。
生命の数だけ無数に存在する〈いま、ここ〉。あるいは、無数の〈いま、ここ〉の集合体であるこの世界。この曲を初演奏した際のエピソードもまた、その本質を示しているようで興味深い。
「このあいだ、〈CIRCLE〉っていう福岡のフェスで初めて“いまここ”を演奏したんですけど、〈いま〉と発音したり、〈ここ〉って歌った瞬間に、その場の空気がギュッとなる。実感するんですよね。自分もですけど、恐らく聴いてくださってる皆さんも、一人一人。ライヴっていう場においては、さらに〈いま〉だけの〈ここ〉っていう感覚も広がっていく。そっかぁ、って、言葉ってすごいなぁ、って。これからライヴでどうなっていくんだろうって、楽しみですね」。
原田郁子のソロ作。
左から、2004年作『ピアノ』、2008年作『気配と余韻』『ケモノと魔法』『銀河』(すべてコロムビア)