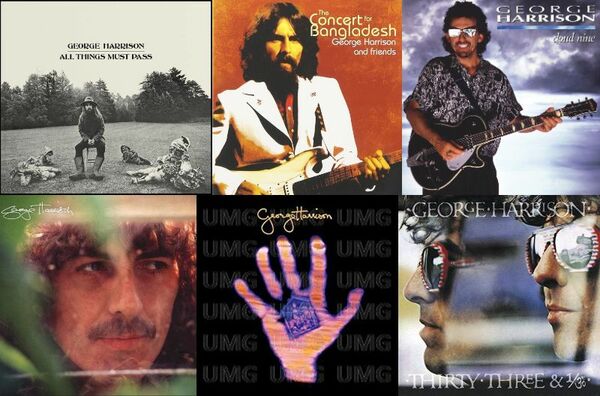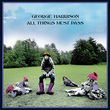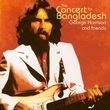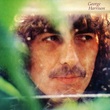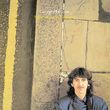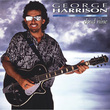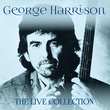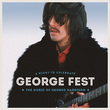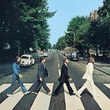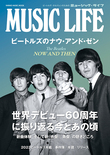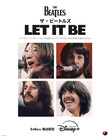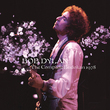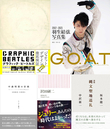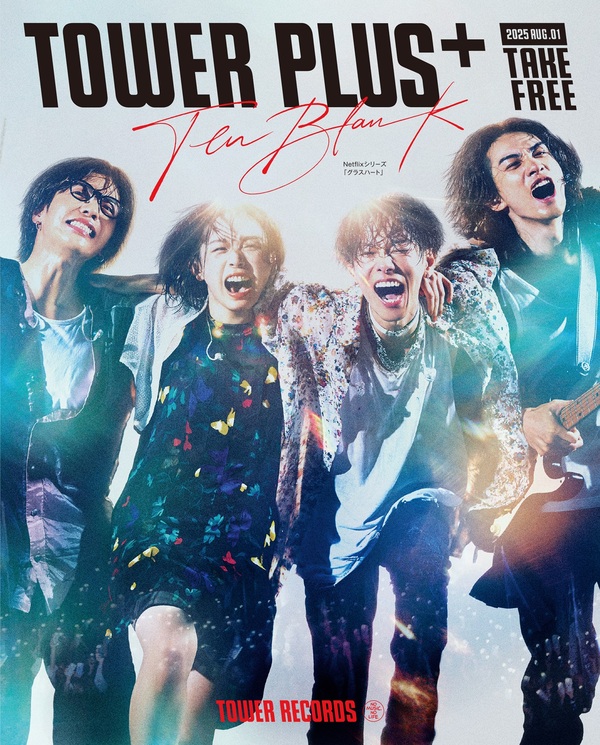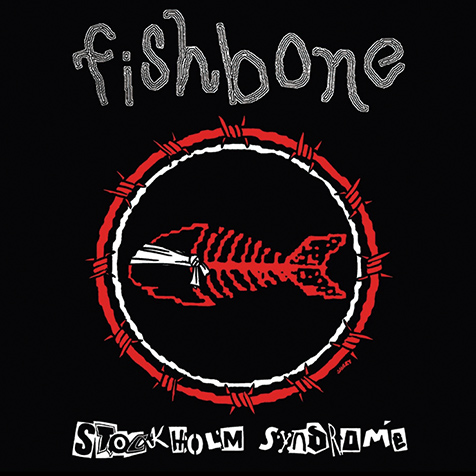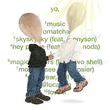本秀康が選ぶジョージ・ハリスンの5曲
1. “The Inner Light”(ビートルズの68年のシングル『Lady Madonna』収録)
2. “Something”(ビートルズの69年作『Abbey Road』収録)
3. “All Things Must Pass”(70年作『All Things Must Pass』収録)
4. “Love Comes To Everyone”(79年作『George Harrison』収録)
5. “Handle With Care”(トラヴェリング・ウィルベリーズの88年作『Traveling Wilburys Vol. 1』収録)
純粋に5曲だけなんて到底選びきれないので、ジョージの音楽性の移り変わりを時系列で区切り、その期間を象徴する曲を選ぶ方式にしました。
まずはビートルズ時代。初期は作曲に迷いもある修行時代、中期はインド風の曲や“Blue Jay Way”、“Long, Long, Long”など不思議な曲ばかり作っていた実験時代、その後覚醒してロック史に残る名曲群を連発した後期と、ビートルズ時代のジョージの作風の変化は3期に分けることができ、聴きどころは中期から後期だと僕は考えます。中期からは3曲あるインド風楽曲のうち最もメロディが美しい“The Inner Light”を、後期からは誰もが認めるジョージの代表曲“Something”を選びました。
ビートルズ解散直後にリリースした『All Things Must Pass』はビートルズ時代に書き溜めた曲を大放出した3枚組アルバムです。これ1作でビートルズの8年間と同等の熱量があります。どれも名曲で迷いますが、この時期特有のスワンプロック的なサウンドと、ジョージ本来の持ち味がマッチしたタイトル曲“All Things Must Pass”を選びました。
76年に立ち上げた自身のダークホース・レコーズ。ここからジョージの替えの効かない独自性が完全に確立されたと言えます。この時期からは79年の傑作アルバム『George Harrison』(邦題『慈愛の輝き』)収録の“Love Comes To Everyone”(邦題“愛はすべての人に”)を選びました。穏やかなメロディとさりげないグルーヴ感がたまらない大名曲です。
87年の特大ヒットアルバム『Cloud Nine』から晩年までは、基本的にはELOのジェフ・リンとタッグを組んでおり、ジェフ特有のサウンドが印象的な時期です。この期間からはジョージを中心としたミュージシャンたちによる覆面バンド、トラヴェリング・ウィルベリーズの“Handle With Care”を選出しました。ボブ・ディランやロイ・オービソンなどの超大物がナチュラルにセッションを楽しんでいるのは、ひとえにジョージの人柄によるところが大きいのだと思います。ビートルズ時代に〈第3の男〉として立ち回った経験の賜物でしょう。トラヴェリング・ウィルベリーズだけでなく、どんな場面でも一歩引き、参加ミュージシャンの個性を尊重するジョージの人柄が、素晴らしい音楽を育んだのだと思います。ジョージの優しさに感謝!