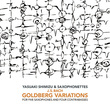清水靖晃インタヴュー 〈究極のゴルトベルク〉コンサートに向けて
先日リリースされたニュー・アルバム『バッハ:ゴルトベルク変奏曲』でますます人気沸騰しているアイスランドの俊英ピアニスト、ヴィキングル・オラフソンと、2015年のアルバム『ゴルトベルク・ヴァリエーションズ』によって世のバッハ受容にコペルニクス的転回をもたらした清水靖晃&サキソフォネッツ。この両者が一堂に会してそれぞれの“ゴルトベルク変奏曲”全曲を演奏するという奇跡的プログラムが12月に実現する。題して〈究極のゴルトベルク〉。
清水は『ゴルトベルク・ヴァリエーションズ』以前にも、テナー・サックスのソロによる『チェロ・スウィーツ 1. 2. 3』(1996年)及び『チェロ・スウィーツ 4. 5. 6』(1999年)を発表するなど、30年近くにわたって独自のバッハ解釈を続けてきたが、ヴィキングル・オラフソンと同じステージに立つ今回のコンサートでは、彼の思い描くバッハ像や音響芸術としてのユニークさがひときわくっきりと照らし出されるはずだ。
期待のコンサートに向けて、今改めて、自身とバッハの関係について語ってもらった。
書棚からパラパラと落ちてきたバッハの楽譜
――清水さんが『チェロ・スウィーツ 1. 2. 3』でセンセーションを巻き起こしてから30年近くが経ちますが、そもそも、最初にバッハを吹いたのはいつなんですか?
「僕は80年代半ばからパリ~ロンドンを拠点に活動していたけど、そのロンドンから東京に戻り、細野晴臣さんと共同プロデュースしたコンサート・シリーズ〈東京ムラムラ〉が終わった後だから、94年頃だったと思います。たまたま自宅書棚である楽譜を探していたら、パラパラっと「無伴奏チェロ組曲第1番」の楽譜が落ちてきた。で、それを拾って吹いてみたらすぐにはまってしまったんです。更に、エフェクターで残響もつけてみたんだけど、これはエフェクターを使うよりも、響きのいい空間でのナチュラル・リヴァーブでやったらもっと面白くなるなとひらめいた。そこからバッハとのつきあいが本格的に始まったんです。それ以前にも、たとえばピアノでちょっと弾いたりはしていたけど、それは楽曲構造や和声の研究のためだったりしたわけで。その頃まで僕はいろんな実験的なことをやってきていたけど、当時はサックス1本だけで何かやってみたいなという気分でもあった」
――リスナーとしての出会いは?
「それはもう小さい頃。父は家業以上にアマチュア音楽家としての活動に熱心で、母は小学校の先生で合唱の指導もしていたから、家にはクラシックだけでなくラテンやジャズ、シャンソン、歌謡曲などいろんなレコードや楽器がありました。だから僕は幼少時から手あたり次第にいろんなレコードを聴いていたし、楽器もピアノの他あれこれやっていた。当然バッハも聴いていたけど、といって特にバッハ・ファンだったわけでもなく、クラシックではロマン派、たとえばブラームスやシューマンなどのオーケストラものが一番好きだった。レコードを聴きながら、指揮の真似をしたり。ショスタコーヴィチの5番を振るのがエキサイティングだったけど。だから、『チェロ・スウィーツ 1. 2. 3』を出すまでは、特にバッハと深い縁があったわけじゃないんです」
――たまたま楽譜が落ちてきたという偶然の再会からCD制作まで一気に行ったのが不思議です。何か特別な感動や、背中を押すような出来事がもっとあってもよさそうですが。
「その自宅でのバッハとの再会の時、〈バッハ × 筒(テナー・サックス)× 空間〉の三角関係というコンセプトを思いついちゃったことが大きかったと思います。そもそもバッハの音楽はキリスト教会で信者の魂を天に向けて上昇させるような崇高なものだけど、そんなバッハと下世話なテナー・サックスという組み合わせがまずは刺激的だし、同じく筒構造である人間が銭湯での鼻歌のような響きを生み出すナチュラル・リヴァーブ空間というのも魅力的でしょう。これはやるしかないとレコード会社に提案したら、ビクターのポップ・セクションが乗ってくれて」
――ナチュラル・リヴァーブの効いた空間で録音するため、いろんな場所を調査したんですよね。
「そう、いろんな人に、いい場所はないかなと相談した。通常は音楽をやらないようなグッとくる空間はないかと。たとえば、南こうせつさんのラジオ番組にゲストで出た時、彼の出身地である大分県日田市に使ってないトンネルがあると教えてもらった。日田市でもそこを有効活用したいと思っており、いろんな案が出ているけど、トンネルを挟んでの綱引き大会ぐらいしか案がないんだと。で、翌週すぐにそのトンネルに行ったら、日本昔話に出てくるようなのどかな田舎で、近くには炭鉱のボタ山も見えたりする。こういう場所でのバッハがいいと気に入ったんだけど、トンネルの構造上、フラッター・エコーで多重反射してしまい、そのうえ意外と響かないので、結局あきらめました。その他にも、使っていない水力発電所とか、福井の山中にある越前大仏の大仏殿とか……(笑)」
――2枚のCDで全6曲、すべて録音場所が違っていましたよね。
「最初の“第1番”は、向島にあった山本耀司さん関係のコンシピオ・レコードのロビーで録音しました。“2番”は宇都宮市の大谷石地下採掘場跡。“3番”は大田原市のよく響く那須野が原ハーモニーホール。“4番”は釜石市の釜石鉱山花崗岩地下空洞。ヘルメットかぶって、地下500メートルまでもぐって。“5番”はイタリアのパドヴァにある巨大な離宮ヴィラ・コンタリーニの3階吹き抜けのサロン、そして「6番”は同じくパドヴァ、ラッツォ・パパフォーヴァの丸天井を備えたサロン。“6番”は演奏が一番難しいけど、録音場所も含めて特に気に入っていますね。そのサロンは貴族の家の空き部屋で、丸天井の高さが12メートルなので残響が15秒ぐらいあった。筒(サックス)に息を吹きかけただけで、その音がフワーッと宇宙船のように宙空に飛び立ってゆく感じ。演奏しながら音と身体が一体化していった。あのマジックは病みつきになります」
――録音機材はどういったものでしたか?
「最初の『チェロ・スウィーツ 1. 2. 3』を録音した96年は、機材がADATからプロトゥールスに移行する時期で、まだプロトゥールスがあまり信頼できなかった。なので“1番”の時はADATで録ったけど、“2番”からはプロトゥールスです。“2番”も最初はADATを持って大谷石地下採掘場跡に入ったんだけど、湿度がすごいのでテープが湿ってエラーしちゃうわけ。それでプロトゥールスに急遽切り替えたんです。当時はまだほとんど誰も使ってなかったけど、うまくいきました。」
――さっきの三角関係のことですが、これはやはりバッハでなくてはいけなかったんですか? 神聖かつ崇高な音楽なら他にもあるわけで。
「まず、無伴奏で楽器一つでやりたかったので、やはりバッハの“無伴奏チェロ組曲”が一番いいと思ったんです。空間の響きを最大限生かすためには、和声のある曲は避けたかった」