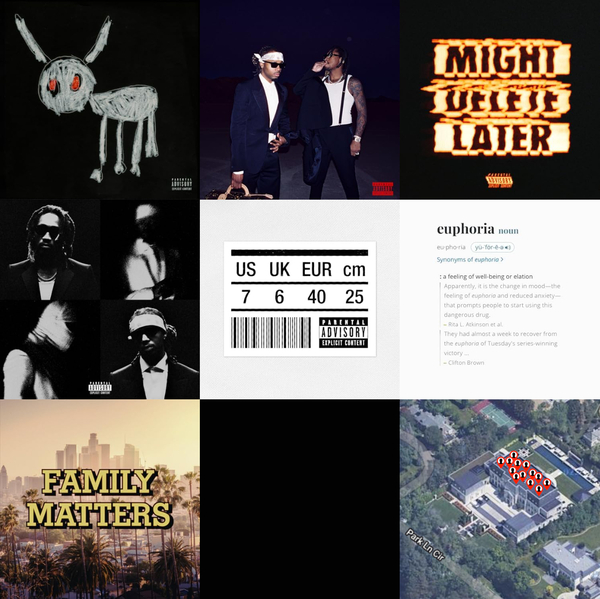ひとつの感情を描いたアルバム
〈私の人生から生まれた楽曲を新たに録音して作り上げた、始まりも終わりもない音楽のモンタージュ〉といった旨のコメントを今回残しているニール。〈アルバムを通してひとつの感情があるのだ〉とも語っているが、確かに“I’m The Ocean”(95年)といったレアなナンバーや“Homefires”など未発表となっていた曲、それに“Birds”(70年)や“Comes A Time”(78年)などのライヴ定番ソングを時系列関係なしに並べつつ、曲間のスペースを取っ払ってシームレスな作りとなっていることから、感情の変遷がいっそう見えやすくなっているというか、もっと言えば、曲を通じて何か大事なものを見つけようとする彼の探求的な姿勢が随所から浮かび上がってくる作品となっていて大変に興味深い。
それにしても選曲、曲順がとてもユニーク。バッファロー・スプリングフィールドのファースト・アルバム(66年)に収められていたまさかの“Burned”が飛び出してきたかと思ったら続けざまに“On The Way Home”(68年)が演奏されたりして、途中下車は不可というルールがあちこちに小さなスリルを発生させているのも魅力的。それから楽器の音色がもたらすさまざまな効果についても見逃せない。例えば、古めかしいオルガンの響きに包まれた“If You Got Love”(82年作『Trans』のアウトテイクだった曲)や“Mr.Soul”(82年)などは閉じっぱなしになっていた心の奥にある引き出しの存在を知らせてくれたりするし、“A Dream That Can Last”(94年)から始まる中盤のまどろみピアノ・タイムは夢想に耽るのにもってこいだったりする。で、歌い手としてのニールはいったいどうなのかというと、ただただ流れるように漂うように曲世界を生きている、といった表現がピッタリ当てはまる感じで、終始穏やかな身振りと表情を浮かべ続けているのであった。
とにかくアルバムのどこを探しても〈重さ〉が見当たらない。よって“Mother Earth”のような美しい曲が存在感を放つ結果となっているのだが、印象的なメロディーの数々が立ち現れては消え、というサイクルが儚くも美しいパノラマを導き出しているところこそいちばんの聴きどころなのかもしれない。あと、2021年作『Barn』のエンディングを飾った“Don’t Forget Love”が本作でも同じポジションに配置されているが、余韻の度合いがすこぶるアップ。秀逸な幕引きを演出しているのも特筆すべき点であろう。
単なるベスト盤ではないし、いわゆるリメイク集とも言い難い。短編小説集的ともいえる構造を持っていたり、ところどころで映画的な手法が駆使されていのも垣間見られたりするが、何にせよ、ニールのディスコグラフィーのなかでも特異な雰囲気を放つ作品になることだけは間違いないはず。聴き手の時間感覚を大いに狂わせてしまう厄介さが備わっていたりもするけれど、聴くたびにいわく言い難い不思議な佇まいに無性に惹き付けられてしまっている自分を発見する。そして、ニール・ヤングって人はやっぱり不思議なお方だとつくづく思うのである。そんな彼がこの先も変わらず不思議なままで居続けてくれるであろうことの証となり得るこの作品とも、当分の間は深い付き合いをすることになりそうだ。
2023年に登場したニール・ヤングのボックス作品。
左から、89~91年作をまとめた6CDの『Official Release Series Discs 22, 23+, 24 & 25』、8CDの『Neil Young Archives Vol. 1(1963-1972)』(共にReprise)