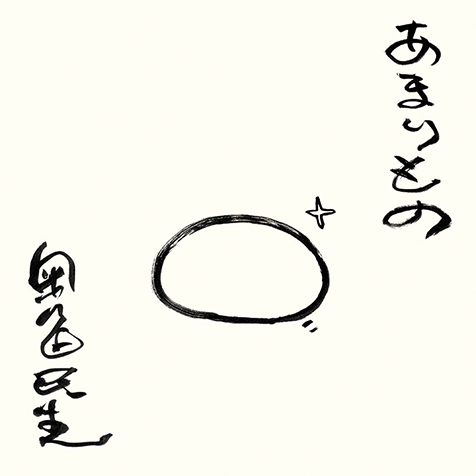超絶技巧とテクノロジーによる熱狂のライブ
――音楽的に大きな振れ幅を持ちながら、トータルなアルバムとしてのまとまりも強く感じるのが本作の面白いポイントだと思います。
「もはやひとつのジャンルにおさまるものではないですよね。たとえば単にテクノというべきかというと、そうは思えない。チック・コリアの『Return To Forever』(1972年)だったり、トムと近しいところでいえばジャコ・パストリアスの『Word Of Mouth』(1981年)とか、あるいはメタリカの『Master Of Puppets』(1986年)みたいな……歴史にのこる名盤のひとつみたいなイメージです。というとちょっとデカく出すぎているかもしれないですけど。
リリース当時はまさにポストロックが盛り上がっていた頃で、つまりバンドという活動形態でありながら、ラップトップでの編集をはじめとしたテクノロジーをつかった改変を受け止めるようになった世代でもある。それが後にバトルズのようなバンドにもつながっていくわけですけど。そういう裾野の広がり方に、トムさんの影響は大きいと思います。
思えば、2004年以降の数年間、僕が好きなアーティストたちはどこかのタイミングで確実にトムの話をしていましたから。レディオヘッドもそうだし、レッド・ホット・チリ・ペッパーズもそうだし。ジョン・フルシアンテはめちゃくちゃトムさんのことが好きでしょう。ほかにも、ジョン・マッケンタイアとかも。ザ・シネマティック・オーケストラのジェイソン・スウィンスコーと一緒にインタビューをしたことがあるんですけど、そのときも突然トムの話が出てきて、意外に思ったことがありました。他にもジャガ・ジャジストが来日したときにメンバーと話したときもトムさんの新譜が話題に出て。それはベーシストの連中と話したからというのも大きいですけど」
――プレイヤーでありつつテクノロジーに関心をもつ方々のあいだで、スクエアプッシャーが共通言語になりえていたということですね。
「昔からトムさん自身が様々な機材を使いつつベースも持つようなパフォーマンスをしていたわけですけど、『Ultravisitor』以後はそれをさらに押し広げたように見えたんだと思います。こんなこと言っていいのかわかんないですけど、最初は本当にカラオケでベースを弾いている感じで。1997年の新宿LIQUIDROOMでの初来日をみたとき、僕は正直〈すごいな〉と思いながら笑っちゃったんです。バカバカしいほどの真面目さがあって、それがすごくチャーミングだった。
でも、『Ultravisitor』で誰もそれを笑えなくなった。2004年、ラフォーレミュージアム六本木でのライブはすさまじい熱狂でした。いまだに忘れられないです。全身黒のトムさんが、山のように積んだ機材を持ってきていて。ラップトップオンリーだった『Go Plastic』(2001年)と『Do You Know Squarepusher』(2002年)の流れから、Eventide H3000をはじめとしたエフェクターラックが積まれて、KORG MS-20が置いてあり……。〈戻ってきた!〉という思いもあるし、しかもまさか“Tetra-Sync”みたいな曲まで生で弾いたことに驚きました。僕はほぼ最前列、トムのど真ん前で、彼の指の動きひとつも逃すまいと思って見ていました。
結局、“Iambic 9 Poetry”は一度もやらなかったんですけどね。それ以降も、フレーズをベースで弾いてくれることはあるものの、ほぼやっていない。トムさんがドラマーを連れてツアーをしていた頃に、この編成ならできないのかと思ってそのドラマーにたずねたことがあるんですけど、あれはクリックがめちゃくちゃだから無理だと言っていました」
――“Iambic 9 Poetry”はスクエアプッシャーのディスコグラフィのなかでも屈指の人気曲のひとつですし、それが演奏されないのは惜しい気もします。
「やっぱり、あのカオスをつくれないのかな。構造上おかしいんです。クリックなしで叩いているドラムに、わざわざシンセを生で弾いてあわせているんですよね。それでも演奏が追いつかないから、ドラムの演奏の隙間をむりやり詰めて、おかしなタイム感の突っ込み方になっている。そこに、位相のずれたシンセの音も入ってくる。あれはもう、和声として整合性をもって再構成することはできないんじゃないかな。いわゆる十二平均律で完全に再現することは難しい。そもそものピッチも少し怪しいですから。
ただ、エイフェックス・ツインもトムさんも昔から、1オクターブ内にある12音を、あえて1音ずつピッチをズラしたりするんです。特にエイフェックス・ツインはそういう機能を持ったシンセ(KORG monologue)をつくっているので。トムさんも、リード楽器はちょっと怪しい音になっていることが多い。たとえば、今回のボーナスディスクに入っている“Square Window”っていう曲も、ピッチが怪しい。そうすることで抜けが良くなるんですよね」
――観客の声やトム自身の呼びかけもアルバムのなかに盛り込まれ、疑似ライブアルバムとでも言うべきギミックが取り入れられているのも本作のユニークなポイントです。
「トムさんって結構ライブで煽るじゃないですか。そこにも彼なりのアティチュードがあるんだと思います。ラップトップに向かって難しい顔をしてやっている人たちに対抗しようとするものを感じるんですよね。
ただ、ベースを抱えているからなのか、挙動がまたお茶目じゃないですか。それがもともと〈おもろかっこいい〉だったのに、〈かっこいい〉になっちゃった。作品でねじ伏せてしまったんです。前2作を経て、〈全然ライブもできるんだぜ、ライブアーティストなんだぜ〉ということを思って『Ultravisitor』みたいなことをしたのかな。
それに、ライブで披露するような、リングモジュレーターをフットコントローラーでいじって出すとんでもないフィードバックや歪みは、CDの音源には微妙にはあったかもしれないけど、生々しく切り取って収めたのは『Ultravisitor』がはじめてだったかもしれない。そういう演奏をどうすれば録れるんだろうと思ったのがきっかけになっているのかも。私たちファンは、もうその姿を見てはいたんですけどね。
ライブのときトムさんの楽器から出てくる音はもう奇想天外すぎて、最近はドラムの音まで出してますから。音がどうというか、ドラムのトリガーになっている。よくわからないMIDIコントロールの使い方をしはじめています」