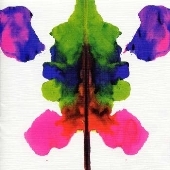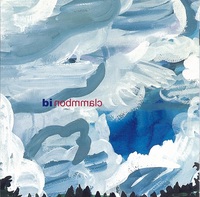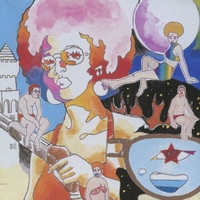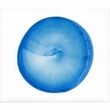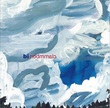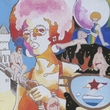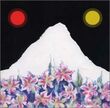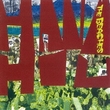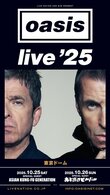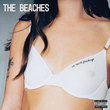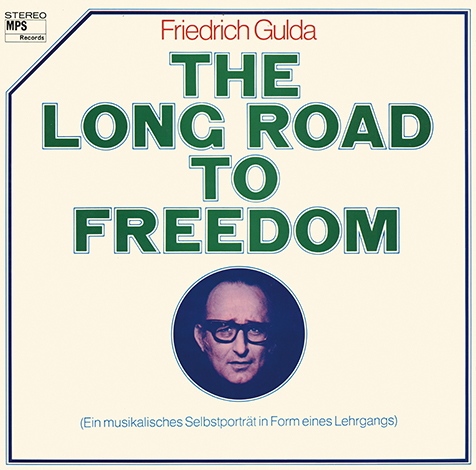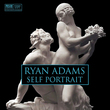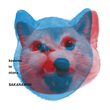米津玄師やVaundyなど、現在シーンの先頭を走る多くのアーティストに影響を与えた2000年代の日本のロックシーンを振り返る短期連載〈Back to 2000s J-ROCK〉。第2回は、くるりやスーパーカーなど〈98年の世代〉の音楽性の進化、フィッシュマンズの復活、〈喫茶ロック〉の盛り上がり、〈4つ打ちロック〉ブームの変遷などについて触れていく。 *Mikiki編集部
★連載〈Back to 2000s J-ROCK〉の記事一覧はこちら
音楽性を変化させ、名盤を生み出したくるりとスーパーカー
2000年代の初頭はまだインターネットの黎明期で、音楽の情報を知るにはテレビやラジオ以上に雑誌の存在が大きな時代だったように思う。僕自身も「rockin’on」「CROSSBEAT」「COOKIE SCENE」などをよく読んでいたが、その中でも一際強い個性を放っていたのが元「rockin’on」の副編集長だった音楽評論家の田中宗一郎が1997年に創刊した「snoozer」。その中で提唱されたのが〈98年の世代〉という言葉だった。
くるりが2014年に最初期のデモテープである『くるりの一回転』をダウンロード販売した際、田中が寄稿したライナーノーツから引用すると、〈時代は90年代半ば。それは日本のポップ音楽にとってとても芳醇な時代でした。「CDショップ」と呼ばれる業態が全国的に一般化し、それまでアナログ・レコードでは手に入らなかった膨大な過去の名盤カタログがCDという形で一斉に復刻され、誰にでも気軽に手に入るようになった時代でした。しかも、以前なら考えられなかったような巨大な敷地面積の売り場の中で、古今東西の名盤がずらりと並べられることになったのです〉という背景から、それまでの日本にはいなかったような多様なアーティストが次々と現れ、ジャンルで括ることができないからこそ、〈98年の世代〉と世代で括ったのであった。
僕の中で〈98年の世代〉を代表するのはくるりとスーパーカーで、CDショップによるバックカタログに加え、まだ黎明期ではありながらインターネットが徐々に普及して、同時代の海外の音楽もより身近になり、制作においてはPro Toolsが普及していったことで、〈バンド〉という形態でありながら、貪欲に様々な表現を行なったのがこの2組だった。
デビュー時にはフォークロック的なイメージだったくるりは、2000年の『図鑑』でジム・オルークを招いてポストロックに近づき、デビュー時にはオアシスやダイナソーJr.といった英米のロックに影響を受けていたスーパーカーは、2000年の『Futurama』でトランシーなダンスミュージックへと接近。その後を追うように、くるりは2001年の『TEAM ROCK』でテクノやハウスを飲み込み、“ワンダーフォーゲル”や“ばらの花”、さらには“WORLD’S END SUPERNOVA”といった名曲が生まれていった。
フィッシュマンズの遺伝子を継ぐものたち
2010年代以降は〈ポストジャンル〉という言葉が生まれたりもしたが、当時使われたのは〈エクレクティック=折衷的〉という言葉で、1990年代においてその先駆けとなったのが、ダブ/レゲエを起点にジャンルを横断し、現在では世界的な評価を獲得しているフィッシュマンズであったように思う。
1999年に佐藤伸治が急逝し、バンドの歩みは一時的にストップしたわけだが、2000年代の前半は彼らの遺伝子を受け継ぐバンドが活躍した時代でもあった。“ナイトクルージング”の素晴らしいカバーも知られるクラムボンは2002年の『id』でシカゴ産ポストロックの雄の一人であるアダム・ピアースを招き、SUPER BUTTER DOGは2000年の『FUNKASY』でファンク起点のポップを表現し、2001年に名曲“サヨナラCOLOR”が誕生している。
2005年にフィッシュマンズが復活した際、ゲストボーカルを務めたのがクラムボンの原田郁子と、SUPER BUTTER DOG解散後にハナレグミとして活動を開始していた永積タカシだったわけだが、同年にこの2人とohanaを結成したのが、フィッシュマンズ休止以降の柏原譲とPolarisをスタートさせた元LaB LIFeのオオヤユウスケ。先日Polarisのライブ活動再開を発表し、柏原が病気療養のために今年8月から活動を休止していることを受け、〈いつかまた譲さんが戻ってきて楽しく一緒に演奏出来る場所になるよう続けていくことを決意しました〉と綴ったことも記憶に新しい。