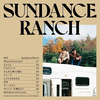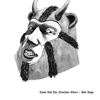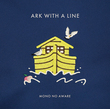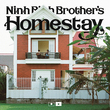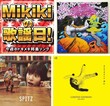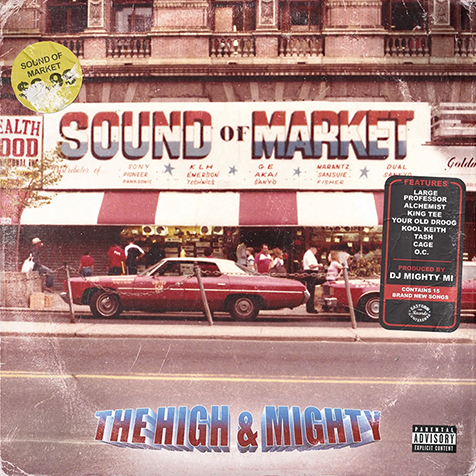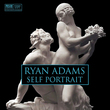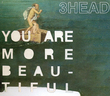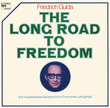賛辞を集めた名盤をモノにし、これまで以上の大舞台を経験してきた4人はいま絶好調! 多幸感と推進力に溢れたニューEP『走馬灯』に見える〈忘れがたき人生のシーン〉とは?
MONO NO AWAREが昨年リリースした『ザ・ビュッフェ』は、ASIAN KUNG-FU GNERATIONの後藤正文が設立した〈APPLE VINEGAR -Music Award-〉の大賞を受賞。今年の〈フジロック〉では大観衆の待機するWHITE STAGEに登場。玉置とギターの加藤(成順)の出身地である八丈島の八丈太鼓も加えた演奏は途轍もない盛り上がりを見せ、喝采を浴びた。そんな彼らのバンドとしての好調ぶりを真空パックしたのが、初のEPなるCD音源と演出付きワンマンライヴ〈波止場大サーカス〉の模様を収めたBlu-rayから成る『走馬灯』だ。フロントマンでソングライターの玉置周啓は、昨今の自分たちのライヴについてこう話す。
「最近のライヴのヴァイブスがかなり素晴らしい状態になっていて。いま、この空気を記録しておかないともったいないなと。意識的に煽っているわけでもないのに、ごっそり客層が変わったんじゃないかっていうぐらい、ライヴの盛り上がりが凄いんです。以前はわりとお客さんが大人しい感じだったんですけど、いまは皆がライヴ中に大きく手を振ってダイナミックに動いてくれるようになった」。
オーディエンスの反応が変わったのはむろん、彼らの演奏が進化/深化したからだろう。
「ベースの竹田(綾子)が休養を取っていた時期があって、その間はサポートを入れて20回ぐらいライヴをしたんです。そこで演奏してくれた清水直哉はすごく巧いプレイヤーだったので、彼が入って演奏のギアが変わったのは正直ありますね。でも不思議なのは、その後竹田が戻ってきて、また以前のような演奏に戻るのかと思ったら、演奏のクォリティーは上がったままで竹田が入ったヴァージョンになった。男4人だったときとはまた全然違う。不思議ですね」。
初のEPは、重心の低いリズムとキャッチーなメロディーが際立つ“走馬灯”、ボサノヴァ風の曲調が印象的な“スノードーム”という新曲を収録。さらに、既発曲だがライヴでアレンジが大幅に変わっていた“そういう日もあるⅡ”“me to meⅡ”も聴くことができる。前者は打ち込みのリズムを含む80年代風の曲だったが、新録では生の質感を活かした温もりに満ちた仕上がり。後者はぐっとテンポが速くなり、疾走感が増した。共にファンには待ちに待った音源だろう。初出音源と聴き比べるのも一興かと思う。
「『ザ・ビュッフェ』のときは食がテーマだったので、そのあとのEPとしてデザート的なニュアンスのものを出しても良かったんですけど、それよりもライヴ映像とかジャケットでも表されているような多幸感を表現したくてこの4曲を入れました。ライヴ映像の最後に紙吹雪が舞うんですけど、そういう喜びも表現したかったですね」。
どの曲もA→B→サビ→間奏といった定型をなぞらず、楽器の抜き差しで曲を転がしてゆくのも特徴だ。ギターのリフや柳澤豊が刻むドラムのライドシンバルは曲を展開させる推進力になっている。
「そうそう。例えばベースだったら、そんなに動かなくていいからって、ルート弾きをする場面が増えているんですよね。 そうすると、ちょっと動くだけで曲のムードが変わる。いままではベースがずっと動きっぱなしのことも多くて、忙しなかったので、それはある意味、成長や変化なのかもしれないです」。
歌詞も相変わらずユーモラスで機知に富む。“走馬灯”の出だしは〈経済学部の経済学科/将来のために入ればよかった〉。思わず反応してしまう。
「僕が好きなアークティック・モンキーズが“Star Treatment”という曲を〈ストロークスになりたかった〉という歌詞で曲を始めていたので、それへのオマージュですね。あとは、以前は自主で活動していたので、お金に関する権利関係のこととか経済学部だったらもっとわかったかなと。あ、それならむしろ法学部? 確かにそうかもしれない(笑)」。
MONO NO AWAREの作品。
左から、2024年作『ザ・ビュッフェ』、2018年作『AHA』(共にSPACE SHOWER)、2017年作『人生、山おり谷おり』(Pヴァイン)
メンバーの参加作。
左から、MIZの2022年作『Sundance Ranch』(SPACE SHOWER)、小原綾斗とフランチャイズオーナーの2025年のEP『BAD DOGS』(BAD PEOPLE/SPACE SHOWER)、Salanの2025年のEP『Mp3』(Salan)