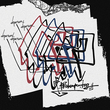自然の移ろいや人生の機微に触れたときに感じる情緒を表す〈もののあはれ〉をバンド名に冠した4人組、MONO NO AWAREがファースト・アルバム『人生、山おり谷おり』を発表した。彼らの楽曲は海外のガレージ・ロックやポスト・パンクなどを背景としつつも、その振れ幅はかなり広く、一曲の中でも大胆に曲調が変化していく。また、アルバム・タイトルにも表れている、思わずニヤッとしてしまうような言葉遊びも独特だ。Tempalayとドミコが共催するパーティー〈BEACH TOMATO NOODLE〉周辺に代表される、東京インディー・シーンのサイケ・ポップな新潮流ともリンクしつつ、しかし、カテゴライズからはするりと抜け出て行く、その飄々とした佇まいが他にはない個性を放っていると言えよう 。
バンドの中心は作詞作曲を担当するヴォーカル/ギターの玉置周啓と、ギターの加藤成順という八丈島出身の2人。感覚派の文系である玉置と、研究家肌の理系である加藤はお互いを補い合いつつ、共に自由を希求し、〈ここではないどこか〉を志向している。どこかシャムキャッツの夏目知幸と菅原慎一にも通じる魅力的なコンビを擁するMONO NO AWARE。井戸を飛び出した彼らは、これからどんな世界を見せてくれるのだろうか?
いろいろあるのがMONO NO AWAREだと思ってほしい
――まずはバンド結成の経緯を教えてください。
加藤成順(ギター)「自分と周啓は地元が八丈島で、高校を卒業したあとに自分は群馬の、周啓は東京の大学に行ったんですけど、彼は昔から曲を作っていたので、上京してから電話やSkypeをしたときも〈大学でも絶対バンドやりなよ〉と伝えていたんです。でも、一年くらい経っても状況が変わらずに、まだ家で1人で曲を作ってるというから、しびれを切らせて〈じゃあ、一緒にやろう〉と言ったら、〈俺も同じこと考えてた〉って(笑)」

――最初から〈一緒にバンドをやろう〉と上京してきたわけではないんですね。
玉置周啓(ヴォーカル/ギター)「成順は群馬に行ったし、バンドを一緒にやるイメージは全然なかったです。かといって、僕は他の人とバンドを組むような行動力がないので、一年ちょっと1人でやってたら、成順が〈もう俺とやろうよ〉って言ってくれた。ホントに僕も同じタイミングで成順を誘おうと思っていたから、〈両想いだった〉みたいな(笑)」

――そして、ベースの竹田(綾子)さんは玉置くんと同じサークルにいたそうですね。
玉置「前にいたドラムはすぐに成順が紹介してくれたんですけど、なかなかベースが見つからなくて……というか、竹田さんのことは知っていたんだけど俺が声をかけられなくて(笑)。でも勇気を出して彼女を誘ったら、〈ちょっと考えさせて〉と言われて3か月も待たされました」
竹田綾子(ベース)「私は高校のときに部活でバンドをやってたんですけど、大学でもサークルだけでやるつもりで、外でライヴとかはちょっとなと思っていたんです。それで迷っていて、気づいたら3か月経っていました(笑)」
玉置「長かったよ~」
竹田「ごめんね(笑)」
――結成当時の方向性はいまとは違ったんですか?
玉置「もっとわかりやすく、2000年代のJ-Rockに近いものをやっていました。それが嫌になったわけではないんですけど、メンバーと情報交換をするようになって、聴く音楽がイギリスのロックに寄って行き、その頃にいろんなドラム・パターンを叩ける(柳澤)豊が入ったこともあり、変わっていった感じですね」
柳澤豊(ドラムス)「僕が入った頃にやり出したのが“井戸育ち”、最初はあの曲が浮いていたので、いま思えばそこが転換期だったんだな」
――もともとのJ-Rockというのは、具体的にはどのあたり?
玉置「よくスーパーカーとかくるりみたいと言われていました。いまよりも、もっとわかりやすくてキラキラした、ポカリのCMみたいな(笑)。僕はもともと日本のバンドしか聴いてなくて、中学のときにまず歌詞を書きはじめたんですけど、そのきっかけがRADWIMPSの野田洋次郎だったんです。彼の言葉遊びやスケールのでかいことを言う感じが中学生の自分にはピッタリで。当時はRADWIMPSやフジファブリックとかをよくコピーしていたので、コード進行なんかは彼らの影響が強いのかな」
――スーパーカーやくるりはバンドの背景としてイギリスのロックもあるから、そっちに向かうのは自然なことだったような気がします。
玉置「僕の音楽の聴き方って結構突拍子もないというか、流れでは説明できないんです。イギリスのロックを知ったのは、大学一年のときに友達がたまたまアークティック・モンキーズの“A Certain Romance”をかけていて、暗めのイントロから急に(曲調が)明るくなるのがカッコイイと思って、そこから洋楽も自覚的に聴くようになりました。“井戸育ち”はそのあとにできた曲で、いま聴くとリズムがストロークスやフェニックスっぽいから、ちょうどそのとき聴いてたんでしょうね。俺は全然音楽詳しくないんですけど、ほかのメンバーはいろいろチェックしてるんで、教えられた音楽から曲が出来てくるんだと思いますね」
――MONO NO AWAREというバンド名にはどんな由来があるのでしょうか?
玉置「昔の僕は〈RADWIMPS=神〉みたいな感じだったんで、考えが青臭かったんですよ。だから、バンド名もダブル・ミーニング、トリプル・ミーニングみたいにしようと思って、吉田兼好の言う〈川の流れは絶えず移り変わる〉みたいな意味と、辞書的な〈何とも言えないしみじみとした感情〉という意味と、さらにローマ字にして〈MONO〉と〈NO AWARE〉で〈気付かない、ひとつのもの〉みたいな(笑)。まあ、いちばん大事なのは〈曲調がどんどん移り変わる〉という部分で、特定のアーティストや、いまだったらブラック・ミュージックが流行っていますけど、そういうトレンドには影響されたくないんです。流れに身を任せるというか、やりたいようにやって、その中でいろんな曲が出来ていく。その様を〈MONO NO AWARE〉って言葉で表したという」
柳澤「個人的には、それこそくるりのように、いろいろなサウンドをやっているのがおもしろさだと思うんですね。僕はブラック・ミュージックが好きだし、もともといろんな音楽を聴くのが好きなんです。自分の趣味にMONO NO AWAREを寄せるというよりは、周啓がどんな曲を作ってきても対応できるように、いろいろ聴いてる感じ」

竹田「私もいろいろあって良いと思っていて、どこかに寄せて行きたくはない。いろいろあるのがMONO NO AWAREだと思ってもらいたいんです」
玉置「バンドの方向性を規定しちゃうと、他のことをやりたくなったときに、苦しくなっちゃうと思うんですよ。なので、まず自分たちが楽しくて、かつお客さんも楽しめるっていう、そのバランスだけを見ている感じ。それに対して、〈MONO NO AWAREっていろいろやるバンドだよね〉と思ってもらいたい。大きいことを言えば、各バンドが各ジャンルを担うんじゃなくて、各バンドがそれぞれ好きなことをやれる音楽業界になったら良いなって。まあ、商業的に扱いづらいというのも自覚してるんですけど(笑)」
柳澤「コンピレーションっぽいとも言われるしね」
――でも、くるりなんてまさにそこがおもしろいバンドですよね。なおかつ、さっきのバンド名の話の通り、1曲のなかで曲調がどんどん変わるのがMONO NO AWAREのおもしろさだなって。
玉置「飽きっぽいので、他のバンドの曲をあんまり何回も聴けなくて、〈またAメロか、さっきも聴いたな〉って、テンション下がっちゃうんですよ。僕らも繰り返しのある曲もやっていますけど、それは〈ここにもう一回歌詞を入れたいから〉っていう発想なんです」
――竹田さんは玉置くんのソングライティングに対してどんな印象を持っていますか?
竹田「一言で言ってしまうと……凄く面倒臭いです(笑)。デモの時点ですごく作り込まれていて、そこがおもしろいんですけど、そのぶん覚えるのは大変で」

玉置「もともと彼女のルート弾きがカッコイイなと思い誘ったんですけど、いまは全然そうじゃないんで……順応性あるなと思います(笑)」
――曲調はさまざまだけど、加藤くんの耳に残る単音フレーズや反復を基調としたプレイはバンドの個性になっていると思います。加藤くんはギタリストだとどんな人が好きなんですか?
加藤「僕は基本的に〈ザ・ギタリスト〉みたいな人ってあんまり好きじゃないんですよね。マニュエル・ゲッチングとかが好きなんですけど、ああいう研究心のある人がおもしろいなと思います。ただ、最近は逆に〈ギタリストになりたい〉という気持ちも出てきていて。周啓が作るギターのフレーズはあんまりギターっぽくないんだけど、お客さんとしては〈いかにもギタリストなプレイ〉のほうが惹きこまれるかなと思う。なので、今後はそうしたプレイも心がけていきたい」