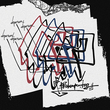どの作品にも常にフレッシュな挑戦と冒険を詰め込んできた小林太郎が、約1年ぶりのリリースとなるサードEP『DOWNBEAT』で見せた変身ぶりは、いままでで最も衝撃的なものかもしれない。グランジ、オルタナを通過したダイナミックなハード・ロックという彼の個性の上に、有無を言わさずダンスを強要する冷徹でマシーナリーなビートを組み合わせた、ヘヴィーかつダンサブルなグルーヴが大爆発。小林太郎に何が起きたのか?
――驚きましたよ。ここまでサウンドの質感が変わるとは。
「クラブ・ミュージックっぽい音をやりたいって、ずっと思ってたんですよね。ケミカル・ブラザーズやナイン・インチ・ネイルズがすごく好きで……あっちで言えばビッグ・ビートやオルタナで、クラブではないかもしれないけど、クラブ・ミュージック、ダンスビートの要素をできるだけ自分のロックに付け足してあげたいなと思っていたので。いつでも良かったんですけど、前作からちょっと期間があいて、〈いろいろ変えてみよう〉と思ったタイミングで、見た目も変わって髪の毛も切って、音も変えて、ずっとやりたかったダンスビートを取り入れたロックを作ってみようと。でもひとりではできないから、プロデューサーさんに相談しながら作っていった感じです」
――それは曲の作り方を根本から変えたということ?
「作り方自体は変わらないです。ただアレンジの段階でいままで使ったことのない楽器も使うし、そこは全部お任せしました。元々アレンジしてもらう前提だから、あまり作り込まなかったんですよ。リフ、メロディー、コード、構成ぐらい。それをまったく違うふうにアレンジしてもらったものもあれば、デモをそのまま生かしたものもあるし」
――違いを一番感じたところは?
「いままでとまったく違うところは、全部エディットしてるところ。ドラムを録った後、波形のグリッドを全部揃えてるんで、これまでと聴こえ方がまったく違うと思います。グルーヴのあるロック的なリズムも乗りやすいけど、今回はできるだけクールに、ばっちりエディットしてすっきりさせる。感情に訴えるというよりは、体が自然に乗ってくるような完璧なリズムを構築したかったので」
――これをどうやってライヴでやるんだろう?ってすごく興味あるんですが。もうやりました?
「年末のイヴェントで3曲やりました。“Show me”と“Damn”、“opposite”を」
――お客さんの反応は?
「だんだん盛り上がって行く感じですね。いままでの曲だったら、イントロでギターを弾いてドラムが入って、ガツンと盛り上がるタイミングがあるんですけど、クラブの要素を取り入れたからこそ、盛り上がりがゆっくりなんですよ。抑揚がゆるやかで、ロックみたいにバン!っていかない。そこが怖くもあったんですけど、だんだん乗っていくし、演奏している感覚も全然違う。そこがほしかったんですよね。ライヴハウスでのライヴとは違って、クラブだったら朝まで行ける。いろんな目的の人がいるけど、とりあえず行って、かかってる曲が誰だか知らなくても、カッコ良かったら乗れる。知らない人でも盛り上がれるというところで、クラブ・ミュージックっていいなと思っているので。もちろんライヴハウスでやるロックの良さもあるけど、純粋な音楽の楽しみ方として、クラブが持ってる要素が魅力的だったので。その要素を持てれば、自分のライヴがもっと長時間楽しめたり、誰でも楽しめるんじゃないかな?と思ったんですよね」
――ミュージック・ビデオも作られたリード曲の“Damn”。これはどんなふうに作った曲?
「サビの〈Damn Damn〉というところから出来ていったんです。今回の歌詞は基本的に響き重視で、ひとつの感情だけをずっと歌ってるものが多いんですが、Damnといえば、クソ!っていう感じだから、じゃあそんな歌詞だろうと(笑)。いままでだったら、クソ!という思いが大サビで解決するとか、そう思うならこうしようぜとか、そういうものが多かったんですけど、今回はグルーヴに徹してます。フレーズ的にも、クラブ・ミュージックは繰り返しが多いから、自然と歌詞もシンプルな感情になるんですよね。〈やってらんねぇよ〉って言ったら、それが解決するわけでもなく、ずーっとやってらんねぇよの繰り返し(笑)。意識したわけじゃないけど、自然と歌詞も繰り返しになっていくんですよ。特に“Show me”“Damn”“Yo-Ho”とかはそう。響きと、日本語のシンプルなメッセージの繰り返し。曲がより単純になって聴きやすくなるから、ライヴで聴いた時に入りやすいし、単純なもののほうが感情の昂ぶりを促進しやすいのかなとか思ったりします」
――しかも、満たされない気持ちをストレートに吐き出した言葉が多い。
「基本的には不満なことがあって、それが解決しなくて、ただ不満だと言ってるだけです(笑)。特に考えたわけではないんですけど、自然にそうなったんですよね。たぶん音に感情が要らなかったから、歌詞も温かい感情よりは、冷たい尖った感情が出やすかったのかもしれない。でも “opposite”と“utsumi”は歌詞にストーリーがあって、どんどん前向きになっていくんですよ。最初は不満があるんだけど、それと向き合って乗り越えていく感情と、バンドの熱い音がリンクしていくようになってます」