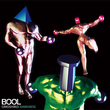連載化したMaltine主宰tomad氏の〈Lost Decade Education〉。第2回は、先日イギリスはロンドンより来日していたプロデューサー・bo en氏との対談の模様をお届けします! Maltineから2013年に『pale machine』をリリースし、その後Yun*chiの楽曲プロデュースなども手掛けて名を広めたbo en、今回の来日時には東京・MOGRAで行われたtomad主催の〈HARUSAKI〉をはじめ、東京/大阪とでいくつかのイヴェントに出演。そんな忙しい合間を縫っての取材となりました! bo en氏には初取材だったことから編集部スタッフの鼻息も荒く、対談というより彼へのインタヴューなのでは……という感じがなきにしもあらず――そんな様子を温かく見守ってくれたtomad氏に感謝。では、ご覧ください。

日本に興味を持った理由
――bo enさんが音楽を作るようになったのはいつ頃からですか?
bo en「13歳くらいの頃から趣味でバンドをやったり、自分で曲を作ったりするようになりました。高校・大学でも音楽を勉強していたので、趣味でやっていたのと仕事として取り組むようになった時期は曖昧なのですが。当初は本名のカルム・ボーエン(Calum Bowen)としてゲーム・ミュージックを作っていました」
――やはりゲームからの影響は音楽をやるようになるうえで大きかったですか?
bo en「そうですね。小っちゃい頃からゲームをよくやっていて、その音楽に触れることも多かったから。特に影響を受けたのは『塊魂』というゲームで、この音楽はゲーム・ミュージックというよりもJ-Popと言えるものだったんです。それを通して日本の音楽に興味を持つようになりました」
――へえ~、そうなんですね! ではゲーム・ミュージックから現在のようなポップスと言える音楽を作るようになったのは?
bo en「〈make believe melodies〉というブログ(日本の音楽を紹介する英語サイト)でMaltine周辺の人たち――Avec AvecやSeiho、tofubeatsのことを知って、彼らが作っている音楽はすごく僕のやりたいことに近いということに気付いたんです。もともと僕が勉強していたジャズや好きなエレクトロニック・ミュージックを良い形でミックスしていたのですごく親近感が湧きました。それで僕もやってみたいと思ったんです」
――ほほ~。それでbo enという名義で新たにスタートしたんですね。
bo en「『Super Ubie Land』っていうゲームが曲によってはヴォーカルも入っていたように、僕も典型的なゲーム音楽を作っているわけではなかったんです。だからゲーム音楽からポップスへ……といっても作る音楽がすごく変化したということではなく、単にブランドとしての変化というだけでしたね」
――それまでとまったく別のことをやろうとしていたわけじゃなく、地続きだったんですね。
bo en「そうです。すでに作っている楽曲に、もっとパーソナルなものを加えて作ろうかなという感じで。tomadさんと連絡を取り合うようになったのも、まだ本名名義だった頃です」
――tomadさんが初めてbo enさんを知ったのは、bo enさんが参加した2013年のコンピ『FOGPAK #6』なんですよね?
tomad「そうですね」
――bo enさんはそのコンピに“miss you”(その後Maltineからリリースされた単独作『pale machine』にも収録)で参加していますが、それは自身で応募して採用された……という形だったんですか?※
※コンピ〈FOGPAK〉シリーズは、毎回ひとつのテーマをイメージして作られた楽曲をみずから応募して参加する
bo en「はい。でもRedcompass(〈FOGPAK〉主宰)とは楽曲を送る前にちょっとやりとりはしていて、ちゃんと覚えてはいないのですが、Redcompassが〈やるべきだよ〉って言ってくれたことがきっかけだったと思います。その時のテーマが〈鶯の典〉だったのですが、良い楽曲が出来たので送ってみようと。僕が〈FOGPAK〉で初めての海外アーティストだったみたい」
――そうなんですね。tomadさんはそこで聴いたbo enさんの“Miss You”に心を動かされたということですが、具体的にこの曲のどういうところに惹かれたんですか?
tomad「それまで聴いたことがないというか、同じような雰囲気を持った曲を聴いたことがなくて、独特の世界観だなと思って。かつ、そんなにクラブ音楽にも寄っていなくて、かといってすごくJ-Pop的なサウンドでもなく、両者が上手くミックスされたサウンドだなと感じました」
bo en「アリガトウゴザイマス(笑)」
――『FOGPAK #6』のリリース(2013年4月)から、Maltineで『pale machine』が発表(同年9月)されるまで早かったですよね。
tomad「ホント〈FOGPAK〉を聴いてすぐにbo enへ〈リリースしませんか?〉とTwitterでDMを送りました」
――それが噂の……(笑)。
tomad「英語で送ったら(bo enから)日本語で返ってきて驚いたっていう(笑)」
――ハハハハ、それ何度聞いてもおもしろい(笑)。bo enさんはその時すでにMaltineの存在は知ってたんですよね?
bo en「はい、知っていたんですが、連絡をもらった時はあまりピンときていなくて。でもAvec Avecの作品をリリースしたレーベルだと気付いたらすぐに〈絶対やる!〉と。その前から作品をリリースしたいという気持ちはあったので、どこかのレーベルに連絡してみるべきかな?と思っていたんです」
――そういう希望はもともとお持ちだったんですね。そんなtomadさんとのやりとりから半年もしないうちに『pale machine』はリリースされていますが、収録されている曲はすでにストックされていた楽曲をコンパイルした形だったんですか?
bo en「それまでにあった曲をリアレンジしたものが主で、元の曲をそこまでいじっていないものもあれば、すごく手を入れているものもあったり……という感じです」
――Avec Avecさんやmus.hibaさんも参加されています。このお2人とはリリースが決まってから一緒に制作に入ったんですか?
bo en「mus.hibaはその前にやっていて、Avec Avecは決まってから」
――日本のアーティストとの曲制作はいかがでしたか?
bo en「日本人と組んで曲を作るのは初めてだったので、日本人が相手だから難しいと感じるのかはわかりません。ただ、僕は自分でコントロールしたいタイプだから、その気持ちが強すぎて他のアーティストと上手くやるのが難しかったのかもしれないし、日本語でやりとりをしなくちゃいけないからそれで大変だったのかもしれないし……どっちかよくわからない(笑)。mus.hibaとの作業は、僕はこうやりたい、向こうはこうやりたい、と意見が分かれてしまったので結局同じ曲(“Winter Valentine”)が2ヴァージョンあるんです。もちろんアルバムには僕のヴァージョンを入れましたが」
――一方のmus.hibaさんのヴァージョンは……?
bo en「彼のSoundCloudにありますよ。Avec Avecとの“Be Okay”は、僕が作曲をして彼がプロデュースをするという別々の作業だったのでスムースでした。日本語と英語のコミュニケーションは難しかったし、ときどき理解できないこともあったんだけど、いちばんおもしろかったのは、Avec Avecと作詞する際に彼がまったく意味をなさない英語を並べて歌った仮歌を送ってきて(笑)。本当にくだらなすぎておもしろかったんです。だから逆に僕はまったく意味のない日本語で歌ったものを送り返したりしました(笑)」
――ハハハ、楽しそうですね。そのデタラメな仮歌が聴いてみたいです(笑)。
bo en「じゃあ今度(笑)」
――また機会があれば日本のアーティストとコラボしたいですか?
bo en「もちろん。いつか椎名林檎さんや矢野顕子さんとコラボするのが夢です。でももっと現実的で、自分としてもやっていきたいのはいろんなアーティストのプロデュースをすること。この間Yun*chi(“Dancing*”)のプロデュースをしましたが」
bo enプロデュース曲“Dancing*”も聴けます
――それはいいですね! 日本のアーティストはたくさん知っていらっしゃるようですが、普段からよく聴いているんですか?
bo en「もちろん毎日聴いています。僕のパソコンに入っている曲は欧米のものが大半だけど、よく聴いているものといったら日本のアーティストがいまは多いかな。最近は80sのエクスペリメンタルなものにハマってて、仙波清彦が率いていたはにわちゃん、小川美潮、YMOをよく聴いてます」
――へ~! ちなみにそういった情報はどこから……?
bo en「ネットやYouTubeからもあるけど、いちばんは人にたくさん訊きます。特にDE DE MOUSEからよく教えてもらっていますね」
――そうなんですね、最近のものも聴いてますか?
bo en「中田ヤスタカさん関連ワークスは大好きです。あとはMaltine関連だったり、Sugar’s Campaignはもちろん、Especiaなんかもよく聴いています。オリコン・チャートの上位に入っているようなものはあまりないかな」
――ハハハ。今後入るポテンシャルのあるアーティストではありますよね。

ロンドンのシーンについて
――話は変わりますが、tomadさんが最近のロンドンのインディー・シーンがおもしろいということをおっしゃっていて、それはPCミュージックやケロ・ケロ・ボニト、もちろんbo enさんもそのなかの一人なのですが、ご自身は地元のシーンについてどのように感じていますか?
bo en「正直言って、僕はロンドンのクラブ・シーンにはほとんど関わってません。行くのはPCミュージックやケロ・ケロ・ボニト、ジャック・ダンスのパーティーくらいです。彼らと僕はエクスペリメンタルなポップ・ミュージックを作るという共通したモチヴェーションはシェアしていますが、パーソナルなレヴェルではロンドンのシーンに関わっているとは思ってません。なぜ僕が日本の音楽シーンに興味があるかというと、日本では僕のやりたいことをやらせてくれる土壌があると思っていて。欧米ではそこまで僕がやりたいことはやらせてくれないから」
――ほ~。
bo en「ただ、僕が辿り着きたいレヴェルと、実際の状況にはかなり隔たりがあると思っています。まず日本人ではないし、日本語も喋れない、日本在住でもない。日本の音楽業界の仕組みもまた壁です。でも日本には興味がある。絶対日本のほうが僕のやりたいこととニーズが一致する可能性は高いと思う」
――それは音楽的に?
bo en「そうです。僕の音楽をイギリスの人が聴くと〈日本っぽい〉と言われがちなのですが、日本だとそういうリアクションはない。そういう意味では日本での反応のほうが嬉しい」
――日本っぽいと思われてるんですか。
bo en「そうですね、〈Kawaii〉っぽいと。ほとんどのイギリス人は日本のカルチャーをそうイメージしているんです。特に僕の音楽はそういうニュアンスが強いから――ところで、イギリスでのbo enのイメージはKawaii、日本っぽいという感じですが、逆に日本だとどう思われるのでしょう?」
tomad「日本の作曲家が作ったものと比べたら違いはあるから、日本っぽいけど無国籍というか、不思議な国の音楽という気がします」
bo en「宇宙人みたいな(笑)?」
tomad「イギリス人の音楽という感じはしないし、かといってJ-Popの音楽家という感じもしないから。その間という感じですかね」
bo en「〈ヒスパニック・ジャパニーズ・アメリカン〉という感じ? 僕はジャズとラテン音楽の影響をすごく受けているから。渋谷系はラテン音楽などの要素を採り入れて日本的なポップスにしているけど、僕はそれに影響を受けてさらにラテンのテイストを入れて……と複雑なことにしちゃってる感じなんですよね(笑)」
――アハハ、なるほど! だから〈無国籍〉という印象になるんですね。しかもbo enさんの楽曲はリリックも日本語っていうところがおもしろいです。
bo en「日本語にしているのはいろんな理由があるんですが、いちばんの理由は、英語が母国語なので英語だとひとつひとつの言葉のニュアンスがリスナーにどう受け取られるかなどを気にしてしまうけど、日本語は喋れないからこそそういうことを気にせず気楽に作詞できるし歌える。もちろん日本語ができる人にとってはさまざまに解釈できると思うけど。日本語を理解できないことによって自由を感じられたし、赤ちゃんみたいに何も考えずにできる状況を楽しめたんです。あと、好きな日本の音楽シーンに近付くには日本語を使ったほうがいいので、それも大きかった」
――日本の人に聴いてもらいたいという意識が強かったんでしょうか。
bo en「決して日本の人に聴かせたいという思いだけでそうしたのではなく、〈自由に表現できる〉というのがいちばん重要でした。ドイツ語でもフランス語でも何語でも良かったけど、日本が好きだったから日本語を使ったんです。ミッションみたいに思わず、もっと自然に」
――なるほど。tomadさんは実際にこの間ロンドンでパーティーをやられて、場の雰囲気などはどう感じられましたか?
tomad「日本のMaltine周りのシーンと近い雰囲気を感じましたね。ケロ・ケロ・ボニトはDJセットだったんですが、そこでHALCALIの曲をかけてみんなが盛り上がったりしてて、僕たちと聴いてるものが同じなんだなと言う印象はありました。ロンドンのなかでも特殊な人が集まってるんだろうなという感じもあって(笑)。だからこそのおもしろさもありました。もっとテクノとかハウスのパーティーに行っていたらまた考えは変わったと思うんですが。アクティヴィア・ベンズっていうレーベルのパーティーにも行ったんですが、そこもフューチャー・ベースとかをかけていたりして、そこも似てるなと思いました。SoundCloudとかで同じタイミングで同じ音楽を聴いているからこそ、そういう一体感というか、音楽を共有できるのかなと」
bo en「どういうふうに似てるのかな? イギリスと日本とどう違うのかが気になります」
tomad「パーティーの雰囲気が近いなと思ったんです。それはこの間のイヴェントに出ていたのがSeihoやPARKGOLFだったからというのもあるんですけど(笑)、来ている人たちがみんな前を向いて盛り上がるみたいな。海外のクラブだとわりとライヴのように前を向いて聴くということはあまりないから。ライヴとDJの間みたいな感じなのかな」
bo en「インターネット音楽のシーンは日本にもイギリスにもあるけど、表現の違いは双方であると思いますか?」
tomad「そこまでの違いは感じてないです。もうちょっとイギリスにいないとわからないかもしれないけど」
――とにかくtomadさんたちと通じているものがそこにあるなという印象だったんですね。
tomad「そうですね。LAのクラブに行った人いわく、そこでも近いものがあるパーティーはあるみたいです」
――へぇ~、気になりますね。海外の同じ匂いがする人たちともどんどん交流が広がるとおもしろい気がします。ということで、そろそろ締めに入りたいのですが、bo enさんは先ほどもおっしゃっていた通り、今後もいっそう日本でも……。
bo en「そうですね、日本も視野に入れてやっていきたいです。ただ問題は海外で人気の音楽と日本で受ける音楽は両立しないこともあるので、そこは難しいなと思います。また、僕は個人的に国境関係なく世界的に自分の音楽をシェアしていきたいですが、音楽業界のシステムにおける制限もあって世界中で一様に聴かせることができない状況もあるので。それがいまのいちばんの悩みです。例えばYun*chiの作品は日本を含めて多くの国のiTunesでダウンロードできますが、USのiTunesではリリースされてないんです。僕の大半のファンはアメリカにいるのに、その人たちに聴かせることができなくて残念だった。あの曲はネット上にはどこにも存在していないから……」
――ん~、なかなか難しいですね……。先ほどもプロデュース仕事もやっていきたいとおっしゃっていましたが、bo enさんの楽曲は子供っぽいという意味ではなく、音色や音飾がキッズにも好かれそうな可愛らしさもあるので、アニメなどキッズ方面で活かされるといいなと思っています。
bo en「僕もそれを願ってますし、アニソンにはとても興味あります。さっきの話題に戻りますが、子供が楽しめそうな音楽と言われるのは、僕が赤ちゃんのように自由に表現できる状況で作ったからそう聴こえたんだと思います。それは絶対関係あると思います。アメリカのカートゥーン・ネットワークで放送されている『スティーブン・ユニバース』という作品のコンペティションに参加する機会があったのですが、ファイナリストまで進んだんだけど惜しくも選ばれなくて……。トテモザンネン」
――そうだったんですね……でもいずれそういう機会もあると思いますよ!
bo en「どこかでサインしたいです(笑)」
――大きく書いておきましょう(笑)。Maltineではまたbo enさんの作品をリリースしたり……というのは考えているんですか?
tomad「他のMaltineのアーティストとコラボレーションするのとかおもしろそうだなと思ってます!」