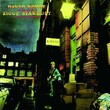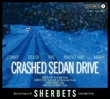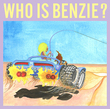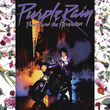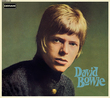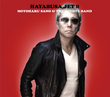『★』でボウイの音楽に〈リアルタイム性〉を初めて意識しました(小林)
浅井「『地球に落ちてきた男』って映画(ボウイが初主演した76年作)あるじゃないですか。あれ全然意味わからんかったけどね(笑)」
土屋「いや、あれ最高だよ! あれと、みんな言わないけど『ハンガー』(83年)は素晴らしいですよ。吸血鬼になっちゃうやつ。映画俳優としてのボウイは、ニュースではせいぜい〈戦メリ〉(83年作『戦場のメリークリスマス』)しか触れられないけど。でも音楽はもちろん、映画でもすごく影響力があったんだよね」
浅井「〈ラビリンス〉(86年作『ラビリンス/魔王の迷宮』)とか」
土屋「あれも良かったね。いっぱいやっているんだよね」
――舞台「エレファント・マン」(80年)など、ボウイは俳優業にかなり力を入れていた時期もあったわけですが、土屋さんはどうご覧になっていたんですか。
土屋「いやもう、めちゃくちゃ格好良いと思っていたし、当然そうなる(俳優業に力を入れる)だろうなっていう。すごくブレヒト(ベルナルド・ブレヒト:ドイツの劇作家。1956年没)に傾倒していたからね。ブレヒトの芝居もやってるんですよ(82年作『BAAL』)。ジギー・スターダストを名乗る前は(68年に)リンゼイ・ケンプのパントマイムの学校に通っていたし。舞台の上に立つ人間がどうあるべきかっていうのをすでに学んでいたからね」
――デビューして泣かず飛ばずの雌伏の時に、音楽修行をするのではなくパントマイムを学ぶって発想が際立ってますよね。
土屋「革新的ですよね。ジギー・スターダストだって演劇じゃないですか。演劇的な脚本が頭の中に出来ていて、そのために自分の身体をそういうふうに作り変えていく。手足の動かし方をちゃんと学んで。だから俳優業に傾倒していくのは当然だった。第一、舞台とか映画の人は放っておかないでしょう、あれだけのキャラの人を。演技力も、見た目のカリスマ性も」
――土屋さんはボウイのベストはどのアルバムだとお考えですか。
土屋「ピークは『Low』や『Heroes』だと思うんですけど、それはサウンド面だけの話じゃない。そこでボウイが言いたかったのは、資本主義に対するアンチテーゼなんです。そういう政治的/思想的なことを直接的には口に出さないけど、ヒントは音楽のあちこちに散りばめてある。『Low』は、世界がなぜナチズムに傾倒していったかという考察が根底にある。それをミュージシャンだから凄く楽しんだんじゃないですかね。政治家だったら物凄くシリアスになっちゃうでしょ。でも音楽家として、ひとつの要素としてそれを持ち込んだ。ベルリンの壁のすぐ脇のスタジオで、ロバート・フリップとイギー・ポップとブライアン・イーノとデヴィッド・ボウイが一緒にいる。それだけで意味があるわけですよ。それが完璧に資本主義に対するアンチテーゼとして作品化されるということですよね」
――あからさまなメッセージにしない、というのは確かにそうですね。
土屋「気付いた人だけわかればいい。言葉にする責任もあるでしょ。ボウイからは、なにを学んだらいいのかを凄く教えてもらった。勉強しないと追いつかないんだよね。シュールレアリズムや表現主義、資本主義とは何かとか。当然そのへんの文献に当たるじゃないですか。〈これって何だろう?〉ってところから、バーッと興味が広がっていく」
――ロックを通じて世界を見る、そういう見方を植え付けてくれた。
土屋「うん。音楽の大事な仕事のひとつに、それは絶対ある。(現代は)売れればいいやって姿勢があまりに多すぎちゃって、音楽が本来やるべきことがなされていない。音楽が伝える力ってすごく重要ですよ」
――そういう意味でボウイの影響力は大きい。それはレコードの売り上げとは必ずしも関係ない。
土屋「ボウイに影響を受けてミュージシャンになったり、アートをやるようになったり、要は文化に携わるようになった人がどれだけ多いかってことですよね。そういう影響力を持ったのは(ロック・ミュージシャンでは)ビートルズが最初でしょうけどね。ボウイの影響力も本当に大きい」
――浅井さんはボウイの作品でどれが一番お好きなんですか。
浅井「アルバムは〈Ziggy Stardust〉、曲は“Blue Jean”が好きかな。ディスコで踊ってました。
――(地元である)名古屋の?
浅井「うん、名古屋の(笑)。あれがかかると踊るよ」
――ボウイの魅力って何ですか。
浅井「カッコイイとこだね。凄いじゃん、ライヴも。完璧で。世界にデヴィッド・ボウイが存在してなかったらめちゃくちゃ寂しいんじゃない? 音楽シーンが」
土屋「ベンジーから見ても、ああいうライヴってカッコイイと思う?」
浅井「思う」
土屋「ああ、それは凄いな。(浅井の)やってることって(ボウイとは)全然逆……じゃない?」
浅井「ああ、そうですね」
土屋「ベンジーの場合は、(ステージに)上がって、ただ純粋に自分の歌を歌う。ボウイの場合は……」
浅井「完璧に作り込んで」
土屋「第一歩からもう計算してる」
浅井「エンターテインメントだけじゃなくて、(歌詞で)言ってることがカッコイイと思うし」
――ボウイみたいなアーティストになりたいとは思わなかったですか。
浅井「なりたいと思ってもなれんでしょう、ルックス違うで(笑)。ボウイの真似しとる人めっちゃくちゃおるよね、日本でも」
土屋「僕はノッティング・ヒル・ゲート(ロンドン地下鉄の駅)で(ボウイを)一度見かけたことあるけど、普段はわりとベンジーみたいだったよ(笑)。ゴム草履みたいなのを履いて(笑)。だから作ってる部分もありますよね」
――私も1回だけ取材で会ったことありますけど、すごく気さくで気遣いする人という印象でした。ボウイみずから、われわれにお茶を煎れてくれて。
浅井「うん、だってモーツァルトも気さくだったもん」
土屋「なんか友達みたい(笑)」
浅井「映画で観ると(笑)」
――小林さんはボウイではどれが一番好きなんですか。
小林「一番好きってことだと……やっぱり『Low』かもしれないですね。思い入れもあるけど。あと『★』も物凄く、本当に好きですね。ミュージシャンとしての自分にフィットしたというか、リアルタイムで体験したアルバムだし。ボウイっていうのを置いといても、ケンドリック・ラマーやディアンジェロとか、去年~一昨年ぐらいから(自分が)凄く好きなテイストの音楽が出てきて、まさかボウイもこういう感じでくるとは思わなかったので」
――詳しくお話いただけますか。
小林「そうですね……。まずは〈ボウイの新譜〉というだけでワクワクして、かなり期待度を高くして聴くじゃないですか。で、1曲目(“Blackstar”)を聴いた時点で……僕、スコット・ウォーカーが凄く好きなんですけど、そういう深遠な、みぞおちを抉られるような世界観で始まるところで一気に引き込まれて。で、4曲目の“Sue (Or In A Season Of Crime)”で、まさかと思った。少し前からあった曲じゃないですか」
――先にリリースされたベスト盤(2014年作『Nothing Has Changed』)に別テイクが収録されてましたね。
小林「そう。〈この曲がこのアルバムに入るんだ〉という意外性もあったし。なにより最近の新しいジャズのミュージシャン、ドラムのマーク・ジュリアナとかも参加していて、物凄く衝撃的だったけど、これは自分のいま欲しい音であり、ちょうどフィットする感じの音だったんですよね。タイムリーというか、ボウイの音楽に〈リアルタイム性〉みたいなものを初めて意識したんですよ」
小林「もちろん素晴らしい作品は(過去に)いくつもあったけど、それは当時の音を振り返って聴くような感じだったんですね。3年前に出た『The Next Day』の時も、凄い作品とは思ったけど、リアルタイム性から言うと、〈伝説のミュージシャンによる素晴らしい新譜〉ぐらいにしか思わなかった。でも今回の『★』に関しては、間違いなくリアルタイム性を感じて、いまの自分が欲しい音だと感じたのが、一番これまでとは違かったところですかね。だからだと思うんですけど、それまでボウイにあまり関心がなかった僕の友達も凄く反応して。〈ボウイの新譜聴いた?〉と連絡が来たり。同世代の友達とボウイのことを話すのも初めてのことだったんです」
――馴染みの薄い、しかも畑の違うミュージシャンを使うのは勇気がいると思います。しかも全員。
土屋「あのね、音楽って達観すると絶対そこに行くの。それこそ、得意の分野じゃない楽器を弾いてもらうっていうのが、最高のレヴェルなんですよ。それを最初にやったのがビーチ・ボーイズの『Pet Sounds』(66年)です。あのアルバムがなんで素晴らしいかというと、各界の達人を呼んできて、その(担当の)楽器じゃないものを弾かせるというね。それがブライアン・ウィルソンの天才的なところで。バーニー・ケッセルという当時最高のジャズ・ギタリストを呼んで、マンドリンを弾かせるとか。細野晴臣さんも言ってました、〈天才的なミュージシャンにやったことのない楽器をやらせると、物凄い効果が出る〉って。だから細野さんもマリンバやハモンドとかを自分で弾くじゃないですか。得意じゃないからいいんだよと」
――でも失敗する可能性もあるわけですよね。
土屋「失敗しないですよ、どう転んでも。天才的なミュージシャンなら。やらされるミュージシャンからすれば、物凄くワクワクしますよ。ヴィスコンティが言ってましたよね、ロックの人たちにジャズっぽくやってもらうよりも、ジャズの人たちにロックっぽくやってもらったほうがずっと効果的だと。ボウイ自身もそれはずいぶん前からわかっていたと思う」