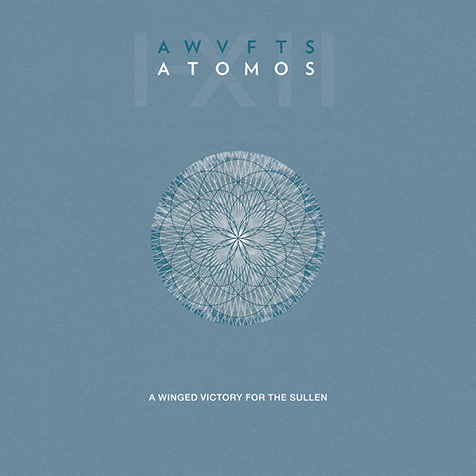音楽は紙の上に座っているだけでは意味がない
――ニルス・フラームやピーター・ブロデリックも参加したAWVFTSのデビュー作『A Winged Victory For The Sullen』は、本当に美しいアルバムだと感じました。作曲や制作はどのように進められたのでしょう?
ダスティン「僕らにとってもすごくスペシャルな作品だよ、これからもね。当時はアルバムを作っているという認識すらなかった」
アダム「まだ(ユニットとして)存在すらしていなかったからね」
ダスティン「どんなサウンドにするのかも考えていなかったよ。レコーディングのセッションをいくつか組んだんだけど、アルバムの制作についてはアドヴェンチャーしながら進めたいと思っていた。それを実践したのが、特定のアンビエンスを出すために、特定の場所に出向くということだった」
アダム「僕らが〈アンビエンス〉と呼んでいるのは〈(音響的な)空間〉のことさ」

ダスティン「レコーディングの一つはベルリンの教会で行った。1500~1600年代に建てられ、戦後に改築された教会で、素晴らしいピアノが置いてあって、リヴァーブも長く響くところでね。そこではたくさんのデモをレコーディングした。あとは東ドイツ(時代)のラジオ局だったフンクハウス。1950年代に建てられた格別な音響環境のスタジオで、ストリングスが本当に美しく録音できるんだ。それに、とあるファツィオリのピアノを使ってレコーディングがしたかったのでイタリアに出向いたりもしたよ。移動が多かったけど、いろいろな環境を試しながら録音することができた。そして最後に、1400年代からあるイタリアのフェラーラ近くのヴィラですべてをミックスした。やってくれたのはフランチェスコ・ドナデッロ、最初に僕らを紹介してくれた彼ね。言うならば、このユニットのシークレット・メンバーみたいなものかな。彼はアナログ作業にこだわりのある人間だから、僕らの素材も全部ミックスしてテープに落としてくれたんだ」
アダム「僕にとってもすごく解放的な経験だったよ。仕事だと思うことはまったくなかった。なにせ僕らはまだ存在していなかったから、レーベルとのしがらみもないし、プレス対応だってない。大の男2人で美しいものを作ろうとしていた、それだけのことさ」
――いま、録音環境の話があったので訊きたいのですが、次のアルバム『Atomos』でも、ブリュッセル、ベルリン、レイキャビクと世界中を回りながらレコーディングしていますよね。だから、録音環境をまるで一つの楽器のように捉えているかのような印象を、いまの話で受けましたが。
アダム「その通りだね。これまで多くのレコーディングをしてきたけれど、ある程度時間が経つとそういうのが必要になるんだ。何か特別なものをもたらしてくれる、古い友人に会いに行くような要素がね。音楽を作っていても、それがただ紙の上に座っているだけでは意味がない。命を吹き込んでやらないと」
ダスティン「スタジオに長時間籠っていると、そのスタジオの音に飽きてくるんだよ。別の空間に行くことでサウンドにユニークなアイデンティティーを持たせることもできるし、違う形で生命を持たせることができるようになる。あるピースをそのまま別の空間に持って行ったら全然違うように聴こえたりすると、驚かされるものさ。アダムと僕はいつも音響に対して貪欲なんだよ。音符を多用するわけではなく、音楽もミニマルで複雑ではないけれど、だからといってプラグインを使って満足するようなことは絶対にしない。とにかく外に出掛けて、ユニークな音を捉えたいんだよ」
――その『Atomos』はウェイン・マクレガー※からの依頼で制作されたわけですが、制作に至るまでの背景を教えてもらえますか。
※英国ロイヤル・バレエ団の常任振付師。レディオヘッド“Lotus Flowher”やケミカル・ブラザーズ“Wide Open”のミュージック・ビデオのダンスも振付けしている。
アダム「彼が前作を気に入ってくれたんだ。だから、スコアをやってほしいと言ってくれて。『Atomos』は確かに僕らが制作したものではあるけど、ウェインはかなり深く関わってくれたよ。でも、僕らが好きなようにクリエイティヴにさせてくれた。そこが彼の素晴らしいところで、作業もすごくしやすかった。もちろん依頼された仕事ではあったけれど、不思議な作品に仕上がったね」
ダスティン「あの時点では、僕らもまだ1枚しか出していなかったし、経験もそれほど多く重ねていなかったから、制作メソッドというものが確立されていなかった。そういう点においても、ウェインとのコラボレーションはいいものだったよ。なんせ前作は制作に2年も費やしたのに、この作品は3か月だったからね。ウェインからは音楽についてのディレクションというのは一切なくて、ダンスの観点から、どちらかというとコンセプチュアルなアイデアをくれた。宇宙空間や不思議な形象の写真や絵、あるいは60年代のサイエンス・ビデオなんかを送ってきたりして。それによって、僕らも自分たちのサウンドをより深く探求することができたし、彼のほうもそれを望んでいた。自分たちがどういうことについて作曲しているのか、考えながら作業してほしかったんだね。とてもナイスな方法だったよ」
――『Atomos』はどことなくエレクトロニックな質感も印象的でした。
ダスティン「でも、聴こえてくる音の大半はアダムのギターだよ。あるいはピアノの音を加工して作った音だったり。よく音を加工して、自分たちだけの音を作っているんだ。すごく時間はかかるけどね。古いシンセの音をシークエンスさせている部分もあるけど、それはごくわずかだよ」
――そうやって生楽器で電子音のようなテクスチャーを作り上げているのも興味深いです。ポスト・プロダクションにもこだわりが強い?
アダム「まったくもってその通り。ファイナル・ミックスこそ、僕らのすべてだよ。古式のリール・トゥー・リール・タイプのアナログ・ボードを使って、僕らにしっくりくるサウンドにしている。どうしてかわからないけど、それが心地良いんだ。クレイジーな2人だからかな(笑)。エンド・プロダクトに到達するまでは、とても長い道のりを辿っているよ」
ダスティン「さっき話したように、わざわざ特定の音響環境に出向いてレコーディングをすると、なおさらミックスは重要なものになってくるんだ。というのも、そのミックスそのものがある意味で立体的な空間になり得るから。幸いにも僕らのエンジニアは素晴らしくて、まさにそれを実現してくれている。その空間を僕らはいつも追求しているんだよ。現代音楽はコンプレス(圧縮)されたものが多いけれど、僕らのミックスにはほとんどコンプレッションは使っていない。だから、使っているレコーディング・テクニックは旧式かもしれないけれど、音のダイナミクスやスペースはきちんと確保されているんだ」
美しいイメージを持つことができたら、作曲の半分はこなしたと言える
――アダムは11月に、ソロ作として『Salero』という映画のサウンドトラックをリリースしますよね。これはどういう経緯で作られることになったのですか?
アダム「あれはただ、たまたま誰かのお眼鏡に適って仕事の依頼があっただけの話だよ(笑)。いつも背景に感動的ないきさつがあるわけじゃない、ただの業務依頼ってことも多々あるわけさ。そして、そうやって請けた依頼のエンド・プロダクトを自分で気に入ることもあれば、そうではないときもある。今回の件で言えば、どちらかというとラッキーだったかな。しかも、イレースド・テープスから出してもらえることにまでなったし」

――音を作るにあたって、映画からインスパイアされた部分が多かったのかなと感じましたが。
アダム「もちろんさ。どんな映画でもそうだよ。映画のおもしろいところはそこで、作品によってその語りかけ方も異なってくるんだけど、今回の作品はボリビアの世界最大の塩湖についてのドキュメンタリーで、とにかく圧巻。非常に美しい場所だ。これだけは言えるんだけど、作曲をするときに美しいイメージを(頭の中に)持つことができたら、それだけで作業の半分はこなしたと言えるね。イメージというのは本当に重要なもので、作業をするときにヴィジュアルの要素があれば、それだけで仕事に大きな差が出てくる。しかも、それが美しく録画されたものなら、何もかもが変わってくるぐらい。だから、今回の作業はかなりやりやすかったよ」
――音でそのイメージを表現するうえで、どういったことを心掛けましたか?
アダム「特にないかな。一般的な映画であれば、だいたい1本の作品につき20~30のキュー(シーン)に音楽をつけることになるわけだよね。より含みを持たせたり、深い繋がりを表現してほしいと監督側から示唆されることもあるし、それが上手くはまらなかったりすれば、別のランダムな方法を試す必要が出てくる。そうなると、(作業をしている)2~3か月の間はちょっとクレイジーなことになるんだ。いろいろと変更され続けるし。すべてがそうとは言わないけれど、今回については締め切りもかなり差し迫っていた。だから、僕も実際に現地に行って有意義な経験をさせてもらえたとは思うけど、(この仕事について)必ずしも素敵な話ができるかと言えば、そういうわけでもないんだよ。ダスティンと僕で最初のアルバムを作っていたときなんかは、ひたすら楽しくてストレスもゼロだったけど、映画のスコアは……まあ真っ当な生活もできているし、楽しくないとは言わないよ。でも、仕事は仕事だよね」

――AWVFTSとしても、映画のスコアを元にした3作目『Iris』をリリースするんですよね。どういった感じの作品になりそうですか?
ダスティン「映画はロマンティック・スリラーみたいな、かなりフレンチでパリジャンな作品だよ。監督にはかなりコンテンポラリーなサウンドを求められた。その結果、音の大半はモジュラー・シンセとオーケストラで構成されている。ピアノはほとんどないし、ギターも少しだけ。初作からはちょっと離れた仕上がりだよ。70年代に使われていたブックラという、モーグのような初期のシンセだったりとか、昔のテクノロジーをたくさん駆使している。ブダペストではオーケストラのレコーディングもした」
アダム「『Salero』でストリングスをやってくれたのと同じオーケストラね」
ダスティン「あとはハープなんかも少し採り入れているよ。ある意味まだミニマルではあるものの、ストリングスは規模が大きくなっているし、エレクトロニクスもまた違うスタイルを導入したんだ。早く聴いてもらいたいよ。とても満足のいく仕上がりではあるけど、確かに新しい領域への試みでもあった」
――ちなみに、2人が好きな映画のサウンドトラックは?
ダスティン「ちょうど先週ブリュッセルにいたときに、ニーノ・ロータによる『カサノヴァ』のサントラをアナログ盤で買ったんだ」
アダム「ああ、あれは最高だね」
ダスティン「フェリーニとかね。とにかく大好きなサントラだ」
アダム「僕はもっとモダンなやつでいくよ。(音楽)出版社が一緒ということで友人になったデヴィッド・ジュリアンという作曲家がいるんだけど、クリストファー・ノーラン監督の『プレステージ』という2人の憎み合うマジシャンたちの話を描いた映画のスコアを彼が手掛けていて。まったく信じられないくらい素晴らしい作品だと思う。どうやって作ったのか検討もつかないけれど、とにかく大好きだね」
――最後に、〈A Winged Victory For The Sullen〉という長いユニット名の由来を教えてもらえませんか?
アダム「秘密だから、それは言えないね(笑)」
ダスティン「でも言ってみて。みんなが上手く発音できるか、あちこちで試しているんだ(笑)」
アダム「だいたいこの名前、日本語に訳せるの? 今度はこっちがインタヴューする番だ(笑)。〈Wing〉が〈羽〉、〈Victory〉が〈勝利〉なのはわかるよね。〈Sullen〉はわかるかい? 頭のうえに雲が立ち込めているような状態のことだ。あとは、〈ゆっくり動く〉という意味もある」
ダスティン「ルーブル美術館に同じような名前のギリシャの像があるよ。あ、〈Sullen〉の部分は違うけどね※」
※〈サモトラケのニケ(The Winged Victory of Samothrace)〉のこと