
音楽ライターの八木皓平が監修を務め、〈ポスト・クラシカル〉と〈インディー・クラシック〉 という2つのムーヴメントを柱に、21世紀以降のクラシック音楽をフィーチャーする連載〈Next For Classic〉。2016年からスタートした本連載も今回でついに10回目を迎えた。ひとつの節目と言うべき本稿において、八木は2018年にリリースされた作品のなかから〈ネオ・クラシカル〉の現在地を象徴している10作を選盤。各作品ごとの音楽性やユニークな魅力を考察したレヴューと合わせて、ここに掲載する。記事の最後には、八木が〈華々しいスタートを切った〉と評価する2019年の(現時点での)様相も紹介。これを読むと、たえず更新されているシーンの〈いま〉がわかるはずだ。 *Mikiki編集部
★連載〈Next For Classic〉の記事一覧はこちら
ポスト・クラシカルやインディー・クラシックを含む、クラシック~現代音楽の現代的な展開であるネオ・クラシカルの2018年は、ニルス・フラームの4年ぶりの新作『All Melody』とヨハン・ヨハンソンの早すぎる死からはじまった。このふたつの出来事についてはそれぞれ〈Next For Classic〉の連載で扱ったのでそちらを読んでいただきたい。このシーンを追っていた人間たちにとっての2018年は、そのはじまりにおいて、喜びと悲しみをほぼ同時に味わうことになった。
ただ、2018年を終えたいまとなっては、この年はクラシック~現代音楽の要素を用いて自身の音楽をアップデートしようとした音楽家たちの意欲作が数多く見られた。実際、ここでリストアップしたもののほとんどが、そういう作品になっている。
また、2018年は近年においても突出して、クラシック~現代音楽が他ジャンルの音楽とのミックスした年であったとも言える。これはネオ・クラシカルが音楽シーン全体に〈浸透と拡散〉した結果だ。音楽シーンに漂うこの空気感を可視化することも、この年間ベストの目的であり、ここで挙げた10枚はそれぞれが現ネオ・クラシカル周辺において何らかの象徴として機能するように配置したものだ。俯瞰的ではあるが、網羅主義的ではないため、ネオ・クラシカル・シーンに興味のない方々でも、きっと自分の愛する音楽となんらかの繋がりを見出しやすいと思う。
10. 蓮沼執太フィル『ANTHROPOCENE』
2018年にアルバム一枚を使ってチェンバー・ミュージックと向かい合った日本の音楽家といえば、蓮沼執太だろう。彼は曲者ぞろいのメンバーを擁する蓮沼執太フィルと共に、前作『時は奏でる』(2014年)から4年半ぶりとなる新作『ANTHROPOCENE』をリリースした。蓮沼執太については、エレクトロニカの作曲家としての彼を好きだった人間は蓮沼執太フィルを敬遠しがちなところがあるのだが、彼らの音楽を聴いたあとに、あらためてエレクトロニカ作品を振り返ってみると、音色の配置などに〈フィル〉に通じる部分があることがわかる。彼の音楽は潜在的にチェンバー・ミュージックを志向していたと、いまとなっては思える。
蓮沼執太の作曲は前作時よりもはるかにヴァリエーション豊かになり、緻密さも備え、その世界観はより強固なものとなった。大きく前進しているように感じたのはリズム隊の、特にドラムの音色や間の取り方。それと全体の構造が連動することでグルーヴが生まれ、そこに環ROYのラップがハマったときの独特のサウンドは、世界的に考えてもあまり類例を見ない。ポップ・ミュージック界隈のチェンバー・ミュージックでドラム/パーカッションがユニークだったものに、ロンドン在住の音楽家カイル・オウルズによるプロジェクト、ヒー・ワズ・イートゥン・バイ・オウルズの2作目『Inchoate With The Light Go I』があった。こちらは、どちらかといえばポスト・ロック~マス・ロック風のものだが、ラフな部分も含めて興味深い音源なので一聴に値する。
現在の国内のチェンバー・ミュージックを眺めると、去年リリースされた網守将平『パタミュージック』は、彼の才覚やポテンシャルが無軌道なまま放出されることで生まれた極めて特異なチェンバー・ミュージックで、オリジナリティー溢れるものだった。また、こちらはオーケストラ作品だが、くるりの岸田繁による管弦楽作品『交響曲第二番』が3月27日(水)にリリースされるようだし、渋谷慶一郎が作曲を手掛けるアンドロイド・オペラ「Scary Beauty」は2020年に新作が公開されるらしく、そちらも楽しみだ。ただ、日本におけるチェンバー・ミュージックの作り手ということでいえば、まだまだ頭数やヴァリエーションが少ないというのも本当のところだ。このシーンは引き続き注視していきたい。
9. ジョーダン・マンソン『Until My Last』

アメリカを代表するロック・バンドであるウィルコが、2018年リリースのアルバムを集めたレコメンド・リストを昨年末に発表しており、その幅広いジャンルを網羅したセレクションは、インディー・クラシックの総本山であるニュー・アムステルダムからはティグー(Tigue)の『Strange Paradise』とジョーダン・マンソン『Until My Last』がセレクトされている。彼らはどちらもパーカッションによる演奏をバックグラウンドに持っているが、2枚の新作においてその音楽的な方向性はまったく異なっていた。ティグーはリズミックなポスト・ロック・サウンドの随所にアンビエント/ドローンを配合。その一方、ジョーダン・マンソンはパーカッションの中心的な構造である点描性をいくぶん保持したうえで、電子音響~エレクトロニカと声楽とを融合してみせた。
クラシック~現代音楽といったとき、どうしても管楽器や弦楽器を中心に考えがちなところはあるが、タイヨンダイ・ブラクストンの近作がそうであるように、そこには当然パーカッションや声楽の要素も入ってくる。それがインディー・クラシックではどのような展開があるのかを考えたときに、ティグーやジョーダン・マンソンらの活動は重要である。
ここでティグーではなくジョーダン・マンソンの新作を中心的に取り上げる理由は、ブーツやサン・ラックスと仕事をした経験のあるハンナ・ベンが作曲に参加していることと、電子音響~エレクトロニカの要素をサウンドに導入しているという2点にある。声楽を学んでいたハンナ・ベンは、ポレンズというバンドの結成メンバーでもあり、声楽という出自を持ちながらも幅広い音楽活動を展開してきた。『Until My Last』ではジョージ・マンソンと〈Anew〉シリーズを共同作曲しており、ヴォーカルも担当している。以前の年間ベストで紹介したガビ(昨年に新作『Empty Me』をリリース)やマイ・ブライテスト・ダイアモンドなどとともに、インディー・クラシック・シーンにおいては数少ない女性シンガー・ソングライターとして注目したい。
また、インディー・クラシックは器楽的な要素がサウンドの中心にあるが、ニコ・ミューリーが実践してきたように、電子音響~エレクトロニカを巧みに導入することで新たなテクスチャーを獲得しえることも『Until My Last』は示している。それも重要な点だ。
8. アクトレス×ロンドン・コンテンポラリー・オーケストラ『Lageos』
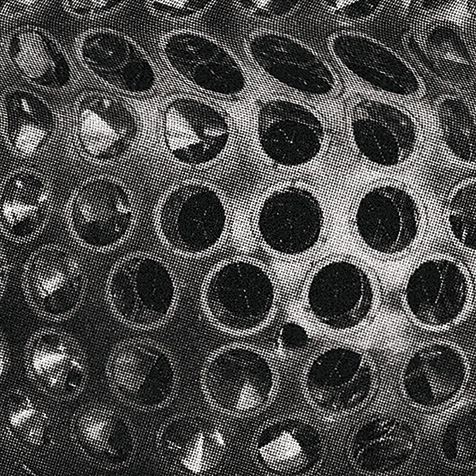
ACTRESS,LONDON CONTEMPORARY ORCHESTRA Lageos Ninja Tune(2018)
オーケストラとのコラボレーションを積極的におこなうエレクトロニック・ミュージシャンといえば、ジェフ・ミルズやカール・クレイグといったデトロイト・テクノのレジェンドがすぐに思い浮かぶ。また、クラシックの名曲をエレクトロニック・ミュージック以降の感性で再解釈しようという試みの代表的なものに、ドイツの老舗クラシック・レーベル、グラモフォンの〈リコンポーズド・シリーズ〉があり、そこでは(マシュー・)ハーバートやクリスチャン・フェネスがマーラーの交響曲を、カール・クレイグがモーリッツ・フォン・オズワルドと組んでムソルグスキーやラヴェルの楽曲をリコンポーズした。また、オーケストレーションを活用しながらエレクトロニック・ミュージックにアプローチしようとする、クラシックの訓練を受けた音楽家は、さまざまなところにいる。
オーケストラを通じた、クラシックとエレクトロニック・ミュージックの出会いは、いまやそこまで珍しいものではなくなっているということは、ここであらためて述べておきたい。今回のアクトレスとロンドン・コンテンポラリー・オーケストラ(LCO)によるコラボ作品『Lageos』はその優秀な最新例のひとつと言っていいだろう。いまもっとも刺激的なテクノ・ミュージックを作り上げるアクトレスが、レディオヘッドのジョニー・グリーンウッドやアーケイド・ファイア、フランク・オーシャンともコラボレーションを展開するLCOと手を組んだ本作は、LCOが各パートの音源をレコーディングした後でアクトレスに送り、その音源をアクトレスがリコンポーズして制作されたものだ。
エレクトロニック・ミュージシャンがオーケストラとコラボレーションする際にポイントとなるのは、基本的にはオーケストラの演奏のレイヤリングとエディットだろう。レイヤリングはオーケストレーションにビートやエレクトロニクスを被せること、エディットはオーケストレーションを裁断して繋ぎ合わせることと考えていい。このふたつをいかに上手く組み合わせるかがポイントとなってくる。オーケストラの存在感が強すぎるとエレクトロニクスが単なる添え物のように思え既視感を拭えないし、その逆だとオーケストラとコラボレーションすることのダイナミズムが失われてしまうからだ。事実、同様の方法論を採用して罠にハマってしまっている作品は多い。しかし、アクトレスは本作でそれらを上手くこなしており、このチャレンジがムリゲーでないことを証明するとともに、自身の音楽性の懐の深さをマッシヴな形で提示してみせた。
7. ミゲル・ゼノン『Yo Soy La Tradicion』

近年におけるジャズとクラシックの関係性の深まりについては、このシーンをディープに追っているわけではないぼくにも、存分に伝わってきており、2018年もじゅうぶんに興奮させられた。それはECMとポスト・クラシカルの類似性だけではなく、例えばカマシ・ワシントン『Heaven And Earth』、アンブローズ・アキンムシーレ『Origami Harvest』、挟間美帆『ダンサー・イン・ノー・ホエア』の3枚を並べただけでも、その質の高さとヴァラエティーの豊かさには驚くばかりだ。なかでもひときわおもしろく聴けたのがミゲル・ゼノンの『Yo Soy La Tradicion』。彼がストリングス・カルテットを従えた本作を聴いていると、ストリングスやサックスの自由な空間配置がもたらす音響的なおもしろさや、多彩な展開がアルバム全体にもたらす〈浮遊感〉に耳がとらわれ、この感覚はベースやドラムが入っている作品ではなかなか感じることができないと気づかされる。
特に低音域をどのように響かせるかが課題である現代のポップ・ミュージックでは、ベースやドラムは、ある意味では鼓膜に楔を打つような役割を背負っており、そのパターンによってぼくたちは快楽を感じる。だが、『Yo Soy La Tradicion』におけるストリングスとサックスがもたらす浮遊感はそれとはまた違った快楽をもたらす。“Promesa”の終盤におけるストリングスの絡み合いとリフレインを聴けば、その新鮮さがわかるのではないだろうか。
また、本作がおもしろいのはそこだけではなく、旋律に寄りすぎるわけでもなく、エフェクティヴな不協和音やドローン/アンビエント的なサウンドにいくわけでもない絶妙なラインをいく演奏も実に優れている。そういった要素も本作にモダンな香りを感じさせる一因だろう。例えば、ジャズと距離が近いもので、ここ数年でおもしろかったストリングス・カルテットの試みとしては、ミゲル・アトウッド・ファーガソンのカルテット・ファンタスティコがあったが、あれはインプロヴィゼーション~現代音楽寄りな部分があるため、本作とはまた違う。どこにも寄りかからずに淡々と独自の道を歩んでゆく『Yo Soy La Tradicion』のサウンドは清々しく、どこかしなやかな力強さと凛とした凄みを感じさせる。
6. ダニエル・ブラント『Channels』

DANIEL BRANDT Channels Erased Tapes(2018)
ミニマル・ミュージック、特にスティーヴ・ライヒに惹かれる音楽リスナーにとって、ドイツ出身のトリオ、ブラント・バウアー・フリックの存在は避けては通れないものだったと思う。彼らは、ミニマル・テクノとミニマル・ミュージックを融合させ、クラブ・カルチャーと現代音楽の垣根を乗り越えた。
『Channels』はそのメンバーの1人ダニエル・ブラントのソロ2作目であり、トリオ時同様にミニマル・ミュージックが本作の核だ。このアルバムはポスト・クラシカルの代表的レーベル、イレースト・テープスからリリースされているが、ニルス・フラームやオーラヴル・アルナルズといったポスト・クラシカルの代表選手と共有する要素はあるものの、かなり方向性の違うサウンドになっている。そもそもミニマル・ミュージックを追求するクラシック~現代音楽家は、私見ではインディー・クラシックの側だ。本作に収録されている“Ltd”に、アイスエイジやマシュー・ハーバート、オーウェン・パレットなどとコラボレーションを展開してきたアンサンブル、スターゲイズが参加していることなどからも、それは言える。
ただ、本作はピアノがアンビエント的に使われているのが特徴であり、そういう意味ではポスト・クラシカル的な部分もあり、ダニエル・ブラントはポスト・クラシカルとインディー・クラシックの結節点とも言えよう。ミニマル・ミュージックの現代的展開といえば、海外の音楽よりも、去年新作をリリースした東京塩麹やMaison book girlといった国内のアクトに着目するのがおもしろい。東京塩麹はブラント・バウアー・フリックの影響を受けており、ミニマル・ミュージックをベースにしたヴォーカル曲やダンス・ミュージックを作り上げ、そのユニークなセンスで注目を集めている。また、Maison book girlはスティーヴ・ライヒ的なサウンドをアイドル・ミュージックに読み替えるとともに、ステージングの際のヴィジュアルが池田亮司やカールステン・ニコライ的な趣がある極めて特異なアイドル・ユニットだ。ダニエル・ブラントの作品をこういったアクトと並列して聴くことで見えてくるものもあるだろう。






















