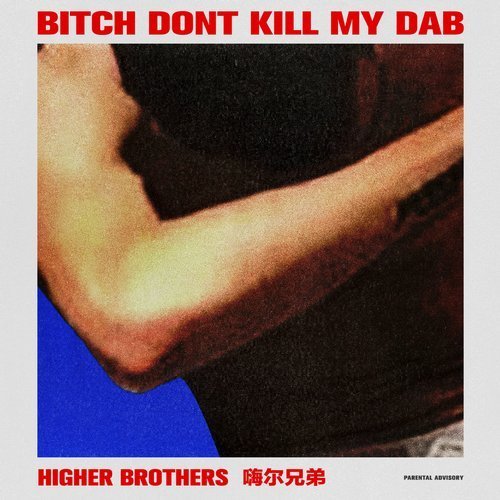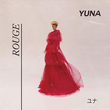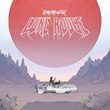■ハイアー・ブラザーズ『Bitch Don’t Kill My Dab』(中国)
ここ数年、強烈におもしろくなっているのが中華圏のアンダーグラウンド・ラップ・シーンです。ウソだと思うなら、〈#1 Spot For Chinese Hip Hop〉を謳うYouTubeアカウント〈Zhong.tv〉をチェックしてみてください。中国~台湾~国外の中華系のビデオクリップが尋常じゃない量アップされており(ほぼ毎日新しいビデオクリップが公開されている!)、まずはその量に圧倒されます。また、トラップなどUSの流行を貪欲に採り入れたサウンド、初期衝動とローカル感満載の映像が凄まじいインパクト! いつの間にかこんなことになってたんですね。ちょっとビックリです。
そうした中華圏ラップのなかでもジワジワと世界的な話題となりつつあるのが、四川省の成都(チェンドゥ)を拠点とするラップ・グループ、ハイアー・ブラザーズ。YouTubeにはナードなんだかサグなんだか判断しかねる彼らのビデオクリップが数多くアップされているけれど、かのキース・エイプを擁するアメリカのアジア系レーベル、CXSHXNLYがこの曲を配信していることからもわかるように、〈ひょっとしたらひょっとするかも〉なグループ。彼らを筆頭に、成都のアンダーグラウンド・ヒップホップ・シーンもかなり熱くなっているようです。
■リッチ・チガ『Dat $tick』(インドネシア)
ある意味で2016年のアジアを象徴するアーティストといえば、やはり彼ではないでしょうか。現在17歳、インドネシアのジャカルタ生まれのラッパー、リッチ・チガ。数年前からYouTubeにお笑い動画をアップしていたそうで、中学生YouTuberのようなものだったのかも。それが昨年初頭にゴリッゴリのトラップの上で英語詞のラップを乗せた“Dat $tick”を突如公開(しかも監督も彼自身)。リッチ・チガのあどけない佇まいとあまりにヘヴィーな曲調のギャップが大きな話題となり、なんと現在まで3千万回以上もの再生回数を記録。ゴーストフェイス・キラーがリミックスを手がけたり、キャムロンやデザイナーが同曲を話題にしたことなどで、それまでアメリカにも行ったことのないジャカルタのフツーのティーンエイジャーが、一夜にして世界的なブライテスト・ホープになってしまったのですからスゴイ話です。そんなわけで、先述のCXSHXNLYもすぐさまリッチ・チガと契約(さすがです)。最近の彼のFacebookにはディプロとの2ショット写真がアップされていたりと、階段を10段飛ばしぐらいでセレブへの階段を駆け上っているようです。
■スボイ “Đời”(ベトナム)
CXSHXNLY主催のショーン・ミヤシロが運営する〈88Rising〉にはリッチ・チガやキース・エイプなどCXSHXNLY関連アーティストのビデオクリップが多数アップされているのですが、近頃こちらで紹介され始めているのが、ベトナム・サイゴン出身のフィメール・ラッパー、スボイ。ベトナムのラップ・シーンのなかではかねてから頭ひとつ飛び抜けていた彼女ですが、ハノイ公演のオープニング・アクトを務めたことをきっかけにスクリレックスとも交流したりと、いよいよベトナムを飛び出した活動を本格的に展開中。昨年リリースされたこの曲も、ほどよくオリエンタルなスパイスが散りばめられた完全海外仕様の仕上がりでした。
■ベン・ウトモ『Lost In The Music』(インドネシア)
リッチ・チガが特大ホームランを飛ばしたインドネシアのジャカルタのアンダーグラウンド・ラップ・シーンでも新しい動きが始まっています。カリフォルニア生まれ/育ちのベン・ウトモはJ・コール、ケンドリック・ラマー、ドレイク、リル・ウェインに影響を受けたというインドネシア人ラッパー。現在はジャカルタを拠点に活動を行っており、昨年はジャカルタの仲間たちと完全USマナーなラップ・アルバム『Lost In The Music』をリリースしました。こちらにも参加しているラッパー、A・ナヤカはアメリカのヒューストン出身のインドネシア系だし、彼らとも交流の深いインドネシア人プロデューサーのエミール・ヘルモノはパプア・ニューギニア生まれで現在マレーシアのクアラルンプール在住……と、頭がこんがらがってくるシャッフル具合です。
ひとつ言えるのは、各国のアーティストにとってはかつてのようにNYや西海岸に移り住まずとも、世界を狙える環境が整ってきたということ。アメリカが絶対的な音楽の中心ではなくなった一方で、世界的な音楽のトレンドはいまだ欧米発信のものが左右しているわけで、そうしたキース・エイプ“It G Ma”以降の状況がアジアのローカル・シーンにもダイレクトな影響を与えているといえるでしょう。