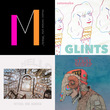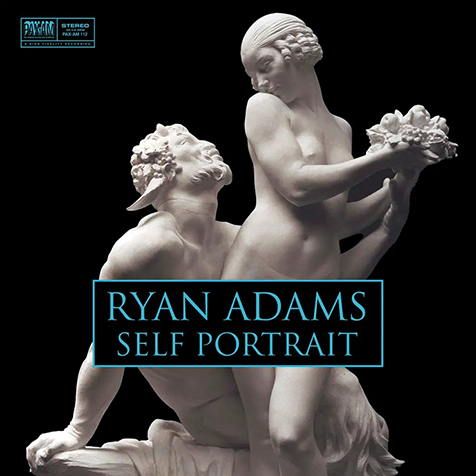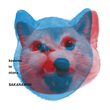大貫妙子の『MIGNONNE』(78年)は音楽評論家の小倉エージがプロデューサーを担い、明確に〈売れる〉ことを目的として制作された。だが、結果的にセールス面では失敗、互いに喧嘩をしながら作られたという同作は、大貫自身も遺恨が残るものだったことを認めている。とはいえ、それから40年後のいま、歌謡性と大貫の持ち味である都会的でヨーロッパ的な嗜好性とのバランス感覚から、その後の音楽的な飛躍も含めて『MIGNONNE』のサウンドは再評価されつつある。
ことほど左様に、ミュージシャンとプロデューサーとの関係性はその作品のサウンドにダイレクトな影響を及ぼす。岡山を拠点に活動するシンガー・ソングライター、さとうもかがリリースしたファースト・フル・アルバム『Lukewarm』をプロデュースしたのは入江陽だ。なめらかでソウルフルな歌声でシュールなユーモアを交えた詞を歌う入江、そして、現実と少女趣味的な空想とのあいだをたゆたっているような世界観のさとう。両者のインタヴューからはその良好な関係性が伝わってくるので、制作中に喧嘩をしたということはさすがにないだろうが、音楽観も、性別も、住んでいる場所も異なる2人の奇妙で絶妙なコラボレーションは本作で見事な実を結んでいる。
音楽的にはジャズやシャンソン、オールディーズのポップ・ソング、あるいはボサノヴァからの影響を垣間見せつつも、一貫してポップな力強いメロディー。ピアノとガット・ギターと、曲ごとに入れ替わるメインの楽器。楽曲に寄り添う、抑制の効いた、親密で箱庭的なアレンジ。『Lukewarm』を特徴づけているのは、そんなエレメントだ。
2015年のミニ・アルバム以来約2年ぶり、現在23歳の彼女にとって短くないブランクを経て放たれる本作は、“Wonderful voyage”という曲に象徴される通り、新たな船出のための作品となるだろう。入江という気のおけない、信頼できる航海士を得て、さとうもかの航海はいままさに始まったばかりだ。
全てのコードが間違っていて戦慄しました。なのに、あんなに良い曲を書けるのがすごい(入江)
――まずはさとうもかさんという音楽家についてお伺いしたいのですが、もかさんが作曲を始めたのはいつ頃ですか?
さとうもか「高校生のときにバンドを始めたんですけど、自分の曲だったら好きなようにできるんじゃないかなって思ったんです。〈歌うんだったら作らなきゃ!〉って固定観念がありました」
――最初からシンガー・ソングライター的な発想だったんですね。当時はどういうものを聴いていたんですか?
さとう「チャットモンチーとか、YUKIとか、aikoとかですね。ジャズも好きでしたけど、曲を作らなきゃって思ったのは日本の歌う人たちを見て、ですね」
――高校が音楽科だったんですよね?
さとう「はい。サックス専攻で入ったんです。ジャズが好きだったから吹いてたんですけど、別にサックスは好きじゃなくて(笑)。ピアノは難しすぎるので、サックスのほうが受験はできるかなって思ったんです(笑)」
――消極的な選択ですね(笑)。では、『Zzz』(2014年)、『Velvet teens』(2015年)という自主制作盤をリリースするに至るまでのことを教えてください。
さとう「高校を卒業して、音楽の短大に行きました。レコーディングとかを学ぶ専攻で。自分の歌が録れるかなあと思って。同級生に録ってもらったりしてました」
――自主制作盤はその大学時代に制作されたんですか?
さとう「はい」
――モナレコードのコンピレーション『モナレコ・コンピ~かけだしてく~』(2016年)に“左耳のネコ”が収録されることになったきっかけはなんでしょう?
さとう「SoundCloudにiPhoneで録ったものをいっぱい載せてたら、当時モナレコードで働いていた佐藤さんがそれを聴いて、連絡をくれたんです」
入江陽「その〈佐藤さん〉はちなみに、カメラ=万年筆(caméra -stylo)の佐藤望さんです」
――そうなんですね! 最近は北園みなみさんとOrangeadeというバンドをやっているという。ちょっと話は戻るのですが、もかさんのプロフィールに〈ピアノの発表会で弾いた“ガラスの靴”という曲のシ・ド・ミの和音で音楽が好きになる〉と書いてありますよね。
さとう「〈♪チャーッチャッチャ チャーッチャッチャ〉って弾いたんですよ。それで、〈ハーッ!〉ってなって。ふふふ(笑)」
――天啓が降りてくるように、閃いたわけですか?
さとう「はい。幼稚園の時だったんですけど、その音が綺麗で、〈ええな!〉って思って」
入江「(小声で)すごいなー……」
――でも、〈シ・ド・ミ〉ってちょっと変な和音じゃないですか?
入江「シとドが半音でぶつかっていますからね」
――2015年の入江さんと大谷能生さんとのインタヴューを読んでいて、〈ジャズ的な濁ったサウンドをどこまで許容できるか〉という話がありました。入江さんがもかさんに共感されているのはそこなのではと思ったのですが。
入江「そうかもしれないですね。もかさんの曲を聴いていて、和音が豊かだなって思っていたので。〈うわっ、濁らせたなー!〉っていう音を使いますよね?」
さとう「そうですね」
入江「濁った和音、本当に好きだよね? デモを聴いていても、〈自分は好きだけど、こんなに濁っていて大丈夫かな?〉って思うくらい濁らせてくるんです。あと、これは本当にびっくりしたんですけど、もかさんは譜面を使わないんですよ」
さとう「コードがわからないんです」
――どうやって書き留めておくんですか?
さとう「脳内に(笑)」
入江「『Lukewarm』では2曲目の“Lukewarm”と9曲目の“殺人鬼”でアレンジャーに入ってもらっているんです。2曲目がTeppei Kakudaくん、9曲目が山田光くん(hikaru yamada and the librarians)なんですけど、2人に曲を伝えるために、もかさんにコード譜を書いてもらったら……最初から最後まで間違っていたんです(笑)」
――ははは(笑)!
入江「全てのコードが間違っていて、僕は本当に戦慄しました(笑)」
さとう「あはは(笑)!」
入江「まず、半音キーがずれていて、それで全部が変わったうえに、さらにいろいろと違ったんです」
さとう「最悪ですね(笑)」
入江「なのに、あんなに良い曲が書けるのがすごいと思いますね」
――では、今回、入江さんがアレンジするにあたって楽譜を書き起こす作業から始めたんですか?
入江「最初は書き起こそうと思っていたんですが……。J-Popならコードの定番の流れの上にメロディーが乗っているんですけど、もかさんの曲ってJ-Popっぽくなくて。例えば、繰り返しが1回あって、そこにメロディーが乗っていて、それとは別に副旋律があったりとか……あんまり〈コードにメロディー〉っていう感じでもないんです。なので、制作の途中からは耳で聴いて、僕もなんとなくで入る感じにしました(笑)。もちろん、もかさんも多少はコードのことはわかるんでしょうけど、すごく本能的に掴み取っているような感じがありますね」
陽さんもSSWだから、お互いの気持ちがわかるところがむっちゃある(さとう)
――そもそも、入江さんがなぜこの『Lukewarm』をプロデュースすることになったのか、その経緯を教えてもらえますか?
入江「初めて会ったのは東京でのライヴかな? 下北沢のモナレコードで知り合ったんです。曲が美しくて、歌声も良いと思いました。でも、悪い意味じゃなく、仕上がった演奏ではないというか、粗い演奏だけど、そのなかにキラキラと歌や曲の良さが見え隠れする、その様に衝撃を受けたんです。なんだこれは?って。それで、ずっと気にはなっていて、何かで協力したいなと思っていたんです。もかさんが前作の『THE WONDERFUL VOYAGE』を出してから、次の作品をしばらく出していなかったので、僕の自主レーベルの〈MARUTENN BOOKS〉からアルバムを出すのはどうですか?っていう相談をしました。僕が岡山駅に行ったんだよね?」
さとう「はい。去年の夏ぐらいに」
入江「当初は自主で出すつもりだったんですけど、作っていくうちに、もかさんの音楽は広く届けたほうがいいのでは?という気持ちになり、それでPヴァインに相談しました。プロデュースとはいっても、基本的には〈いかに何もしないか〉というのが今回の自分のスタンスでした」
――入江さんらしさが抑えられて、もかさんの音楽を引き立てている、もかさんの音楽に寄り添っている感じがしました。
入江「『Lukewarm』はもかさんの演奏素材がほとんどなんですよ。それになるべく触らないようにして、〈これは減らしたほうがいい〉〈コーラスをずらしたほうがいい〉とか、演奏のリズムを直したりとか、どうしても必要そうだったらちょっと足したり、みたいなかたちですかね。リード曲の“Lukewarm”はかちっとしたほうがいいかなと思って、Kakudaくんにアレンジを頼みました」
――もかさんはそのプロデュースされる立場として、制作中、入江さんの采配にはどう感じていました?
さとう「もう、最高です」
入江「ははは(笑)」
さとう「陽さんもシンガー・ソングライターだから、お互いの気持ちがわかるところがむっちゃあると思います。自由にやらせてもらったのでありがたかったです。楽しくできました」
入江「前作は技術レヴェルの高いミュージシャンの方々が演奏しているアルバムだったので、対照的な内容にしたほうがおもしろいかなと思って。でも、本当に、もかさんがほとんど演奏しているよね?」
さとう「そうですね」
入江「もかさんの演奏に他の人の演奏を足していくのはけっこう難しくて。がらっと変えちゃうか、そのままにするかしかなかったんです。リズム感も独特で、揺れているけど、本人のなかにはリズムがあるというか。そのマイペースさも素敵ですね。例えば、(録音で)〈メトロノームを使って〉って言っても、〈結局、使わなかったです〉って事後報告で言われるんです(笑)。“April in my memory”はクリックを使っていないもかさんの演奏に、後からドラムを乗せていったんですけど、それも良かったですね」
――入江さんの『仕事』(2015年)というアルバムは大谷さんがプロデュースですよね。〈プロデュースされる〉という経験は今回、入江さんがプロデュースするにあたって活かされていますか?
入江「『仕事』では大谷さんががっちり枠を作ってくれて、作品の世界観を作るっていうプロデュース方法だったと思うんです。もかさんの場合は、例えば、〈ポップな曲を作ったほうがいいんじゃないか〉とか〈こういう曲はウケないんじゃないか〉とか、自分のなかに枠を作ってしまっている感じがありました。なので、『Lukewarm』の制作を通して、枠を全部なくして、好きなようにやってもらいました。枠を取っ払う作業をしたかったんですね。何かがずれていても、最低限を直すだけで、あとはもかさんの〈味〉としてそのままにする。なので、大谷さんにプロデュースしていただいたのは本当に参考になっていますね。やり方は違いますけど、それは音楽的な自由を得るための手段が違うだけというか」
――なるほど。プロデュースするためのリファレンスやロールモデルになった作品はありましたか?
入江「そうですね……。あえて言うならトム・ウェイツでしょうか。彼ぐらい自由に、1曲1曲に本人の魅力が出ているアルバムにしたかったので、そういうイメージはありました。『ミュージック・マガジン』でトム・ウェイツの本の書評を書いている時にそう思ったのですが、それはよく考えたら『Lukewarm』を作った後だったので、リファレンスになっていないんですけど(笑)」
――それは『Swordfishtrombones』(83年)以降のアヴァンギャルド路線になったトム・ウェイツですか?
入江「そうですね。聴き手が〈うわっ……〉って感じるような、もかさんの魅力を濃度の高いかたちで一回解放したかったので。だから、好き勝手にやってくれと。僕もいろいろと言うんですけど、でも、最終的には言うことを聞かなくてもいいのでと。音楽を作ることには飽きないほうがいいので、わがままを言ってもらって、嫌なことはしないでと。最終的なしわ寄せは、申し訳ないけど、エンジニアの中村公輔さんが被るだけなので(笑)」
――もかさんも前作の対比として今回の『Lukewarm』の制作に挑んだんですか?
さとう「そうですね。曲を作るときの気持ちは前作も今回も同じでしたけど、前作ではアルバムの曲よりも自分で録ったデモの方が気に入っていたり……それがショックでした。なので、今回は絶対に気に入るものを作りたいなって」
入江「サンクラで聴けるもかさんのデモは、あれはあれで作品だと思うんです。iPhoneのGarageBandアプリで、イヤホンに付いているマイクで録っていて。キーボードの音もスピーカーで出してこのマイクで録ってるんだよね? そのおかげでいい具合に部屋の雰囲気が入っているんですよね。そのデモのほうが良いって言われるのが本当に怖くて(笑)。それがいちばんのライバルでした」
――入江さんは前作での反省も聞いていたんですか?
入江「聞いていました。でも、前作を作ったことは良い経験になったと思うんです。自分も『仕事』を作ったあとは反動があって、それに固定されてしまったような気持ちになったから、違うものを作りたいって思ったし。すごく健全だと思う」
さとう「『Lukewarm』に取り掛かるまでの間、こまごまとした自分の趣味の曲はあんまり作れなくなっちゃって。けど、陽さんに〈自由にやっていいよ〉って言ってもらって、好きなものを作れるように、戻りましたね」