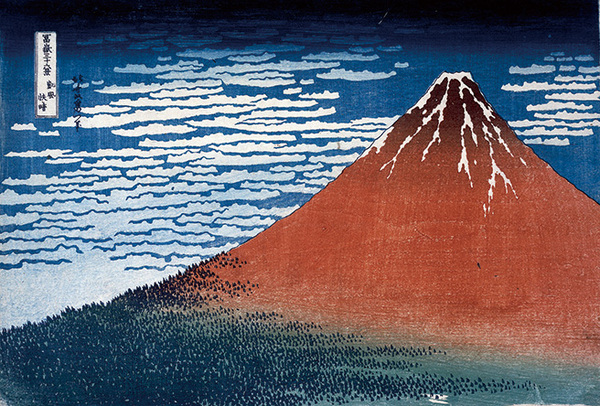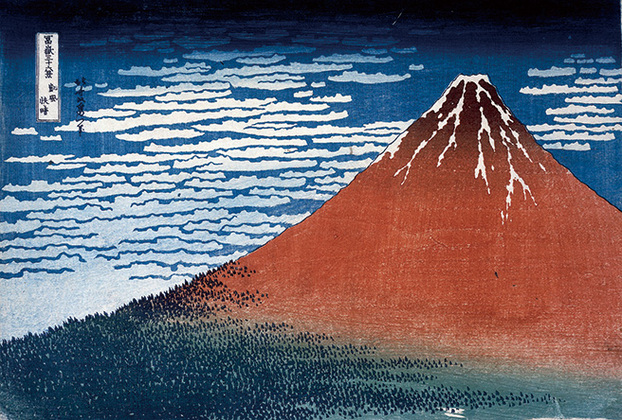
Documentary film and guide to exhibition film ©British Museum
BIG COMIC Manga images in documentary ©Shogakukan
世界の〈日本化〉(人間の〈動物化〉)が進行する現在にあって、二人の孤高のアーティストが〈平面〉における邂逅を果たす。
渋谷のスクランブル交差点で盛んに写真や動画を撮影する外国人観光客が出没しだした頃、こうして世界は日本化していくのか……と少しばかり複雑な感慨を覚えた。もっともこれは僕のように一定の年齢を重ねた人間ならではのものだろう。80年代後半に初めてヨーロッパを旅した僕は、当時ステレオタイプ化していた〈日本人〉に何度か出くわした。たとえば、ローマのトレビの泉に日本人の団体が現れ、後ろ向きにコインを投げる定番の儀式を一通り済ますと、またぞろぞろその場を後にする。もちろんその間、彼らは写真を撮りまくることに忙しかった。まだ若かった僕の目に、正直、日本人団体観光客は〈愚か〉に映ったが、ここでの〈愚かさ〉は必ずしも悪口ではない。予想以上の出来映えだったウェス・アンダーソンの最新作「犬ヶ島」を見ながら、僕の脳裏を何度かよぎり、この文章でも大いに参照するアレクサンドル・コジェーヴによる「ヘーゲル読解入門」(上妻精、今野雅方訳)での記述に従えば、世界の日本化は人間の〈動物化〉(〈愚鈍化〉?)であり、1968年の時点でコジェーヴはこんな予言的言葉を残している。「最近日本と西洋社会との間に始まった相互交流は、結局、日本人を再び野蛮にするのではなく、(ロシア人をも含めた)西洋人を〈日本化する〉ことに帰着するであろう」。

「犬ヶ島」の設定を簡単に説明しておこう。近未来の日本では犬インフルエンザなる病が流行し、メガ崎市の市長は、人間への感染を回避すべく、あるゆる犬を犬ヶ島へと追放する。一方、両親を亡くした孤児でいまは市長の養子である、12歳の少年アタリは、愛犬との再会を期して小型飛行機で、単身、犬ヶ島に乗り込み、そこで出会った5匹の犬と冒険を共にする……。こうした映画が十月革命を機に祖国を離れた亡命ロシア人による「精神現象学」への注釈を連想させるのはなぜなのか。
ヘーゲルにとって人間は〈所与〉(自然に与えられたもの)を否定する存在であり、対象に対立する〈主観〉が人間を〈本来の人間〉足らしめる。人間がそんな〈本来の人間〉を止めると〈歴史の終焉〉に至るが、それは〈世界の終焉〉ではない。自然は人間の誕生以前からあり、消滅後も存続するからだ。〈歴史〉とは、人間による〈所与〉の否定の積み重なりであり、戦争や革命、人間と人間、人間と自然の命を賭した戦いの連鎖であった。だから〈ポスト歴史〉において人間は、もはや自然を否定する存在としてではなく、自然と調和した動物として生き続けるだろう……。
こうした(ヘーゲル=)コジェーヴの議論は、第二次世界大戦後の世界を規定してきた冷戦構造の終焉の際に脚光を浴びた。イデオロギー対立や東西ブロック間の戦争の危機が過去のものとなることで、世界は〈ポスト歴史〉に突入し、戦争や革命に煩わされることのない〈空間的自然〉のうちに人間は幸福をむさぼることになる……と。むろん、こうした主張はアメリカの保守派イデオローグによる呑気な〈勝利宣言〉に過ぎず、その後の世界で頻出した戦争や内戦、テロなどを見るまでもなく明らかに誤りであった。ただ、コジェーヴによる〈歴史の終焉〉をめぐる議論のなかで不意に登場する日本は、「犬ヶ島」での日本と無縁でないように思う。
1946年の時点でコジェーヴは、「人間が動物性に戻ること」を「将来の可能性」としたが、後に発表された第二版では「すでに実現された確実性」であると考えを改めた。そうした見解に到達する背景として、アメリカ合衆国で未曽有の豊かさを享受しつつあった「アメリカ的生活様式」との出会いがあり、彼はそれを「ポスト歴史の時代に固有の生活様式」と見なした。そして、59年の日本への旅が彼にさらなる衝撃を与える。「おそらく、日本にはもはや語の〈ヨーロッパ的〉或いは〈歴史的〉な意味での宗教も道徳も政治もないのであろう。だが、生のままのスノビズムがそこでは〈自然的〉或いは〈動物的〉な所与を否定する規律を創り出していた。……能楽や茶道や華道などの日本特有のスノビズムの頂点(これに匹敵するものはどこにもない)は上層富裕階級の専有物だったし今もなおそうである。だが、執拗な社会的経済的不平等にもかかわらず、日本人はすべて例外なくすっかり形式化された価値に基づき、すなわち「歴史的」という意味での「人間的」な内容をすべて失った価値に基づき、現に生きている」。こうした記述が現に日本で生きる僕らと具体的にどんな関係があるかは疑問だが、要するにコジェーヴは、ポスト歴史の〈人間〉のモデルを日本の〈純粋なスノビズム〉に見出そうとする。ポスト歴史において人間は、〈本来の人間〉(西洋人?)が信じた意味での宗教や道徳、政治を手離すことと引き換えに、茶道や華道に興じながらの(?)永遠の平和を生きるのだ。