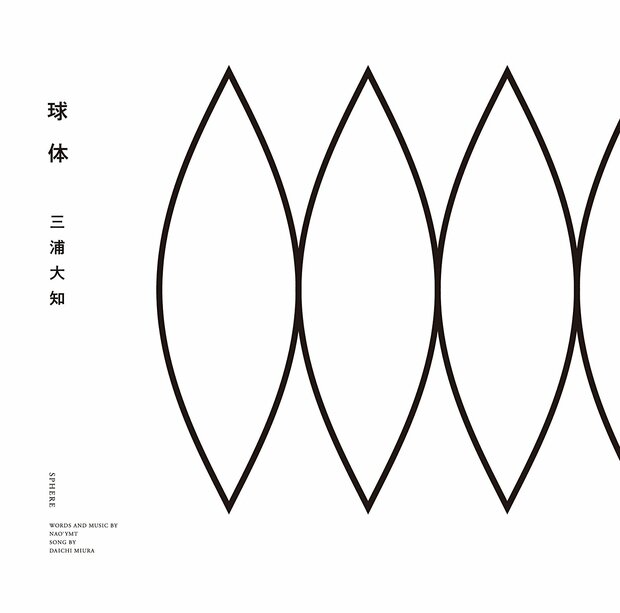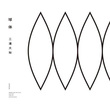ある架空の世界で描かれる時空を超えた17の物語は複雑に連鎖しそしてまた繰り返していく。三浦大知とNao’ymtが贈るコンセプチュアルプロジェクト・アルバム『球体』。7月11日リリース!
2009年のアルバム『Who’s The Man』以来、濃密なコラボレーションを重ねてきたNao’ymtのプロデュースによって組み立てられていったこのプロジェクトは、まず、その名を冠した全国ツアー(8都市8会場10公演)で内容が明かされた。
ツアー初日となったのは、5月25日、東京・昭和女子大学人見記念講堂。大知自身が演出、構成、振付を担当し、〈着席指定〉の鑑賞形式でおこなわれたステージは、いつものライブとはまったく違う様相を、始まりと同時に感じさせた。〈完全独演〉で表現されるステージは、リズムと〈静寂〉が入り交じり、しかし、そのすべてが彼のダンス・パフォーマンスと歌によって鼓動する。そう、昨年の〈紅白〉でも大きな話題となった〈無音ダンス〉をよりエンターテインさせた世界とでも言えばよいだろうか。途中、MCを一切挿まず、最後の一曲が終わるまで、いや、客電が灯るまで、観客は固唾を呑んでステージを見つめる。歓声もなく、ただ、最後に送られた拍手は大きく、余韻を噛みしめるようにしばらくのあいだ鳴り止まなかった。
行き場をなくした男の前に現れた君は、あの時と変わらぬ微笑み浮かべていた。男はゆっくりと砂のついた手を伸ばす。この世界に居場所求めて――。ある架空の世界で描かれる、時空を超えた17の物語が複雑に連鎖し、そしてまた繰り返していく。Nao’ymtによって作詞、作曲、編曲、プロデュースされたアルバム『球体』は、言わば〈完全独演会〉のサウンドトラック、でもある。
寄せては返す波の音、遠くで響く船の汽笛がアルバムの始まりを告げ、そのあとに連なっていく物語を予感させるようなシンフォニー“序詞”(じょことば)がドラマティックに鳴らさせる。フリーキーなビートを刻む“円環”(えんかん)、眩いファンタジアを目の前に浮かばせるダンス・ナンバー“硝子壜”(がらすびん)と続き、セレモニーの始まりを告げるかのように勇壮なトランペットが鳴るインストゥルメンタル“閾”(いき)を挿んで、〈私たちの個性が、ここに馴染めないだけ〉――微かな風を受けた水面のように心地よく揺れるスロウ・チューン“淡水魚”、メランコリックな旋律を奏でるアコースティック・ナンバー“テレパシー”、〈印などいらない 保証などいらない ただ自分でいたいだけ〉――エキゾチックなメロディーを絡めた壮大なバラード“飛行船”……と、さまざまなニュアンスを感じさせる楽曲群、そのすべてには一種独特の〈緊張感〉がある。
全編日本語で編まれた歌詞には文学的なニュアンスが映り、そこに込められた感情や情景を繊細に描写するメロディーとアレンジ、そして声。17の物語、すなわち17のトラックは、それらすべてでひとつの物語で、トータル75分以上にもおよぶ大作だが、最後までその心地よい〈緊張感〉で耳を離さない。
アルバムには、撮り下ろしの映像を収めたDVD/Blu-ray付きの仕様もスタンバイされており、『球体』の世界観をより深く、パノラミックに体験できるものになっているが、とにかくこの作品は、大知にとってもNao’ymtにとっても実験的かつ冒険を孕んだ作品であり、現在の音楽シーンにおいても挑戦的な作品と言えるだろう。クラシックな洋楽を聴いているリスナーであれば、デヴィッド・ボウイ『ジギー・スターダスト』やピンク・フロイド『狂気』、ザ・フー『四重人格』(そういえば、このアルバムのオープニングも波の音で始まる!)、クイーン『オペラ座の夜』なんていう往年の〈コンセプト・アルバム〉ないしは歌劇的なアルバムを思い出すだろう。
リスニング・スタイルの変化もあって、現代では全世界的にそういった大作が生まれにくく、1枚のアルバムで芸術を作り出すという意識も薄れているところはあるのだが、そういった〈時代〉に倣うことだけが正解ではないことをこのアルバムは示している。自身のボーカルとダンス・パフォーマンス、そしてオリジナリティーを究めていくなかで生まれた〈前代未聞〉のアルバム『球体』。さて、あなたはどう受け止める?