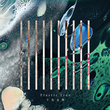シンメトリーなイメージを重ねながら〈らしさ〉を追求することで踏み出した新世界。持ち前のエッジと、これまでとは趣を異にする優美な耽美性に投影されたバンドの美意識とは?
今年3月に発表した14枚目のアルバム『doorAdore』ではメンバーそれぞれのルーツにある音楽性をさらに深化させつつ、ポスト・ロック然とした新味も垣間見せた――つまり、バンド本来の個性と新たな可能性を同時に追求したPlastic Tree。その後の全国ツアーに関しては、「いままで自分たちがやってきたことを改めて実感できたし、この先はそれぞれのメンバーの手によってバンドに新しい風が吹きはじめるんだろうなという予感もありました」(有村竜太朗、ヴォーカル)と振り返る彼らより、ニュー・シングル“インサイドアウト”が届けられた。本作には、PlayStation Vitaゲーム「Collar × Malice -Unlimited-」の主題歌を担う表題曲と、エンディング・テーマの“灯火”を収録。〈Collar × Malice〉シリーズとのコラボレーションは“サイレントノイズ”(2016年)に続き2度目となる。
作詞を有村が、作曲を長谷川正(ベース)が手掛けた“インサイドアウト”は、空間を切り裂くようにエッジーなギター・リフと、直線的に突き進むエイトビート、憂いと共に解放感も伝わるメロディーラインがぶつかり合うアッパー・チューン。生々しい臨場感に溢れたバンド・サウンドに乗せ、〈夜が朝に変わるの〉〈未来と過去〉〈君と僕〉というシンメトリーなイメージを描きながら、新しい世界に向かって進んでいく歌詞も強く印象に残る。
「(混沌とした雰囲気の)“サイレントノイズ”とは違う、開けたイメージの楽曲にしたかったんですよね。Plastic Treeの濃い部分を表現したアルバム『doorAdore』の次のタイミングということもあって、自分たちとしてもフラットな楽曲を作りたいなって。バンドとしての良さをストレートに出せた曲になったと思います。(ゲーム側のスタッフから)求められたことと、自分たちのやりたいことが合っていたのはすごく良かったです」(長谷川)。
「前回の“サイレントノイズ”はゲームのシリアスなところをピックアップしたんですが、今回は希望的観測も含まれているということだったので、〈夜明け〉をテーマにして〈希望〉だったり、どこかハッピーな雰囲気も含んだ歌詞にしたいなと。もともとPlastic Treeは多面的なバンドだし、違和感なく書けましたね。割と僕らは〈こういうものじゃなくちゃイヤだ〉というようなバンドではないので。新しいテーマをもらえたらむしろ楽しんでやれるし、他のジャンルの作品と一緒に何かを作ることは向いているバンドだと自分では思ってて(笑)」(有村)。
そして、クラシカルなピアノと壮大なストリングス・サウンドをフィーチャーした“灯火”は〈逃げ出せない哀しみなら/どこまでも側にいるよ〉というサビのフレーズが重厚に響くバラード・ナンバーで、作詞/作曲は共に長谷川が担当。ゲームのエンディングに相応しいスケール感と、Plastc Treeらしい耽美性が融合した楽曲と言えるだろう。
「最初はアコギの弾き語りのイメージで作りはじめたんですけど、ゲームのエンディングとして求められる雰囲気に近づけるために、アキラ(ナカヤマアキラ、ギター)にアレンジを相談したんです。ピアノと弦を打ち込みで入れたのは彼なんですけど、それが圧倒的だったんですよね。完成した楽曲はサウンドトラック的というか、方法論としてはロック・バンドらしくないかもしれないけど、メンバーのアイデアや美意識みたいなものは入っているし、胸を張ってPlastic Treeの作品だと言える楽曲になったと思います。もともと〈良い曲にするためなら手段は問わない〉というところがありますからね、このバンドは」(長谷川)。
「作詞/作曲、アレンジやサウンドメイクは正君、アキラ君に任せて、自分は歌に専念しました。いままでバンドが触ったことのない雰囲気のアレンジだったし、だからこそ自分の歌で〈プラらしさ〉を示すというか、楽曲とリスナーとの橋渡しができたらなと」(有村)。
前作『doorAdore』の延長線上で、〈らしさ〉と〈新しさ〉を同時に追い求めるスタンスを提示した“インサイドアウト”。本作を通過し、Plastic Treeの鳴らすロック・ミュージックはより独創的に進化することになりそうだ。
「“インサイドアウト”に関しては、偶然的な部分を含めて、すごくいいカタチでバンドの良さを抽出できたと思っていて。この先のヴィジョンについて具体的なことはまだ言えないけど、バンドとしてもヴォーカリストとしても〈こういうモノを追求したい〉というイメージがあるので、それを次の作品に繋げたいですね」(有村)。
Plastic Treeの近作を紹介。