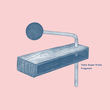Taiko Super Kicksは、みんな我が強いっていうか、変なんです
――『Fragment』リリースのタイミングで取材できなかったことが残念でした。なので、『Fragment』から今回のシングルまでのことをお伺いできればと思います。
「『Fragment』の取材は詞について訊かれることが多くて、音楽的なことにあんまり触れてもらえなかった気がします。意図が伝わっていないという、力量不足もあると思いますし」
――『Fragment』は、バンド・アンサンブルを大事にしていると感じました。
「その意識で作ったんです。〈4人である〉っていうことを、いちばん重要視して作ったので」
――タイトで引き締まってて、無駄がない演奏という印象です。例えば、Corneliusのサウンド・デザインのような。
「新しいアルバム(『Mellow Waves』)は参考にもしましたね。音を並べていく、敷き詰めていく感じというか」
――具体的にはどういうことをしたんですか?
「まず、基本的にはオーヴァー・ダビングをしないっていうのがひとつ。楽器の音の配置も基本、全曲同じです。〈ここでこれが鳴ってる〉っていうのをわかるようにしました。あと、これまでは〈樺山(太地)のギターがいい〉という評価も多かったので、メンバーみんなの個性を出そうって考えて。
去年1年間、メンバーで〈月刊タイコスーパーキックス〉っていうフリーペーパーを作ったんですけど、みんな我が強いっていうか、変なんです。サークルの後輩にも〈この3人とバンドをやるのはなかなか難しいですよ〉って言われたり」
――まとめるのが難しいんですね(笑)。
「まとめられてないから、逆にいいと思うんですけど。例えば、ベースの大堀(晃生)さんは、バンドが全然続かなかったんですよ(笑)。本人も自虐で〈バンドクラッシャー〉って言ってるくらいで。
のぞみん(こばやしのぞみ/ドラマー)も自分を持ってる人で、簡単には自分を曲げないタイプ。樺山もそう。だから、音楽的な理由というより、人間味とかキャラクターとか、そういうのを作品に出したほうがいいなって思って。
タイコはワンマン・バンドじゃないんです。新曲を作ってても、みんながノるまでに時間がかかったり、〈この曲はよくわからない〉っていう空気になったりすることもある。だから、みんなの納得するポイントを、ちゃんと取らなきゃいけないバンドなんです」
〈ルーツ〉って、いろいろな捉え方ができると思うんです
――他に『Fragment』の音楽的なテーマはありましたか?
「まさに訊かれなかったことなんですけど、ミニマルがやりたかったんです。特に“バネのように”と“遅刻”は、自分たちなりのミニマル・ミュージックを意識しました。“遅刻”については当時、清水靖晃さんの『案山子』(82年)にすごくハマってて、ああいうポップ感があるミニマルをやりたかった。“バネのように”は、ジュリアス・イーストマンの“Stay On It”(73年)っていう曲がリファレンスで。〈♪テッテレレレッテッテーレ〉っていうフレーズで展開していく曲なんですけど。
あと、自分がギターで、コードじゃなくフレーズを弾くっていうのもテーマでしたね。『家族ゲーム』(83年)って映画があるじゃないですか? 最後、家族4人が横並びで食卓についてる画が有名な。レコーディングする前に、あのイメージでやろうって言ってたんです」
――それはおもしろいですね。あの画を音にするという。では、『Fragment』のリリースから今回のシングルを発表するまでの9か月間、バンドの状態はどうでした?
「ライヴの本数も多くはなかったですし、どちらかというと曲を作ることに専念してました。今回のシングルは、形が見えてくるまでに何か月間か、うまくいってないなっていう期間もあったんですよ。何回も曲を作り直しましたし。メンバーの間には〈この状況、何なんだろう?〉って気持ちもあったんだろうなって……」
――閉塞的だった?
「そういう時期もありましたね。でも、樺山が〈頑張りましょう! 暁里さんがビシッと締めないと駄目ですよ〉って言ってくれたりして。なので、曲の作り方を変えて、デモを作り込むようにしたり。でも、“感性の網目”が出来て、〈いい曲が出来た〉っていう空気になりましたね。とりわけ歌は、これまでとは違う、ハートウォーミングな感じになったんじゃないかと(笑)」
――確かにそうですね。
「あと最近、タイコはルーツがわかりやすいタイプのバンドじゃないっていうことを意識しはじめたんです。〈ルーツ〉って、いろいろな捉え方ができると思うんですけど、そんなとき、たまたま『インドア・ポップ・サイクル』(99年)※っていう本を買って。〈ジャンル名はないけど仲間だよね〉っていう、通じ合うアルバム100枚が紹介された本で」
――わかりやすい影響関係ではなく、音楽的に距離はあるけど、何か補助線があると、その距離がグッと縮まるみたいなことでしょうか?
「まさにそうです。それを教えてくれる本で、自分にもそういうルーツはあるなって。例えばそれは、僕が大学に入学した2010年頃によく聴いていた、ブルックリンのバンドかもしれませんし」
――アニマル・コレクティヴ、グリズリー・ベア、ダーティ・プロジェクターズとかですね。
「そうですね。具体的にどのバンドがというわけではないんですけど、そういうもののなかに自分の第2のルーツ、それこそ補助線のようなルーツがあるんじゃないかなって考えて、それで“bones”を作りはじめたんです。メンバーにも〈なんでいま音楽をやってるのかを考えてみない?〉って問いかけてみたりしましたね。そういう期間でしたし、いまも考え続けてます」