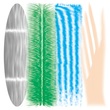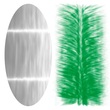(左から)樺山太地、こばやしのぞみ、伊藤暁里、大堀晃生
2021年、Taiko Super Kicksが突如リリースしたニューアルバム『波』と、連作のように続けて発表された『石』。『波・石』としてCD化され、先日アナログレコード化も発表された両作は、岡田拓郎がプロデュースとミキシングを担当している。バンドメンバーと同年代であり、おなじころにデビューし、つかず離れず、それぞれの道のりを歩んでいた2組が合流し、試行錯誤と実験の結果、生まれたのがこの『波』と『石』だ。
前回は、『波』についてのロングインタビューを掲載した。今回は、『波』と『石』の両作について、Taiko Super Kicksの伊藤暁里(ボーカル/ギター)と岡田の対話をここにお届けする。前回同様、北沢夏音が聞き手としてインタビューをおこない、私、天野龍太郎も、ところどころで質問を投げかけた。
今回の対話も、『波・石』の背景を掘り下げるのに留まらず、本源的な問いにまで及んだ。日本語でロックやポップスを歌うこととは。言葉と音との関係性とは。詞と詩のちがいとは。現状に対して〈緩やかなアゲインスト〉を続けている2組だからこそのダイアローグになったと思う。
Taiko Super Kicksと岡田拓郎、それぞれの歩み
――Taiko Super Kicks(以下、タイコ)と岡田拓郎くん、2組の交流はいつ始まったのでしょうか?
伊藤暁里(Taiko Super Kicks)「バンドを本格的に始めたのが2013年で、それから2016年頃までは近い場所で活動していたと思います。
対バンは、Nohtenkigengoのイベント※で一回しかしていないんです。当時のNohtenkigengoのバンドメンバーは、のぞみん(こばやしのぞみ、ドラムス)と大堀さん(大堀晃生、ベース)と岡田くんだったんですよね。それがたぶん初対面で、そのとき(の打ち上げで)、僕はすごく酔っ払っていて……」
岡田拓郎「二度と会いたくないと思った(笑)」
伊藤「ははは(笑)」
――暁里くん、酒癖悪いの(笑)?
岡田「わりと最悪ですよ(笑)。絡むし、帰らないし」
――でも、なんか楽しそう(笑)。お互いのバンドについては、どう思っていましたか?
伊藤「岡田くんの森は生きているは、音楽的な(技量の)裏づけや知識の面で到底かなわない、すごいバンドだと思っていました。当時の自分たちは〈とりあえずギターを歪ませてオルタナティブロックをやる〉という感じで、やっていることも全然ちがうなと」
岡田「2013年前後は、ココナッツディスク吉祥寺店に並んでいるCD-Rとかがおもしろかったんですよね。それまでは日本の音楽で聴きたいと思えるものがぜんぜんなかったけど、あの頃からミツメとかKlan Aileenとか〈いいな〉と思えるバンドがちらほら出てきて、その流れをチェックしていくなかでタイコを見つけて、〈同い年なんだ、いいなあ〉と思っていました。タイコは同時期に、一緒に出てきたバンドだと思っています」
――その頃から新世代のユニークなバンドの登場が相次いで、東京のインディーポップやインディーロックのシーンが急速に活性化した印象があります。『日々の泡沫』(森は生きているの自主制作CD-R)が世に出たのも、2012年末でしょう?
岡田「そうですね」
――あんなに早く森は生きているが解散するなんて思ってもみなかったけど※。昆虫キッズも解散しちゃったし、シャムキャッツまでいなくなってしまった。そう考えると、タイコってしぶとい。しかも、ただバンドを続けているんじゃなくて、着実に進化している。
伊藤「少しずつ、ですけどね。そのころにデビューした周りのバンドは自分たちよりも早く動いていったんですけど、僕らはじっくりとやりながらも進歩している感じはありますね」
――岡田くんは、その後もタイコの活動を追っていましたか?
岡田「作品が出るたびに聴いていました。もともとファンで、〈りんごの質感 イェー〉のころから好きだったし。
僕はヨ・ラ・テンゴとかヴェルヴェッツ(ヴェルヴェット・アンダーグラウンド)とかソニック・ユースとかも好きだったんだけど、森のメンバーはアーシーなものが好きだったから泥臭いバンドをやっていて、同年代でああいうクールなインディーロックをやっているのは正直うらやましかったんです」
――森は、言うほど泥臭くはないよ。むしろ、洗練されていたほうだと思うよ。森は生きているが解散したとき、暁里くんはどう思いましたか?
伊藤「美学を感じたし、岡田くんらしい、森は生きているらしいなと思いました。無理をしてまで続けず、音楽的な難しさを感じたらスパッとやめる、そのことに潔さを感じたんですね。自分には、あれはできないなと」
岡田「俺と同じくらい頑固だと思うけど(笑)」
伊藤「僕らは続けようとするほうに、頑固にやってる(笑)」
――はっぴいえんどだってアルバムを3枚は作ったのに。
岡田「ほんと、そうですよね」
――はっぴいえんどは『風街ろまん』(71年)のあと、実質的に解散状態だったのに、〈アメリカでレコーディングしよう〉というキング/ベルウッドのプロデューサー、三浦光紀さんの提案にグラッときて、ラストアルバム『HAPPY END』(73年)を作ったという逸話があります。森も、せめてもう1枚作ってほしかった。
岡田「そういえば、森の解散後、英太さん(岡崎英太、YOMOYA/ookubofactory)と一緒に飲んだことがあったよね」
伊藤「そのときも酒癖が最悪だった(笑)。悪態をついていましたね」
岡田「〈おめえのそういうところが気に食わねえんだ〉とか言ってた気がする(笑)。
英ちゃんが〈新しいバンドをやりたい〉と言っていて、〈暁里くんがボーカルだったら俺もやります〉という話になったんです。で、それを暁里くんに知らせないで、〈3人で飲みに行こう〉と誘ったんですけど、暁里くんが酒に飲まれて……(笑)」
伊藤「知らぬ間に新バンドの構想が立ち消えたって、あとから知った」
――バンドメイトになれたかもしれないのに。
伊藤「ちがう世界線はあったかもしれないですね。
岡田くんとは、そんなふうにオン&オフな感じでしたね。その後も〈新作をリリースしたよ〉とたまにDMしあったりしていたんですが、2020年の頭に僕から〈会って話せないか〉と連絡したんですね。コロナ禍のギリギリ前で、まだ対面で飲めた時期に」
――暁里くんからプロデュースを持ちかけられたとき、岡田くんはどう思いましたか?
岡田「やりたいとは思っていたんです。なので、暁里くんに〈たぶん、僕なら誰よりもいいミックスができる〉と言ったおぼえがあります。
タイコのような音楽をやっているバンドって日本にあまりいないので、そういう音楽に日頃から触れていないと、いいミックスやマスタリングができないし、いいアイデアも出せないと思うんですね。もう自分はバンドやれないなと思いますけど、気を遣わずにいられる年齢が近いバンドと一緒にやるのは好きだし、エンジニアやプロデューサーには自分たちより上の世代の方が多いので、もし年齢が近い人がいたら、僕も一緒にやってみたい。だから、声をかけてくれたのはうれしかったし、〈やりたい!〉って思いましたね」
――〈ここをこうしたらもっとよくなるのに〉というイメージはありましたか?
岡田「細かいポイントではあったかもしれないけど、音響設計やプロダクションってあとからついてくるものなので、そもそも曲がいいかどうかがいちばん大事なんです。あと、タイコにはタイコのカラーがあるので、誰がプロデュースしてもタイコの音楽になると思います。
そのうえで、これまでのソリッドなロックバンドのサウンドではないものをタイコはやろうとしていたので、〈それなら僕がいちばんうまくできる〉と思ったんです」