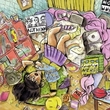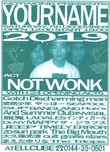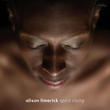NOT WONKがニュー・アルバム『Down the Valley』をリリースした。ウォール・オブ・サウンド的な分厚い音作りのもと、尖ったハードコア・パンクを鳴らした前作『This Ordinary』から約3年。その間、苫小牧を拠点に活動する3人組は、全国各地でのライヴに明け暮れながら、いくつかの7インチやEPを発表してきた。なかでも、2017年のEP『Penfield』収録曲“Of Reality”で見せた、甘やかなファルセットと隙間を活かした演奏によるソウル・ミュージックへの志向性が、多くのリスナーを驚かせたことは記憶に新しい。
加えて、新作『Down the Valley』が、これまで彼らの作品を世に出してきた安孫子真哉率いるインディー・レーベル・KiliKiliVillaからではなく、メジャーのcutting edgeからのリリースとなったことも大きなインパクトを引き起こした。つねづね反メインストリーム的な姿勢を打ち出してきた彼らゆえに、今回の変化は小さからぬ決断だったのではないだろうか。
もちろん、本作を聴けばわかるとおり、バンドはメジャーに移ったところで、ポップになることも、口当たりのよいサウンドに舵を切ることもなかった。むしろ、“Of Reality”以降の先鋭的なリズム・アプローチを推し進めつつ、ソングライティングを練磨させた『Down the Valley』は、彼らのキャリアのなかでもっとも音楽的にラディカルなアルバムと言ってもいいはずだ。
だが、そうした点を踏まえたうえでなお、本作をメジャー作品たらしめている決定的なポイントがある。それは、バンドの眼差しが彼らのさまざまな隣人たち、ありふれた人々へと向けられていることだ。社会から疎まれてきた底辺層=チャヴを喩えに出しながら、〈全て自分のことだと思えて仕方がないんだ〉と歌う“Subtle Flicker”は言うまでもなく、みずからの不安や弱さを率直に綴っている言葉を持った楽曲は、これまでよりはるかに多くのリスナーから〈自分の歌〉として受け止められるだろう。
かつてエルヴィス・コステロはシニシズムへの怒りを込めて〈愛と平和と理解の何がおかしいんだ?〉と歌ったが、2019年のNOT WONKは、不寛容さと敵意が蔓延した現在に、ただ〈優しくあろう〉と呼びかける。アンダーグラウンド・パンクの若きヒーローから、市井の人々の魂に灯をともす音楽家へと成長を遂げた起点には、どんな問題意識の芽生えがあったのだろうか? フロントマンにして全曲で作詞作曲を手掛ける加藤修平に語ってもらった。
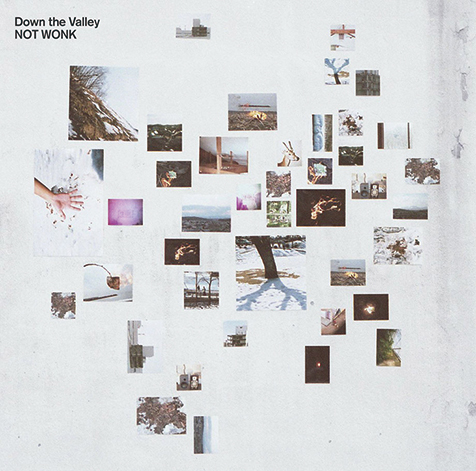
NOT WONK 『Down the Valley』 cutting edge(2019)
パンクやインディーから心が離れたとき、ソウルの率直さに胸を掴まれた
――前作『This Ordinary』のあと、NOT WONKはどんな課題をみずからに与えていたのでしょうか?
「自分が曲を作る際、それまでは強弱でメリハリをつけるばかりで、時間的な流れで起伏をつけていくいものがほとんどないと思ったんです。だから今度はソングライティング的なところでなだらかなダイナミクスを作りたいなと。2017年に出したEP『Penfield』からはそのあたりを意識して曲を書いてみて、演奏面でも繊細なタッチをめざした。それは今回のアルバムまで続いていますね」
――自分の曲を聴き返してみて一本調子に感じたということですか?
「切り貼りで作ったような構成だなと思ったんです。すべての曲で、AメロからBメロ、Bメロからコーラスといった各パートをブレイク※で繋いでいたんですよ。それが手癖みたいになっていて、ちょっと飽きてきたんですよね。じゃあどうするのがいいかと考えたときに、リズムやフレージングを工夫して、各パートの縫い目をなだらかにしていこうと思ったんです」
――結果的に、前作以降のNOT WONKの楽曲はシンプルにヴァース・コーラス・ヴァースといった構成ではないものが増えています。
「ブレイクを使わずに各パートを綺麗に繋ごうとすると、グラデーションしていくみたいに滑らかな変化を持った曲に仕上がっていったんです。 あと、繋ぎ目を大事にするっていうことは、その前/後のパート自体を丁寧に作り込むことでもあって。そうすると各楽器のフレーズもいままでより増えたり逆に減ったりと変化していく。それはリズム隊の2人(ベースのフジとドラムスのアキム)も自然に感じ取って、演奏の質が変化していった」
――綺麗な縫い目を作っていくという点でヒントとなったアーティストはいますか?
「2017年以降にハマったのは、ファーザー・ジョン・ミスティ。彼の曲は縫い目がすごく綺麗じゃないですか。あとはエルヴィス・コステロとバート・バカラックの共演盤※もかな。ソウルもよく聴くようになりました。だから……パンクをほとんど聴かなくなったんですよね」
――作り手としてポップスの錬金術的なところに興味がいったんですね。それにしてもパンクを聴かなくなったというのは驚きです。
「単純に飽きていたんだと思います。パンクやガレージ、インディー・ロックみたいなものにちょっとうんざりしていた感じもあって。それこそマック・デマルコ以降のインディーR&Bっぽい音楽がつまらなくなり、フィドラーとかサーカ・ウェイヴスとかああいうガレージっぽいバンドにも正直飽きていた。
〈じゃあ僕はいま何に入れこめるんだろう?〉となったときに、ファーザー・ジョン・ミスティがしっくりきたんです。女性シンガー・ソングライターもよく聴いていて、サンディ・デニーやジョニ・ミッチェル、キャロル・キング……なかでもハマったのがジュディ・シルでした。曲のなかでの縫い目の綺麗さと歌の神々しさ――そのふたつがキーだったように思います。ジェフ・バックリーはその二点を上手く融合している感じがして、彼の音楽はヒントになっていましたね」
――最近のライヴで、たびたびジェフ・バックリーのカヴァーでも知られる“Hallelujah”(原曲はレナード・コーエン)を演奏していますよね。よく聴くようになったというソウルの志向性は、『Penfield』収録曲の“Of Reality”から顕著になったように思います。
「歪みでスピーカーの上から下まで塗り尽くすみたいにサウンド面で挑戦したセカンド・アルバムを経て、次はリズムのおもしろさを追求したいと考えたんです。リズムとセブンス・コードかな。これまでNOT WONKの曲ではあまりセブンスを使っていなかったんですけど、セブンスやアドナインスの持つソウル・フィール、メロウでちょっと臭い感じが、当時の自分へと妙にマッチしたというか。ソウルって臭さになんの照れもないじゃないですか。そういう率直さみたいなものに惹かれたんですよね」
――情緒をストレートに出すことにてらいがないというか。
「いままで自分がやってきた音楽は、いかに外し続けるみたいなところがあったと思うんです。インディー・ロックってそうじゃないですか。ペイヴメントのヘロヘロなバンド・サウンドやマック・デマルコのリヴァービーでボヤっとしたギターもすべて、照れ臭さの裏返しにも思えた。NOT WONKもしかりで、良いメロディーをベタベタのコードに乗せて、ただ一所懸命に歌うという力強さが、以前の僕にはなかったんです。それと比較すると、ソウルやR&Bって歌詞もベタベタじゃないですか。I Love Youでしかない。そこが強いなと思ったんですよ。逃げてない、誤魔化していなくて」