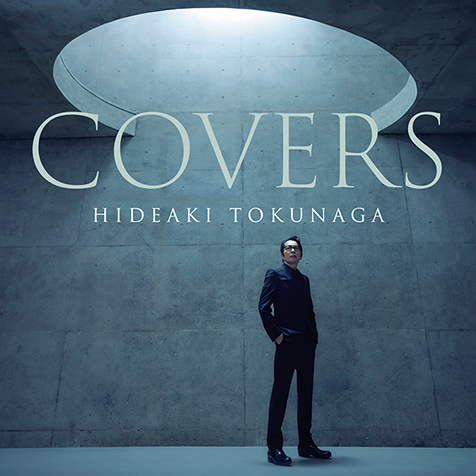アレクサンドル・デスプラ 初のオペラ「サイレンス」をパリで観る
川端康成の短編「無言」を題材にデスプラが問う
アレクサンドル・デスプラは、「真珠の耳飾りの少女」から、アカデミー賞作曲賞に輝いた近作の「グランド・ブダペスト・ホテル」「シェイプ・オブ・ウォーター」まで、繊細な感性に満ち、エスプリの効いた映画音楽で知られている。そのデスプラの作曲した初のオペラ「サイレンス」が、ルクセンブルク(2月26-27日ルクセンブルク大劇場)とパリ(3月2-3日ブーフ・デュ・ノール劇場)で初演され、音楽界の注目を集めた。
彼は今まで、映画や舞台とは関係ない純粋な音楽作品として、フルート協奏曲や管弦楽曲なども作曲しているが、いわゆる声楽作品はない。ヴィブラートの効いた歌唱法や少しオーバーなロマン派のオペラ的表現は苦手で、彼の音楽世界とは相容れないとのこと。今回もオペラと言っても、小編成で、薄くデリケートな響きの得られる、ソプラノ、バリトン、語り各1名と10人の器楽奏者による室内オペラという形が取られた。
台本も、淡々とした幻想性から選ばれた、川端康成の短編「無言」に基づいている。デスプラと共同で台本を手がけたヴァイオリニストのソルレイ(ドミニク・ルモニエ)は、公私にわたる長年のパートナーで、演出、ヴィデオ映像もソルレイが担当した。2人は、このオペラで、数年前、脳の手術の後遺症でソルレイの左手の指が以前のように動かなくなってしまったことと、「無言」に登場する作家が、脳卒中により言葉を失い、書けなくなったことを重ね、表現手段を失った芸術家はどう生きていくのかという問いを掲げる。もちろんこの舞台では、それに対する明確な答えはないままに、現実と虚構、想像の狭間で、言葉や想いが夢の中の出来事のように曖昧に漂っていたのが絶妙であった。
デスプラの音楽では、同じ楽器を3つずつ用いる雅楽にちなんだ楽器編成(フルート3、クラリネット3、弦楽三重奏、打楽器)、音取にも似た冒頭の音楽、酒を飲む場面での篳篥風のピッコロ、箏のような弦楽器のピッツィカート、邦楽の五音音階と、声と楽器のユニゾンなど部分的に日本らしさが取り入れられてはいたが、大半はミニマル・ミュージック的であったり旋法が響いたりと、彼らしいきめ細やかな音風景の中に様々な要素が混ざり合っていた。とくに、憂いを帯びた、短3度下行する2つの音のモティーフが何度かくり返され、宙ぶらりんの状態を表すかのように虚ろに響くのが印象に残った。また、録音された、ソルレイの即興によるヴァイオリンの音が、時折〈幽霊〉として、生きた亡霊となってしまった作家やトンネルの中でタクシーに乗ってくる女の幽霊を象徴するという趣向も味わい深かった。
声の旋律は、ドビュッシーやプーランクなどを想起させる、フランス語の言葉を聴きとりやすいものだった。できるかぎりヴィブラートを取り去った、飾りのない声、削られた表現が川端作品とよくマッチしていた。