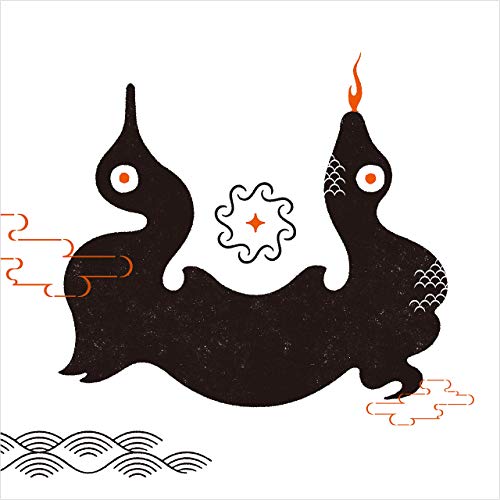Abbau――解体、取り壊し、分解……。
愛知・名古屋を拠点に約20年間活動を続け、多くのバンドや音楽家たちからひそやかに尊敬を集めているGUIRO。彼らが(短くない活動休止期間を挟んで)2016年12月にリリースしたシングル『ABBAU』は、『Album』(2007年)から実に9年ぶりの新作となり、静かに波紋を広げていった。
さかまく波の音のように躍動し、伸縮するビート。野性的なコーラス。どこか不穏さをたたえながらもメロディーを美しく飾るストリングス。GUIROでありながらGUIROでない、そんな新鮮さと奇妙な質感とを『ABBAU』はたずさえている。
その『ABBAU』が今回、新装盤〈Neue Welle〉として生まれ変わり、全国流通および配信がスタート。〈Neue Welle〉では、あだち麗三郎がリミックスを施し、風間萌によるリマスターがなされたほか、“アバウ(Pt. 2)”は“アバウ(Welle)”と改題のうえで髙倉一修がヴォーカルを再録、さらに大場ともよのコーラスも追録された。
しかし、『ABBAU』という作品と“アバウ”という曲については、まだ髙倉の口から詳しく語られていない。これらはどんな曲で、どのように生まれ、どんな思いが(必然的に)こもってしまったのか。今年6月にリリースされた中篇アルバム『A MEZZANINE(あ・めっざにね)』とはまた異なるバンドの姿が刻まれた『ABBAU (Neue Welle)』(〈Neue Welle〉には、過去ではなく〈いま目の前にある「新しい波」を見に行こうよという気持ち〉が託されているという)について、GUIROの中心人物である髙倉に訊いた。
“アバウ”が産声を上げるまでの15年
――“アバウ”がどういう曲なのか、髙倉さんの口からはまだ語られていませんね。
「そうですね。ただ、明快に説明できるものでもないので、なんでも語ってしまえばいいものでもないんです。明らかにしすぎないように、とも思っています。
何かを読み取ろうとすると、ぜんぜんわからないかもしれません。曲の構造も変わっていますし。(発表してから)3年経ってみて、やっぱり特殊な曲だと思います。この曲はこれだけで、以降のGUIROとはまた切り離されている感じがあるんです。
ただ、『A MEZZANINE(あ・めっざにね)』に収録した“三世紀”は、自分の中では作曲上の発展型のように感じています。ポップス的な曲の組み立て方をより意識しなくなったというか」
――GUIROは曲が生まれてから録音されるまでに時間がかかるものも多いそうですが、“アバウ”はいかがですか?
「録音までは10か月くらいですかね」
――意外と短いですね。2016年にできた曲なんでしょうか?
「いえ、録音に取り掛かったのがその年の8月の終わりくらいで、2015年末のライヴ※でも演奏しました。実は段階を踏んでできた曲で、足掛け……たぶん15年以上(笑)」
――やっぱり時間がかかっている(笑)。
「僕は作りかけのまま放ってある曲ってほぼないんですけど、“アバウ”は断片だけがあって、どうにもできなかったんです。ガット・ギターと歌だけの当時のデモもMDに残っています。『Album』の最初のプリプロを2005年の終わり頃にやったんですが、収録する曲が足りないとわかり、2006年が明けてすぐに断片をリハに持っていったんです。でも、収録できるほどのものにはならなくて」
――その〈断片〉は具体的にはどのあたりなんですか?
「歌詞で言うと、〈ここへおいでよ〉から〈砂漠を掠めて〉まで。サビのような部分ですね。ライヴで未完成のままやったりもしました。結局『Album』には収録されず、そのときまた蓋を閉じたんです」
あの頃の三陸海岸の海へ、どうしても行きたかった
――では、“アバウ”は一度お蔵入りになっていたんですね。
「その後、歌詞に関わる話になってくるんですけど、2011年に震災がありました。僕は宮城の生まれなんです。10歳まで宮城にいたんですけど、親戚はいないので、その後遊びに帰るということもなかったんです。でも自分にとって、その時期のことは人生の中でいちばん大きい……みたいなんです。だから、心の中だけにあるふるさとのようで。それが災害があるたび、なにか壊されてしまったような気持ちを覚えて。東北の震災が起こったとき、すごく絶望感があったんです。本当に、〈損なわれてしまった〉という気持ちになりました。
その頃から“アバウ”のサビの部分を反芻しはじめたんです。なんだかひとに言うのが恥ずかしいんですけど(笑)。実は震災が起きる直前に〈そろそろGUIROを再開しよう〉って思っていたんです。でも震災があったので、できなくなってしまって。GUIROは2014年の終わりごろから動き出すので、3年くらいなにもしていなかったんだけど、その間ずーっとこの曲を反芻していました」
――それは歌詞の〈波〉や〈太平洋〉といった言葉から喚起されたんでしょうか?
「まさにそうです。〈太平洋〉って自分の中では三陸(海岸)の海なので。僕が唯一おぼえている校歌は宮城にいたときの小学校のもので、それがすごく好きなんです。冒頭が〈太平洋の磯馴松(そなれまつ)〉っていう歌詞で」
――まさに“アバウ”の歌詞ですね。
「うん。なので、〈磯馴松〉っていう言葉をその曲に織り込みたいということを考えていました。〈太平洋〉も、たぶんその校歌からきているんです。
GUIROを再始動しようというとき、昔の曲をやるだけではなく、やっぱりいまのものを提示したいって気持ちがありました。そのわりには仕事にかなりの時間を取られて、休んでいる間になにひとつ曲は作っていなかったんですけど。なんとか新曲を作りたいっていう思いからもう一度“アバウ”に取り掛かって、この形になったんです」
――髙倉さんの子どもの頃の思い出や宮城という土地の記憶と強く結びついている曲なんですね。海寄りの地域に住んでいらっしゃったんですか?
「そうです。その頃の三陸の海の思い出は、かなり鮮明に残っています。宮城には女川原発があるんですけど、僕がいた頃はそれすらまだ作られていなかった。だから、本当に海がきれいで。〈地元の人々の営みのため〉の範囲を越えた埋め立てが大々的におこなわれるようなことは、まだなかった時期でした。
震災をきっかけにそういうものが損なわれてしまったっていう気持ちが、そのとき特に強くなって。広い意味では〈失われる〉ことなんてないと思うんですけど、でも、その頃の海や波の記憶をもう一度見に行きたいって思うようになったんです。
そういうちょっとシリアスな背景があるので、あんまりひとに話すのも真面目くさくなってしまうし、楽しくないんです(笑)。それを知らないで聴いてもらってもいいなと思うんですけどね」
――そうですか? 背景を知ることも大事だと思います。では“アバウ”は、髙倉さんが震災が起こる前、さらには女川原発ができる前の三陸の海に再訪する曲でもある?
「僕はどうしてもそこに行きたくて。でも、行けないじゃないですか。〈どうしたらいいんだろう〉という気持ちだけがありました。リハが始まっても曲ができあがらなかったんですけど、やりはじめたら突然、前半部分がわーっと書けたんです。それから、それに伴うコードやメロディーがくっついていった」
――前半部分は詞先なんですね。
「たぶんあの思いが、よくわからないけど形になったのかな。なので、書いた後に自分で解読していく、という順番でした。〈焼け焦げた窓に〉っていう部分では、たぶん自分も丸焦げになっているんだと思うんです。魂だけを連れて行ってほしいから、その状態になる必要があったのかなと。肉体があったら、時間を遡ることはできないので。
〈鷦鷯(みそさざい)〉もなんで出てきたのかわからなかったんです。あるとき知り合いが〈ミソサザイっていうのは冥途の水先案内なんだ〉って教えてくれて。びっくりしましたね」
――記憶の中の土地に赴くということは、ある意味〈彼岸〉へ行くことかもしれません。
「そうですね。その頃のことを知らない小さなひとたちに、一緒に見に行こうよ、見せたいんだっていう感じの、そういう歌詞なのではないかなって思っています。
僕は詞から書けることってほとんどなくて、基本的にメロディーが先なんです。『Album』の頃まで、大事なところは言葉とメロディーが同時に出てくることもあったんですが、そこから広げていくときに言葉がメロディーに乗っていないと、やっぱり気持ちがよくない。だから、合う言葉をひたすら探すんです」
――音の面でも、意味の面でも?
「見たときの字面も意識しています。意味合いはぼんやりと自分の中で辻褄が合えばいいので、とにかく〈メロディーの抑揚にかちっとはまるか〉だけで作っています。だから、抽象的にしかならない。自分は詞が書けないからしょうがないって思っています」
――“アバウ”は髙倉さんにとって具体的なイメージを描いた珍しい曲なんですね。
「うん。『Album』の頃とは作りたいものがちがってきているんだろうって思います。“アバウ”がきっかけで、未完成のものを現場に持って行ってもなんとかなる感じがしているんです。いまは、できないなりの方法論で作ろうとしているところですね」