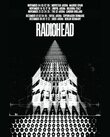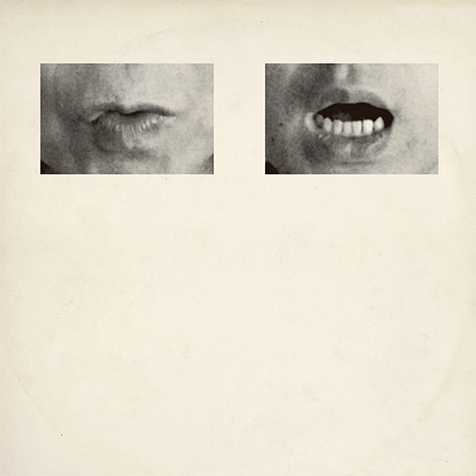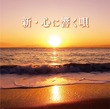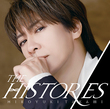この人ヤバいわ――ミトがスクエアプッシャーの音楽に開眼するまで
――まずはスクエアプッシャーとの出会いについて話していただけますか?
「最初に聴いたのは『Hard Normal Daddy』です。ただ、当時はドラムン全盛で、(LTJ)ブケムだったり、ロニ・サイズだったり、基本ジャズ・マナーでスペーシーなイメージのものが多かった中、スクエアプッシャーの『Hard Normal Daddy』は非常に特殊というか、最初はとっつきにくいイメージだったんです。
知り合いに誘われて、新宿LIQUIDROOMでの初来日公演(97年)にも行ったんですけど、その時はめちゃくちゃベースが上手い、非常に偏屈な方がやってらっしゃるんだなっていうイメージ(笑)。
その後に『Big Loada』を聴いたら、1曲目(“A Journey To Reedham (7am Mix)”)とかはすごくいい曲で、〈こういうのもっと作ればいいのに〉と思ってましたね」
――当時は〈コーンウォール一派※〉の周辺も一通り聴いていたわけですか?
「はい。ただしエイフェックス・ツインとは別物だと思ってました。入口が『Hard Normal Daddy』だったので、〈リズム・トラックをオケにして、ベースを弾く人〉という漠然としたイメージで、最初は『Big Loada』のような音楽をやってる人だとも思ってなかったので」

――そのイメージがどのように変化して行き、〈推し〉になっていったのでしょうか?
「『Music Is Rotted One Note』(98年)に入ってる“My Sound”とかでメランコリックなところが出てきて、“Iambic 5 Poetry”(99年作『Budakhan Mindphone』に収録)では結構バンドものになってましたよね。さらに『Go Plastic』(2001年)を聴いて、〈コンポーズもしっかりやる人なんだ〉と気づいてくる。
ただ、まだズドンと入ってくるところまではいってなくて、2001年の〈フジロック〉には、観に行こうとも思わなかった」
――今ではスクエアプッシャーを観るためだけにフェスに行ったりもするのに(笑)。
「そうそう(笑)。で、やっぱり決定的だったのは『Ultravisitor』(2004年)だと思うんです。あれを聴いて、トータル的なコンポーズ能力と、作家としてのすごさがわかったし、〈これ!〉ってなると他のことが見えなくなって、そこに邁進してしまう求道的な人間なんだと気づくわけです。それを理解し始めてから、〈この人ヤバいわ〉となったんですよね。
だから、私はリチャード(・D・ジェイムズ)も大好きですけど、流れとして全部一緒くたかっていうとそうではなくて、あの2人はいつも平行線をたどってるイメージがある。すごく寄った時期もあれば、離れた時期もあると思うんですけど、今はお互いいい感じの距離にあるのかなって」