
2012年にリリースした“Harlem Shake”がYouTubeで億単位の再生回数を叩き出し、世界の頂点に立ったプロデューサー、バウアー。トラップの様式美を確立した彼がこの度リリースするセカンド・アルバム『PLANET'S MAD』は、なんと90年代に勃興し、ケミカル・ブラザーズやファットボーイ・スリムらを代表格とするジャンル、ビッグ・ビートの再解釈を含んだ挑戦的な内容となった。
バウアーは、活動初期からトラップを基軸にしながらも、さまざまな要素をみずからの楽曲に盛り込んできた。そうした引き出しの多さに加え、クラブやフェス映えするトラックメイキングの手腕から、これまで数多くのメジャー・アーティストをプロデュース。その一方で、アンダーグラウンド系のレーベル、ラッキーミーからアルバムをリリースするなど、活動は多岐にわたっており、なかなか得体のしれない存在だ。
今回は、そんな一筋縄ではいかないバウアーの魅力を解読すべく、バウアー自身とも面識があり、トラックメイカーとしてのスタンスにおいても共鳴している日本人プロデューサー、Masayoshi Iimoriに登場してもらった。国内のレーベル、TREKKIE TRAXに所属し、DJスネークやディプロなどのレーベルからも楽曲をリリースしてきた彼は、アンダーグラウンドから登場し、世界に認められた数少ないプロデューサーの1人だ。
4月にリリースされ、多様なジャンルが詰め込まれたIimoriのファースト・アルバム『DECADE4ALL』の話題も含めながら、トラップがフェスティヴァルを席巻して久しいダンス・ミュージック・シーンの状況を伺った。なおIimoriは、緊急事態宣言中に制作の過程を生配信しながら完成させたEP『Wonky Rave』をちょうどリリースしたばかり。そちらもぜひチェックしてみてほしい。
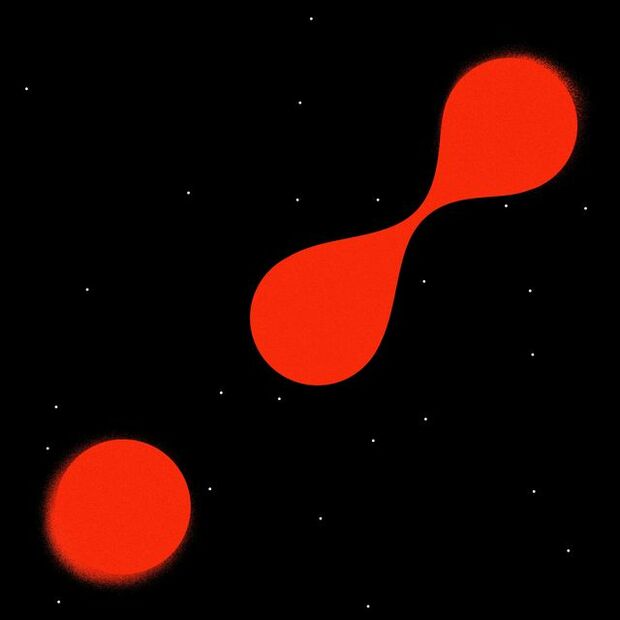
BAAUER 『Planet’s Mad』 LuckyMe/BEAT(2020)
すべてが混在していたトラップ・シーンの黎明期
――バウアーの曲とはどのように出会ったのでしょうか?
「まずバウアーを知ったのは2012年頃。この頃の初期トラップがいまだに好きなんです。どんなジャンルでも黎明期はおもしろいと思いますが、特にトラップはフェス向けのサウンドとアンダーグランドなビート・ミュージックが混ざっていたのがおもしろかった。
あの頃はYouTubeに曲が大量にアップロードされていて、それがすべて〈トラップ〉という括りだったから、いまやフェスティヴァルで超プレイしてるフロストラダムスやオーケー(Ookay)と、いまもアンダーグラウンドのカリスマであるシュローモやライアン・ヘムズワーズが同じ枠組みにいたことが好きだったんですよ。あの頃の空気感をすごく覚えています。
そこからトラップというジャンルが世界に根付いて、各々が自分のやりたいことを落とし込み、いまはフェスティヴァル・トラップ、EDM向けのトラップ、トラップ以降のヒップホップ、ニンジャ・チューンが出しているようなエクスペリメンタルなもの……と細分化していきました。それらが各方面において洗練されているのが現状だと思います」
――初めて聴いたバウアーの曲は何ですか?
「たぶん“Harlem Shake”かな。高校生の頃に海外で流行っていて、なんとなく聴いていました。ジャスト・ブレイズとの“Higher”(2013年)も、あまり世の中的には評価されなかった印象ですけど、自分はよく聴いた記憶があります。その後は、謎のネタものを出したり、精力的にリリースをしていてましたよね。たぶん本人も大ヒットした“Harlem Shake”に引っ張られすぎていて、その呪縛から逃れようと本当にやりたい曲をいっぱい出しているような印象でした。
それからリリースされたバウアーのファースト・アルバム『Aa』(2016年)は、トラップの集大成的なアルバムだと僕は捉えています。前半はフェスティヴァル・トラップ的なものを揃えていながら、後半に向けて徐々にヒップホップ的なトラップが混ざっていって、両方がうまくミックスされているアルバムなんです。ダンス・ミュージックとしてのバランス感で理想的というか、自分の楽曲制作でも参考にしていますね。リード・シングル“Gogo!”は、あそこまでトラップに世界観を持たせたのが革新的だなと思いました。あと、あのアルバムを出した頃のDJを観ると、僕がリリースした曲もDJでかけてくれたりしていて……ディグがすごいんです」
――いろいろ聴いてるんですね。
「大物のプロデュースもしれっとやっていて。フューチャーのビート作ったり、ジョージやリッチ・ブライアンなど〈88rising〉のアーティストにも関わったり、レンジの広いプロデュース力が好きです。たぶん本人も曲を作っていくなかで進化していったと思うんですよね」

































