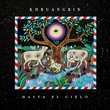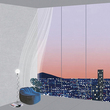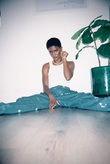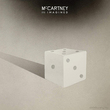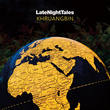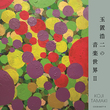〈クルアンビンらしさ〉は自分たちに正直にいること
――『Mordechai』で、歌詞以外にクルアンビンのサウンドに生じた変化は何だと思いますか?
DJ「うーん……、僕たちがずっと使ってきた色調のようなものは変わっていないと言いたいな。
マークがモーグ(・シンセサイザー)をこのアルバムではたくさん使っているからそれは結構効いているかもしれないけど。あとはオルガンのサウンドもこのアルバムでは使われているね。それ以外で明らかなのはヴォーカルの採用だと思うけど、ほとんどの部分では、他の人が僕たちらしいと感じるようないままでと同じやり方を貫いているよ。
僕たちは、どうやってアルバムにアプローチするかについてはとても敏感なんだ。このアルバムがどういうものになるか、自分たちならではの音を突きつめたり、自分たちらしさを隅々まで研究してみたりね」
――その変わらないように心がけた〈クルアンビンらしさ〉というのは具体的にはどういうことでしょう?
DJ「僕たちにとって一番大切なことは自分たちに正直にいることなんだ。デジタル・エフェクトとかそういったものは使いたくない。自分たちのオリジナルのサウンドに忠実でいたい。コードがあって、ベースがあって、ドラムがあってそこにいくつか要素を足していくっていうね。
レコーディングするものは、全てレコーディングしたサウンドと同じようにライブで再現できるものにするということが僕たちにとってはすごく大事。オリジナルのアイデアにいろんなものを足していっちゃう傾向もあるんだけど、あまりにもそれが渋滞したような状態になると、ライブで演奏したときにレコーディングしたものの縮小版みたいになっちゃうよね。
だから、自分たちのサウンドに忠実にいて、それが変わらないようにしている」
――マークさんとDJさんはチャーチでの演奏を通じて知り合ってクルアンビンの結成に至ったわけですが、現代のR&Bやジャズ・ミュージシャンにもチャーチを経験している人たちはかなりいますよね。あの場の独自性が日本に暮らす私たちにはまだよくわかってない部分もあるのですが、クルアンビンのサウンドの土台にもそういう影響はあるんでしょうか?
DJ「もちろんバンドのサウンドに教会での経験はかなり貢献してくれているし、すごく大きな影響になってる。前作も今作も教会で演奏していたときに書いたものが土台になっている曲が入っているよ。
マークと僕がほぼ同じセッティングで10年近く一緒に演奏をしてきたことが、音楽的なケミストリーも進化させてくれた。それは誰かに強要されたり急かされたりしてできることではなくて、時間をかけて得られるものだよね。教会で演奏していた頃から15年近くの月日が経っているからこそ、マークとステージを共にしていると彼がわざわざ後ろを向いて僕にどこへ向かっているかを伝えてくれなくても彼が向かっている先がわかるんだ。それは時間をかけて培った僕とマークの間にあるコネクションのおかげだと思う」
音楽は〈顔〉ではなく音楽が代表するべき
――そういえば、クルアンビンやローラさんのInstagramをいつも見ていて、特にローラさんに顕著ですが、ミステリアスな存在であった初期に比べるとこれまで以上に写真で目をはっきりと見せるようになっていますよね。マークさんも最近、目がはっきり写ってる写真がありました。何らかの気持ちの変化があるのでしょうか?
ローラ「どうだろう、どっちかっていうとアクシデントに近いんじゃないかな。うーん……自分たちの存在よりも音楽が優先されるべきっていう考えは常にある。自分たちの音楽は自分たちの顔ではなく音楽が代表するべきでしょ。だけどライブをしていくなかで、〈自分自身を自分たちがやっていることから隠さなくてもいい〉っていう自信はついた」
――新作がこうしてリリースされるというのに、新型コロナウイルスの影響でツアーがしばらく行われそうにないことが残念です。一昨年クルアンビンが出演して話題になった〈Tiny Desk Concert〉も最近は自宅配信がメインになっています。今後、この状況下でバンドとしてできること、トライしてみたいことをもし考えていたら教えてください。
DJ「いまのところ決まっている予定はないな。アルバムを仕上げてスタジオから出てきたばかりだから、レコーディングのことを振り返ったり、深呼吸をして自分たちに再び力を蓄える期間として捉えているんだ。
あといまはリモートでプロモーションをすることに集中しているよ。自分たちがやってきたことをなるべく多くの人に言葉で届けて、自分たちの音楽がこの状況をなるべくポジティヴなものにする助けとなるようにね」
角松敏生、石川セリ、幾何学模様……クルアンビンが好きな日本の音楽
――去年、DJさんにインタビューしたときに、最近チェックしたいい音楽を訊いたら、カナダの女性シンガー、ダイアン・テル(Diane Tell)を挙げてくれました。お2人が最近注目してよく聴いている音楽や作品があったら教えてください。
DJ「ああ、ダイアン・テルをお勧めしたのを覚えているよ(笑)。最近は僕らと同じヒューストン出身のサックス奏者、ロニー・ロウズ(Ronnie Raws)を聴いてる。70年代中盤頃からかなりたくさんのレコードを出しているんだ」
ローラ「私はグロリア・アン・テイラー(Gloria Ann Taylor)。残念ながらもう亡くなってしまっているんだけどね。R&B、ソウルが土台となっているんだけど、ファンキーでとても美しい。何枚かレコードを持っていてしょっちゅう聴いてる」
――来日時に発見したいい音楽はありましたか? Japanese City Popもチェックしているんでしょうか?
ローラ「私たちは世界中にあるいい音楽のファンだから! 実は最近いい日本のバンドを見つけてね。幾何学模様と何回かライブをしたんだけど彼らはすごくよかった」
DJ「彼らはかっこいいね」
ローラ「その他は……ちょっと待ってね。プレイリストを見るから……。わかった! 阿川泰子、石川セリ、当山ひとみ」
DJ「僕は角松敏生の“RUSH HOUR”って曲を聴いているよ。
Japanese City Popについても知ってるよ。ポップの復権が起こっているんだ。復権というより〈発掘されている〉と言うべきかな。日本や韓国、その他のアジア圏の国の楽曲がここアメリカで徐々に人気を集めだしているね。すごくクールだよ」
――再びクルアンビンがツアーに戻り、世界中の音楽ファンと笑いながらライブできる、つまりあなたたちのファースト・アルバムのタイトルである『The Universe Smiles Upon You』な状況が来ることを待ち望んでいます。インタビューに答えていただき、ありがとうございました。
DJ&ローラ「ありがとう!」