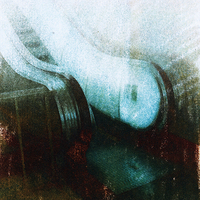2013年頃より電子音楽とヴォイスを主体とした新たなソロ・ワークを手がけてきたPhewによるニュー・アルバム『Vertigo KO』が、ワープ・レコーズのサブ・レーベル、ディサイプルズ(Disciples)より2020年9月4日(金)にリリースされる。5月に発表され即座に完売となったカセット『Vertical Jamming』の音源を加えた2枚組で、これまでCD-Rやコンピレーション盤などに収録されていた音源および新録をコンパイルした、テン年代の彼女の活動の総決算とも言うべき内容に仕上がっている。
Phewは70年代後半にアーント・サリーのヴォーカリストとして大阪の初期パンク・シーンで鮮烈なデビューを飾り、バンド解散後は主にソロ・ミュージシャンとして活動。坂本龍一やカンのホルガー・シューカイおよびヤキ・リーベツァイト、アインシュテュルツェンデ・ノイバウテンのアレクサンダー・ハッケ、大友良英、山本精一らとコラボレーションをする一方、Blind Light、Novo Tono、Big Picture、MOSTといったグループ/ユニットでも活躍してきた。2018年にはレインコーツのアナ・ダ・シルヴァとコラボレーション・アルバム『Island』を発表し、大きな反響を呼んだことも記憶に新しい。
期せずして世界を覆い尽くしたパンデミック下でリリースされる今作『Vertigo KO』は、テン年代中盤以降の彼女の足跡とその変化を克明に記録したドキュメントであるとともに、時代と共振するメッセージを内包した音楽としても聴くことができる作品となっている。直近では英国ロンドンのカフェ・オトがコロナ禍を受けて始動したレーベル・Takurokuから、6月に〈ロックダウン中の音楽〉を主題にしたミニ・アルバム『Can you keep it down, please?』もリリースしているものの、パンデミック以前より制作が進められ、ライナーノーツで彼女自身が「2010年代後半のある個人のドキュメンタリー・ミュージック」とさえ記している本盤が現在の社会状況と響き合うのは、あくまでも個別具体的な実践からすぐれて普遍的なテーマを捉え続けてきたからでもあるのだろう。
今回のインタビューでは新作のリリースを控えた彼女に、アルバムの制作プロセスはもとより、約5年間のソロ・ワークにおける活動の変化、そこから避け難く直面する〈慣れ〉を回避するための手段、あるいは西洋音楽的なるものから離れるという方向性、さらにはコロナ禍であらためて浮き彫りになったライブ空間および録音作品の意義などについて伺った。