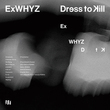沖縄出身のシンガー・ソングライターNazが、前作『JUQCY』からおよそ1年ぶりのEP『YUQCY』をリリースした。
沖縄の方言で〈嘘〉を意味するタイトルが冠せられた本作には、Naz自身が日々の暮らしの中で、心動かされたり悩まされたりしている〈嘘〉に向き合い作り上げた5曲が並んでいる。サウンド・プロデューサーには前作から続投となる冨田恵一(冨田ラボ)と江﨑文武(WONK/millennium parade)に加え、初のタッグとなるSeihoを迎えており、曲ごとに全く異なるサウンドスケープが広がっているのが特徴だ。彼女自身のルーツに根差し、ソングオリエンテッドだった前作と比べると、どこか掴みどころのないアブストラクトなメロディーが多いのは、レコーディング直前までの渡英経験と、今回から新たに導入した作曲ツールの影響も大きかったはず。19歳でデビューを果たしてから1年、日々アップデートされているNazの〈今〉が詰め込まれた一枚といえよう。
今回Mikikiでは、そんなNazのクリエイティビティを一番近くで支え続けてきた冨田、江﨑、そしてSeihoによる鼎談を敢行。新型コロナウイルスによる感染拡大が広がる中、試行錯誤を繰り返しながら行われたというレコーディング秘話はもちろん、コロナ禍で作品を作り続けることの意味など、アーティスト活動の本質に迫るような興味深いトピックで盛り上がった。


Nazが音楽的にどうしたいか
──冨田さん、江﨑さんはNazさんとデビュー時から関わりになりますが、出会った頃と今とでは印象など変わりましたか?
冨田「最初は僕のソロ・アルバムに彼女をシンガーとして迎え入れる形だったので(冨田ラボ『M-P-C “Mentality, Physicality, Computer”』収録曲“OCEAN feat. Naz”)、そこでは彼女の音楽性というよりも〈声〉が欲しかったわけですね。で、その後に彼女のファーストEP『JUQCY』を手がける上でも、割とソロでのフィーチャリングの延長というか。彼女の〈声〉がよく聴こえる音楽を歌ってもらえるといいなと思っていました。ただ、その時に彼女自身が作曲した曲(“Rain Wash”)をやる機会があったのと、何度か現場をご一緒していく中で、〈この子は割とロック好きだしUSというよりUK志向なのだな〉ということが分かってきたんですよね」
──なるほど。
冨田「それと、今作『YUQCY』を作る前に彼女はロンドンへ留学しているじゃないですか。そこでよりUK志向が強くなっていったのかもしれないなと思いましたね」
江﨑「僕が彼女と最初に会った時は、R&Bやソウル、それもUSっぽい音楽を聴く人なのかなと思っていたんですけど、冨田さんもおっしゃったように実は全くその辺は追っていなくて。〈私はトラディショナルなUKの音楽が好きなんです〉と言っていたんですよね。なので、前作では彼女のルーツにある音楽を軸に考えてプロデュースしたのですが、今回は留学から戻ってきたタイミングということもあってか、聴いている音楽の幅がグッと広がっていると思いましたね。Instagramとか見ると、Jojiの曲なんかもカヴァーしているし」
──インスタでは、シガレット・アフター・セックスやクランベリーズなどもカヴァーしていますよね。
江﨑「彼女自身が音楽的にどうしたいかということを、様々な視点から、より具体的に言えるようになっているなと思いました。そうやって自分のことを俯瞰的に見られるようになってきたのなら、こちらも彼女のルーツに寄せていくだけじゃなくて、僕自身の音楽性もぶつけてみようかなと思いながらプロデュースしてみました」
──Seihoさんは、今回がNazさんと初の関わりですよね。もともとはどんな経緯でプロデュースをすることになったのですか?
Seiho「NazちゃんのディレクターがもともとSugar's Campaignの担当で、〈今、ちょっと一緒にやりたい女の子がいるから〉と言って、彼女が14歳くらいの頃のオーディション時の映像リンクを送ってきたのがそもそものきっかけですね。実際に会ったのは、もうちょっと後になってから。沖縄でオーガナイザーしている、クラブ周辺の友人から紹介されました。冨田さんと江崎さんがおっしゃった通り、UKのダンスミュージックとかもすごく好きで。すごく幅のある子なのだなと思いましたね」

〈こういうサウンドにしたい〉
──今作の作業は、実際どのように進んでいったのでしょうか。
冨田「今回、僕が手掛けた3曲のうち“Bill”は彼女が確か中学生くらいの時に書いた曲で、どちらかというとUS寄りのフォーキーな曲調のデモが送られてきました。
後の2曲、“7-Knife(切)”と“cacao-dark”は割と最近彼女が作った曲で、作曲用のアプリなども使っているんですよ。そのため、〈こういうサウンドにしたい〉といった曲全体のイメージも、以前より具体的になっていましたね。
例えば“cacao-dark”にはかなり歪んだギターの音が入っていますが、おそらくNazさんのデモを聴いていなかったらああいうフレーズ入れてなかったと思う。そういう意味では、Nazさんのデモを起点にして新鮮なアプローチができたと思っています。もちろん歪みの感じとかは、今自分が好きなテイストに寄せていますけど。で、そういうところから〈じゃあ、プラグインとボコーダーでコーラスパートを新たにつけてみよう〉みたいなアイデアも生まれたりしました」
──ちなみに今回、Nazさんが使用していた作曲用のアプリというのは?
冨田「〈Auxy〉です。最近は、これで曲を作っている人も割と多いですよね。こういうツールなしでは“7-Knife(切)”や“cacao-dark”みたいな曲は作れないというか。ギターの弾き語りで作ってたらああいう曲は浮かばないでしょう。このアプリを手に入れたことで、彼女にとってのクリエイティヴィティはかなり上昇したんじゃないかな。きっと、彼女自身の創作意欲を掻き立てるフレーズもたくさん入っていたのだと思いますしね」

Seiho「僕は今回“I'll go to the moon”をプロデュースしたんですけど、最初のデモが送られてきた段階で音色やフレーズなど、さっき冨田さんがおっしゃったように彼女の中でやりたいことはすでにはっきりしていましたね。なので、そこからエッセンスを取り出して僕なりに料理していきました。結構、彼女が作ったデモに入っているシンセの音が良くて。〈これ、曲の中で大事な要素やな〉と思って再現するのに時間がかかりました(笑)。
ヴォーカルに関しては、オンマイクで歌うパターンや、少しマイクから離れて声を張って歌ってもらうパターンとか、ニュアンスのヴァリエーションなども色々試してもらいました。Nazちゃんは張って歌っている時も囁くように歌っている時も、高域の倍音がすごくきれいに出るんですよ。小さめの声で歌っている時のピッチの外れ方とかもすごくいいので、とにかく色々録りためておいて、その中からトラックにあうテイクをセレクトしていきました」
──彼女の声に対して、かなりフェティッシュなこだわりがあったのですね。そういえばSeihoさんは、コロナ禍直前にインドへ行かれていましたが、この曲の後半のインドっぽいフレーズはその影響ですか?
Seiho「そうだと思います(笑)。でも、割とデモの段階からビートルズ的というか、サイケな要素が結構あって。〈なんでこんなヘンテコなニュアンスなんやろ?〉と思ったんですよ」
冨田「ああ、確かに。彼女が送ってくるデモのシンセのフレーズとか、ちょっとサイケっぽいところがあった(笑)。親御さんがすごくUKロックがお好きだと言ってたから、その影響なのかもしれないけど」
Seiho「なので、僕は普段シンセの音ってドライに録ることが多いんですけど、今回はかなりリヴァーブをかけてサイケ要素を足したりしていますね(笑)」

Nazとコロナとプロデュース
──江﨑さんは今回“Bluebell”で、アレンジのみならず作曲も手掛けています。
江﨑「僕が作業を始めるタイミングではもう冨田さんとSeihoさんの曲が聴ける状態だったんです。なので、お二人とは全く違った雰囲気にしようと思いました。まずは僕の方で、ほとんどピアノ1台のみのアコースティックなデモを作り、それをNazちゃんに送るところから始まりました。〈私もこういうアコースティックな音像の曲もいいなと思って聴いていたんです〉という話もしてくれて、そこからはジャズ・ミュージシャンを後ろに従えて、ちょっとセッションっぽい要素も入れつつアレンジしていきました」
──江﨑さんがヴォーカル録りをする頃は、すでにコロナ禍だったのですか?
江﨑「そうです。本当はNazちゃんも含めたバンド一発録りがしたくて、そのつもりでスケジュールも組んでいたのですが、ちょうどコロナの第二波と重なり、彼女が沖縄から出てこられなくなってしまったんですよね。それで今回、僕にとっては初のリモート・レコーディングを行いました。Nazちゃんに沖縄のスタジオに入ってもらって、そこからZoomでつないでやり取りをしたんですけど、僕がモニターしたのは彼女の歌をiPhoneのマイクで拾った音だったんですよ(笑)。それでニュアンスとか判断するのは本当に大変で……。辛うじてピッチが分かるくらいで、〈エアコンついてない?〉〈車が通ったよね、今?〉なんて話しつつ(笑)、色々苦労しながらディレクションしたのが印象に残っています」
──オケはしっかり録ってあるのに(笑)。
江﨑「そうなんです。実は、奏者を集めて生でレコーディングをさせてもらえる機会って本当に今、少なくなってきていて。大抵はオケを作り込んで、個別できてもらって差し替えていくというやり方なので、今回は本当に楽しかったです。何ならピアノなんて2年くらい生録していなかったから、今回は本当に楽しかったです。
それと、デモの時点で〈こういう音を混ぜてみたいな〉と思ったアイデアを色々試す事ができたのも嬉しかったです。今までは弦の音も、割とハイファイに録ることが多かったんですけど、一旦メロトロン風のプラグインに取り込んで、テープの歪んだサウンドをレイヤーさせていくことが自分の中で流行っていて(笑)。ピアノの音も、最近はクリアなグランドピアノよりも壊れかけのアップライトのような音の方が惹かれるようになってきて(笑)。ハンマーの音がバシャバシャ鳴るような、状態の良くないピアノの方が情報量も多いというか、温かくていいなと思っているんです。それって、アンビエント・ミュージックの音楽家たちや、チリー・ゴンザレス以降のピアノ・サウンドという感じもありますけど、その辺りの影響がこの“Bluebell”にも入っていますね」
──そういったサウンドはプラグインを使って作っているのですか?
江﨑「そうです。劇伴の人たちがよく使っているプラグインには、そういう抽象的なサウンドを作れるものがたくさんあるんですよ。それこそハンス・ジマー周りとか、いわゆるポピュラー・ミュージック界隈で使われているものとはまた違う、ユニークなツールがたくさんあるんですよね。
プラグインといえば、これは後から知ったんですけど、レコーディング中の音をそのままリアルタイムでZoomに流し込めるモノがあるらしくて。DAW上で立ち上げて、Zoomのアカウントとリンクさせるらしいんですけど、その存在を知っていたらどれだけ先ほどのリモート・ヴォーカル録音が楽だっただろう……って思いますね(笑)」

──そういった作業面も含め、今作にはコロナウイルスの影響がどのくらいあったのでしょうか。
冨田「やっぱり、彼女が沖縄から出られなくなってしまったのは大きかったですね。沖縄は結構感染者数が増えた時期があったじゃないですか。それで予定がいろいろ変更になってしまった」
Seiho「僕は、コロナ禍の直前はパリにいたんですよ。2月中旬くらいだったかな。イタリアで感染者数がグッと増えたので、〈これはまずい〉となって帰ってきた。“I'll go to the moon”のデモをもらったのはその翌日だったので、日本ではまだそれほどコロナが深刻な状態ではなかったと思いますね。その後、どんどん状況は悪化していったけど」
江﨑「僕は5月とか6月にお話をいただいたので、本当にずっと家にいる状態でした。でも、家にいて音楽を聴く時間もたくさんあるし、そこでかける音楽も〈ノリがいい〉ということよりも、アンビエントよりの曲ばかりかけるようになって。〈自分が一人で落ち着ければそれでいいかな〉という感じの、なんならかかっているかどうか分からないくらいのサウンドの方が、今のムードに合うなと思っていました。なので、今回Nazちゃんに書いた曲も、割とそういう作風になった気がしますね」
冨田「すべての仕事において影響がないわけがなくて。僕のスタイルは比較的影響を受けづらいとは思うんですけど、それでもやっぱり、スタジオに来てもらう時間は短くする傾向にあったし。みなさんが帰られたあとは全面的に消毒してますしね。毎日、違うシンガーが歌いに来られるわけですから。
それと、これは話がちょっとずれるのかもしれないんですけど、今はコロナ前に作られリリースされた作品と、コロナの期間中に作られリリースされた作品が混在しているわけじゃないですか。それに対しては思うところが色々あります。世界規模で同じ問題を抱えながら、それが長期に渡る、という経験は多くの人にとって初めてだと思うので、今までになく、生きる上で根源的なことに意識的にならざるを得ないというか。コロナ以降は、個人的なこと以上に社会的なことに意識を向ける時間が長くなってると思いますね」
──確かに。テイラー・スウィフトの『Folklore』も、フリート・フォクシーズの『Shore』も、やはり独特のムードがありましたよね。
冨田「もちろんコロナ前後関係なく訴求力のある作品はあるという大前提あってですが、コロナの最中に制作された作品の多くには、今の空気が投影されてますよね。〈腑に落ちる〉という感覚がある。時代の空気を反映するというのもポップ・ミュージックの役割のひとつですから」
Seiho「あと、こういう時って多くの人が保守的になっていくのかなと思いました。リスナーとしての自分は新しい音楽を聴くよりも、コロナ前の音楽を聴いてノスタルジーに浸りたい気持ちが強くなるというか。〈ポップ・ミュージック〉っていうのはつまり既視感じゃないですか。みんなが既視感を持ちにくくなっているというか、共通言語がなくなりつつあると感じるからこそ、古いものでなんとかつながろうとしているのかなと。60年代のジャズなどを聴いてると普通に落ち着くんですよ。映画も新しく公開されたものより、古い作品の方がより見たくなったりして。作り手としての意見をいうと、このタイミングの方がいろいろ湧いて出てくるというか。〈ずっと曲を作っていられるな〉みたいなモードに入りましたね(笑)。そのギャップは常に感じていました」

──Seihoさん自身の作風は変わってきましたか?
Seiho「作っている時って気付いていなくて、やっぱり1年後とか2年後とか、あるいは10年後とかに〈そうか、あの時はこんなふうに考えていたのか〉と自分に対して思うのかもしれないです。僕は音楽を日記のように作っているので、〈とりあえずこの気持ちを書き留めておこう〉くらいにしか今は考えていないんですよね。で、日々それが積み重なって、何年か経って振り返った時に分かる。
思考の方が、圧倒的に音楽よりも遅いんですよ。思考の先に音楽があって、後から思考が追いつき、最後に〈理解する〉みたいな感じですかね(笑)。なので、今作っているものに関してはまだ思考が追いついていないんです。もう少し経ったら分かるのかなあ」
江﨑「僕は、ライブでたくさんの人の前に立つ機会も少なくなり、曲を作る時も、お客さんの前で演奏するイメージみたいなものが全然持てなくなってきて。〈みんなで盛り上がって聴く〉みたいなことが、分からなくなっていくような感覚がありました。コロナ期間中、何回かバンドで配信ライブもやったのですが、そのたびに〈再結成〉みたいな気持ちになっていたんですよね。」
──ある意味それが人間の〈適応能力〉なのでしょうけど、慣れていく感覚は少し怖いですよね。
江﨑「これまで私生活で関わっていた人とも、顔を合わせることもかなり減って、家族くらい距離感が近い人のことしか分からなくなるというか。それによって、自分が作る音楽もどんどん内向的になっていきましたね。作るもの全てが半径3メートルくらいにいる人々のため、というサイズ感になっている。状況がもう少し変わってきたら、ポジティヴな音楽を作るようになる気がしますけど。しばらくはこの感覚が続くのかも知れないです」

──この期間でないと、絶対に作れない作品がどんどん生み出されていることは間違いないですよね。そんな中、今後Nazさんにどんなことを期待しますか?
冨田「僕が考えていたのは〈Nazの音楽性はこうです〉みたいなものを、まだ固定する時期ではないのかなということです。今回僕が手掛けた3曲にしても、”Bill”のようにメロディーとシンプルな和声という曲の骨格と声だけをフィーチャーしたようなアプローチもあれば、曲の骨格よりもトラックがムードを演出するものもある。ジャンルなど気にせずに、いろいろトライしてみる方がいいんじゃないかなと僕は思っています。さっき江﨑さんもおっしゃっていましたが、今作もプロデューサーが3人いるわけだし、僕も統一感を求めるよりは可能性を広げていく方向で考えていました」
Seiho「プロデュースする時の大事なことって、例えば上司と部下の関係もそうですが、〈こうしたらいいよ〉みたいに具体的にサジェスチョンしてしまうと、伸びなくなっちゃうんですよね。本人が行きたい方向の道筋を作ってあげて、目的地まで自分で到達しないと意味がないというか。Nazちゃんに対しても、〈ああ、そこはこうした方がいいのにな〉〈こっちの曲調の方がええのに〉とか思う時もあるけど(笑)、それって本人が〈やりたい〉って思ったり〈私が向いているのはこっちだな〉って気付いたりするものじゃないですか。今はまだ、どこへ進んで行くべきなのか人も周りも誰も分かっていない状況で、それがすごく面白い。とにかく今は、選択肢を増やしていってほしいです」
冨田「もちろん、彼女自身も前作では割と様子を見ていたというか。僕と文武さんではプロデュースの仕方も全然違うわけじゃないですか。僕はほとんど自宅スタジオで完結させるけど、文武さんの場合はスタジオに入ってミュージシャンと〈せーの〉で録るわけだし。そうやって、いろんなレコーディングのやり方を体験するのはとても有意義だったはずですよね。
彼女が今、何をどう考えているのか分からないけど、どんどんいろんな音楽を聴いて学んでいってほしい。今は曲作りのための新しいガジェットを手に入れ、それが面白くて色々試している時期だろうし、それで彼女の音楽はどんどん魅力的になっていくと思うけど、自分の声がスペシャルである事は絶対忘れないでほしい。そのスペシャルな歌を、もっと良くするにはどうしたらいいのか、これからも追求し続けてくれたら嬉しいです」
江﨑「今、彼女って20歳なんですよね。自分がその年齢の頃を思うと、もう彼女は充分色々なことをやっているとは思うんですけど、アプリで簡単に音楽が作れるようになった反面、音楽の楽器的な観点からの要素が掴みにくくなっているところもあるのかなと。これからライブをやっていく上で、楽器を演奏している人とのやりとりが増えてくると思うし、そのときに楽器奏者との共通言語が持てるようになっているといいのかも知れないですよね。まだしばらくは人前で演奏する機会も少ないと思うので、このステイホーム期間中にいろんな楽器に触れる機会を作ってみてほしいです」