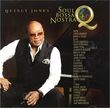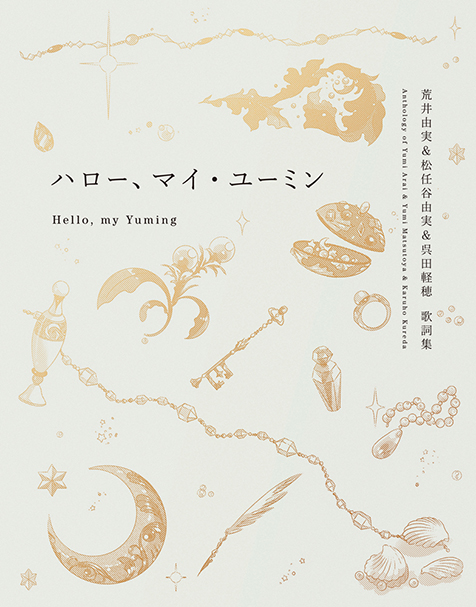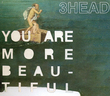アイアンサイド・オブ・クインシー・サウンド
2024年11月3日のクインシー・ジョーンズ氏逝去を受け、その後さまざまなメディアで追悼企画が実施された。私もあるラジオ番組では解説を求められ、また自分のサイトでは特集記事のリリースもした。音楽プロデューサーというカテゴリーでは間違いなく世界一著名であり、見合う実績も備えたクインシーにはビジネス面でのトピックも多かった。しかしその実、彼は紛れもない音楽家であった。そう、彼はスコアを書き、コンダクトするアレンジャー出身のプロデューサーなのである。本稿では彼の音楽的側面について解説していこうと思う。
70年代中盤以降、クインシーは演奏、作編曲などに関わることがほぼなくなった。肩書き通りプロデュースに徹する形となり、企画、選曲、人選、スタジオでの指示、サゼッション、ジャッジ、に全力を尽くしたのだ。しかしそうしたスタイルにも関わらず、彼が制作した作品はどれもクインシー・サウンドといえるものだった。この事実こそがクインシー・マジックなのだが、音楽家クインシーを語るにはもう少し時代を遡らなければならない。50年代からのビッグ・バンド作品が解説には最適だが、その完成形とも言える60年代末から70年代初頭のサウンドトラック作品を題材としよう。もっともポピュラーなのは「鬼警部アイアンサイド」(原題:Ironside)のテーマ曲ではないか。ある程度の年齢の方であれば吹替テレビ放映をご覧になっていただろうし、「ウィークエンダー」というバラエティ番組での使用を思い出す方はさらに多いかもしれない。
曲冒頭からの流れで説明していく。まずは音楽的な、というか譜面的な観点から見れば、スコアリングはたいへん綿密だ。冒頭の不協和な和音もインストゥルメンテーション(楽曲を構成する各音符を各楽器にどう割り当てるかなど)の的確さにより、不協和なはずの和音を整然と響かせている。しかもその和音は3パートに分けられ、ごく短い時間差で提示、重なったときに一つのコードを構成するという小技も効かせているのだ。コード自体が持つ不穏さにプラスして、3パートを16分音符一つずつズラすことによってスピード感、緊迫感を加えた演出である。そしてその後すぐ耳に入ってくるのがシンセサイザーによるサイレンを模した音だ。伝統的なアンサンブルに当時最新鋭の楽器であったシンセを加えるといったアイディアに、クインシーのプロデューサー的視線も感じる。そしてこのシンセ音こそが曲を象徴するサウンドとなり、刑事ドラマに最適でイヤー・キャッチなコマーシャル・フレーズとして機能するようになっているのだ。オープニング早々、最新の音色による象徴的なフレーズをフィーチュアし、そのバックグラウンドでは綿密な伝統的アンサンブルによる的確なムードが提供されているという構造。これ以上効果的なイントロはないだろう。同部分ではスネアによる16ビート連打のクレッシェンドと、予想に反してさらに不協和を加速させるベースによるルート音提示にもハッとさせられる。しかもここまでは曲冒頭からわずか9秒間での出来事だ(『Smackwater Jack』収録ver.)。
そして00:10、前述「ウィークエンダー」でもアタックとして使用された有名なトゥッティ部分が登場する。この部分も和声的には不協和と言えるが、的確なスコアリングとタイトな演奏によって音楽的にはスムースな表現となっており、我々リスナーには〈緊迫感〉というムードが何より先に提示される。アレンジや演奏の技量、熟練はそういった目的のために必要とされる。音楽内容のいずれかに着目させるのではなく、目的とする表現、ムードを余すところなく、かつ深く届けるために必要なのである。