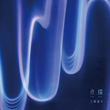自身の内面を深く見つめ、たった一人で作り上げた傑作『告白』(2018年)のリリースから3年。butajiから、ついに新作『RIGHT TIME』が届けられた。
前作とはうってかわって、『RIGHT TIME』は数多くのゲストとの共演や共作を軸にした、賑々しく華やかなポップアルバムだ。ジム・オルーク、石橋英子、tofubeats、折坂悠太、STUTS、壱タカシ……活動するフィールドの異なる音楽家たちがさまざまな形で貢献し、『RIGHT TIME』のサウンドを多彩で多様なものにしている。
では、『RIGHT TIME』が表現しているものとは? butajiはここで、どんなことを歌っているのか? 『告白』のリリース以降、ドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」の主題歌“Presence”の制作でも脚光を浴びたbutajiに、『告白』から『RIGHT TIME』へと至る道のり、そして『RIGHT TIME』に込めた思いをじっくりと語ってもらった。

〈認められたら〉から〈自分を認める〉へ
――『告白』をリリースしたあとの感触はいかがでしたか?
「デリケートなものとして扱われていた感じはするかな。多くの人に届いたものじゃなかったけど、聴いてくれた人はとても大事にしてくれた、という印象ですね」
――その後、一人で作った『告白』からバンドで録音したシングル“中央線”(2019年)へ、という変化には驚きました。
「“中央線”は、実は『告白』が完成する前に出来ていたんです。でも、アルバムに入れるべきじゃないと思って、シングルにしました。
『告白』の反動だったのかな? 『告白』で表現したものとはちがうものを作るとしたらどういうものになるかな、と考えながら作ったところはあったかもしれません。“中央線”が『告白』に対してどういうアンサーになっているのかは、具体的には言いがたいですし、〈なにかが示唆されている〉くらいの作品だと思うんですね」
――本当にただの反動だったのでしょうか? 『告白』から“中央線”への変化は、もっと深くて大きなものだと僕は思ったんです。
「(『告白』の)“秘匿”に〈認められたら〉という歌詞がありますけど、そこから主体的に自分を認めることに主題が移っていったんじゃないかな。『告白』は、手に負えないものを手にしたい葛藤だったり、過去と現在の自分との乖離だったり、その距離感についての葛藤だったりを表現していたんです。でも、“中央線”では、だれかに自分をOKしてもらうんじゃなくて、自分で判断をくだしてOKをしていく――そういう切り替わりがあったかもしれないですね」
〈自分自身の表現〉なんて大それたものはないと思っているんです
――“中央線”は、音楽的にも『告白』とは異なっていますよね。すっきりした音像で、爽やかでポップなフォークロックサウンドと力強いストリングスやトランペットが特徴です。
「僕がパソコンで音楽を作りはじめた頃は、聴いたことのないもの、だれも作ったことがないものを作ってみたくて、挑戦心や野心、好奇心があったんです。もちろん、今もないわけじゃないけど、それがちょっと薄れてきたんでしょうね。自分の記名性を手放したというか。自分を満足させるためのこだわりが表現においてどこまで有効なのか? それは手放してもいいんじゃないか? “中央線”でやったことは、そういうことだったのかもしれません。
そこで、なにが自分の表現の柱になっているかと考えて、歌詞に重きを置きはじめたんです」
――つまり、『RIGHT TIME』で試みているように、演奏やアレンジを他人に任せていく、ということ?
「でも、結局、(“中央線”では)譜面もストリングスやトランペットのアレンジも、全部自分でやっているんですけどね。ただ、音像は宅録のものとはまったくちがう。
自分が想定するものよりいいものを作ろうと思ったら、ある程度コントロールを他人に委ねていく、お任せしなきゃいけないんですね。つまり、他人に任せたものを自分がOKする、ということに挑戦したんです。自分一人でやったら、自分が想定したものしか出てこないので、他人に委ねることによって、作品が大きな広がりを持つことができるかもしれない、という期待があったんですね」
――『RIGHT TIME』は、まさにそういう作品ですよね。パーソネルを見ると、とんでもない数のミュージシャンが参加しています。
「『告白』のクレジットは3行ぐらいでしたからね(笑)。対極です。
“中央線”という曲をすでに持っていたからこそ、『告白』ではあそこまで深く掘り下げられたのかもしれない。『告白』を作っていた段階で、〈次の作品をどう作ろう?〉と構想を練っていたからこそ出来たものだと思います。暗中模索の状態で作品は作れないので、常に俯瞰の視点があるんですよ」
――おもしろいですね。あれほどまでにご自身の奥深くに沈みこんだ作品を一人で作りながら、ちゃんと客観視されていたというのは。
「そういうものなんじゃないかな。僕は、〈自分自身の表現〉なんて大それたものはないと思っているんです。自分が大事にしているもの以上に、もしくはそれとおなじように大事にされるべき他人や物事があると思うので、今回は他の人を招いて、その人たちにOKをしたかったのかもしれません」