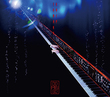「メトロイド」や「ドクターマリオ」「MOTHER」シリーズなど数々の人気ゲームの音楽を手がけ、またテレビアニメ・映画「ポケットモンスター」主題歌の作曲者として、さらに近年ではChip Tanaka名義でのアーティスト活動など、多岐にわたる作品で世界的に知られる音楽家、たなかひろかず。彼が1980~1990年代に残した多くのデモテープやプライベート録音までを編集し、CDで2021年に発売した『Lost Tapes』が好評を得、それに続く決定版ともいえる『More Lost Tapes』が50曲入り2枚組CDで2024年7月24日に発売された。これを機に、監修者として膨大なテープから選曲作業に携わってきた佐藤優介が、たなかひろかずに話を訊いた。 *Mikiki編集部
世界的作曲家のルーツ
──まず、ひろかずさんのルーツ的なお話から伺いたいんですが、子供のころ、学生時代にはどういった音楽を聴いていましたか。
「小3くらいのころに、テレビでザ・モンキーズのドラマ(1967~1969年に日本で放送された『ザ・モンキーズ・ショー』)を見て、その影響で初めて洋楽のレコードを買うっていう経験をしたのかな。当時380円くらいだったと思うけど。当時やっていたアメリカのドラマで『わんぱくフリッパー』(1966~1968年)とか『ローハイド』(1959~1965年)とか、テーマ曲やBGMは自然と耳にすることはあったけど、意識的に聴くようになったのはザ・モンキーズが最初だったと思う」
──バンド活動もされてたんですよね。
「中学生になってからいろいろバンドをやるようになって。楽器は主にドラムだったり、キーボードもギターも何でもやってた。その後、10代後半からハイウェイっていうバンドに参加して、〈日清ハッピー・フォーク・コンテスト〉に出場したら優勝して。それでバンドはデビューするんだけど、僕はやめて任天堂に入った」
──そのときの担当楽器は?
「キーボード。主にローズピアノとエーストーンのオルガンで。ライブではレスリースピーカーも持ち込んで演奏してた」
──バンドでは作曲もされてたんですか。
「そのときは演奏だけだね。バンド時代は、スターダスト☆レビューの前身バンド(アレレのレ)ともツアーを一緒に回ったりして。当時の自分の周りにはドラマーの菅沼孝三くんとかもいて、当時の大阪のミュージシャンは、後にスタジオミュージシャンになっていった人も多い」
たなかひろかずの音楽を構成する物悲しさ、呪術的低音、偶然性
――それが1970年代の終わりごろでしょうか。それから任天堂に入社されて。
「そうですね。入社当初はエンジニアとして、作曲家じゃなく玩具の音担当者という感じだった。そのころは任天堂って、まだおもちゃ屋さんっていう認識。自分も昔から任天堂のおもちゃで遊んでたからね、光線銃とか、N&Bブロックとか」
──ひろかずさんのゲーム音楽を聴いていると、いわゆるゲームらしい、楽しいサウンドの中に、ちょっと物悲しさというか、切なくて美しいメロディーが入ってくるのが印象的で。作曲の際、そういう対比とかっていうのは意識されますか。
「いや……あんまりないなぁ(笑)。でも、そういう切ない情緒的なものって、自分が子供のころに特に敏感だったというか。親と離れて不安になる気持ちとかね。童謡でも“ドナドナ”みたいな物悲しい曲が好きだった。なんかね、子供みたいに生命力が強いときほど、孤独感、喪失感とかそういうものに反応的だったような気がする」
──その感覚はよくわかります。
「だから若いころの方がそういう切ない曲をより好んで聴いてた気がする。あと3コードのブルースを基調とする音楽は、若い頃はあんまり好きじゃなかったのに、最近は1950~1960年代ごろのそういうアメリカ音楽をよく聴いてる。一方でテクノっぽいこともやったりするんだけど(笑)」
──そのバランス感覚というか、いろんな音楽が聴こえてくるのがひろかずさんらしいというか。
「あとは10代後半から恐ろしくレゲエにはまったので、ああいう低音が強く出てるようなものが好きっていうのはある。それはテクノをやるにしてもそうだけど。レゲエの、あのベースの低音に何か潜んでるような気がして。音数も少なく、ただリズムがうねってるだけなんだけど、ちょっと呪術的な感じというか。そこに感化されて、ベースで引っ張っていく、低音重視の音楽づくりっていうのが自分の中にあると思う」
──その呪術的っていうのは、ひろかずさんの音楽を聴いていると、低音の話に限らず、すごく感じる要素なんです。さっきの切なさとか、綺麗なメロディーの話をしましたけど、その一方でキーもコードもわからないような、すごくアバンギャルドな要素もあって。
「それは当時のゲーム音楽の作り方というか、制作環境も関係してる。基本的に数値を打ち込んで作っていくんだけど、その数字の羅列を、試しにめちゃくちゃに打ち込んでみるとか。例えるなら、楽譜をビリビリに破って適当につなげるみたいな感覚で。出てくる音の結果を予測せず適当に打ち込んでいくみたいな」
──ランダムな、偶然性の音楽というか。
「そうそう。それで面白い音があったらつなげていく。『ドクターマリオ』(1990年)とか、『MOTHER』(1989年)でもそういう作り方をよくしてた。もっというと、音楽を鳴らすシーケンサーそのものを自分でプログラムしていた。昔のゲーム音源は元々、音色のバリエーションは少ないけれど、それ以外の要素を自由に試せる環境を自ら作っていた、というのが大きかったのかなぁ」