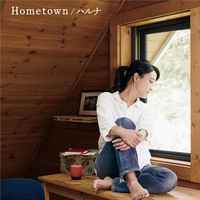シンガーソングライター、ハルナがこのたび初となるフルアルバム『Hometown』をリリースする。その名を目にして、ひょっとしてあの彼女?とピンときた人もいることだろう。平井堅、中島美嘉、松任谷由実、坂本真綾、JUJU、Kinki Kids、嵐など数多くのアーティストのバッキングボーカルを務め、CMソングや映画音楽などさまざまなフィールドで活躍してきたシンガーである。現在は、山下達郎の3年ぶりとなるホールツアー〈山下達郎 PERFORMANCE 2022〉に参加して全国を飛び回っているバックコーラスの歌姫が、どんな音楽性の持ち主で、またどんな世界観を描く表現者であるのか、そこまで把握している人もそうはいまい。
アルバムに触れてみてまっ先にイメージしたのは、キャロル・キング、ジェイムズ・テイラーといった、ハートフルで温かみのある音色に彩られた70年代米国シンガーソングライターの諸作品。アーシーさとアーバンさが絶妙に混じり合ったサウンド、ふくよかで栄養価の高いグルーヴなど、あの時代に生まれた名曲たちが携えていた香りや空気感を現代的によみがえらせようとする意志がそこかしこで働いているのを発見できる。つまり、アルバムタイトルから読み取れる印象そのものがそこに広がっていた。
プロデュースおよびギターを担当するのは、佐橋佳幸。この説明で感触がだいたい掴めるんじゃないかと思う。ほか参加メンバーに、キーボードの柴田俊文、そしてコーラスの三谷泰弘、ENA☆など、達郎ツアーバンドの面々が顔を揃えているのも注目ポイントだろう。さらに、ドラムスに坂田学、ベースに鹿島達也、バンジョーとフィドルに有田純弘も参加しており、それぞれ日本の第一線で活躍する豪華なメンバーで構成されている。
山下達郎さんにルーツをズバッと言い当てられたんです
――まず、一聴して感じたのは、ヴァレリー・カーターのアルバムの横に並べたい作品だなぁ、ってことでした。
「嬉しい~。ありがとうございます!」
――ルーツが透けて見えてくるところもそうだし、言いたいことがことごとく明確になっている点がまた爽快感を与えてくれる。ご自身の手ごたえはいかがですか?
「まずアルバム制作に辿り着くまでの経緯からお話したいのですが、16歳から27歳までバンド活動をしていて、ずっとオリジナル曲を演奏していたんです。解散後はサポートの仕事が中心となり、1年に何本もツアーに関わらせてもらうようになりました。そして、忙しくなるにつれて曲を書く作業がどんどん隅に追いやられていったんです。ただ、書きたい!という創作意欲が消えることはありませんでした。
15、16年ぐらいそういう生活が続き、2015年に山下達郎さんのツアーバンドに参加させてもらう機会を得るんですけど、そこからですね、自分の音楽にちゃんと向き合っていないといけない、って気持ちが芽生えたのは。ツアーに参加できたおかげで、佐橋(佳幸)さんや柴田(俊文)さんらと出会い、改めて自分のルーツを探る旅を始めるきっかけを与えてもらったんです」
――彼らに背中を押してもらうようにして、ふたたび曲を書き始めたというわけですね。
「そのデモを達郎さんに聴いてもらったんです。そしたら〈あなた、キャロル・キングみたいな曲書くね〉ってズバッと言い当てられたんですよ、私のルーツを」
――ズバッときましたか。どんな曲だったんですか?
「“ホームタウン”の原曲ですね。それと“You already have(仮)”。こちらは花澤香菜さんに提供した曲(“ゆうのそら”)です。その頃はまだ迷いのなかにいて、まだまだうまく自分を表現できていないな、と感じていたのに、私がもともと持っていたものを簡単に見抜かれてしまった。その出来事が衝撃的すぎて。
そのデモも何か狙って作ったわけじゃないんですよ。せっかく達郎さんに聴いていただくのだから、ありのままの曲を聴いていただきたいと思って」
――自然と本質の部分が出てしまっていたってことでしょうね。
「なんだ、私そのままでよかったんだ、と思った。いろんな方のサポートさせてもらいながら、もっと自分を飾ってみせたほうがいいのかな?と考えた時期もありました。でも飾りなんか全部取り払って、昔からのスタイルで作ったものを聴いてもらおうと決心できたんです」
――大丈夫だよ、と太鼓判を押してもらえたと。
「そうかもしれない。とにかく初めての感覚でした。10代の頃はありのままの自分をさらけ出そうとすると、稚拙な部分をダメ出しされることが多かった。たしかに技術もないし、そうか私はダメなんだ、って劣等感を持ってしまっていたんです。バンドメンバーにフュージョン好きが多かったんですよ」
――なるほど、テクニシャン揃いだったんだ。
「そうなんです。私がめざしていたものとは真逆だったんです。シンプルなサウンドが好きでしたから」